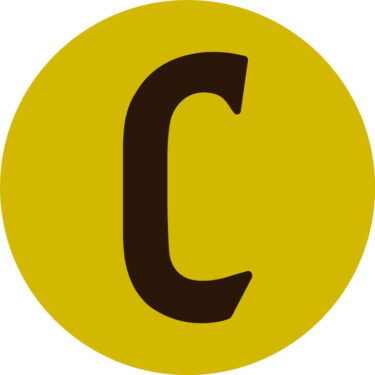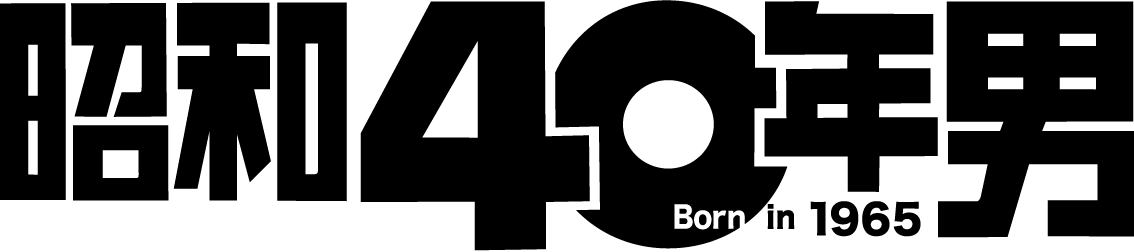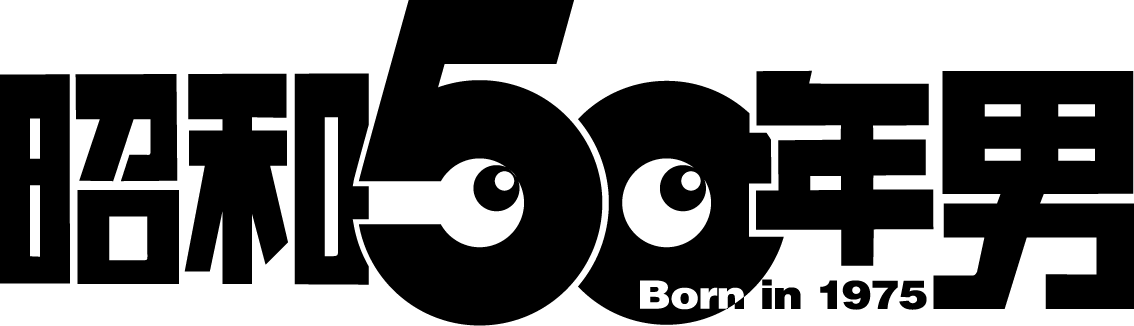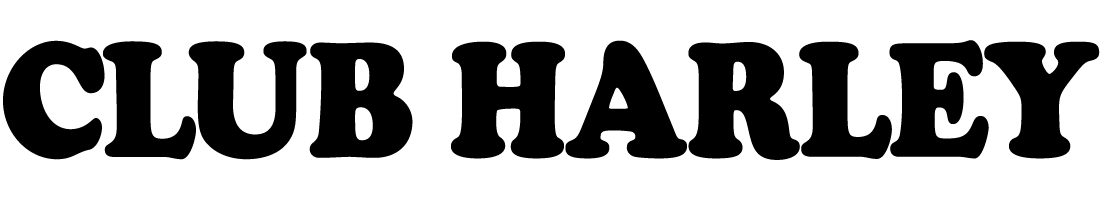1985年は、スピルバーグにとってのターニングポイント

スティーヴン・スピルバーグと言えば、映画に詳しくない人でもその名はわかる、ハリウッド映画界のスーパースター監督だ。1975年の『ジョーズ』で世界に衝撃を与え、その後も『未知との遭遇』(77年/日本公開78年)、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(81年)、『E.T.』(82年)、『インディー・ジョーンズ/魔宮の伝説』(84年)と世界的ヒットをコンスタントに飛ばしてトップランナーに君臨した。そして、『魔宮の伝説』の翌年になる85年には、〝製作総指揮〞の肩書で、映画史に残る名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー(BTTF)』(ロバート・ゼメキス監督)を含む4作品を世に放ったのだ。昭和50年男であり、生まれて初めてスクリーンで観た映画が、ドライブインシアターでの『E.T.』だったという映画監督の佐々木誠は、この1985年がスピルバーグにとって最も重要なターニングポイントなる一年だったと振り返る。
「85年のスピルバーグは『BTTF』や『グーニーズ』(リチャード・ドナー監督)など、製作総指揮で大活躍だったんですが、劇場用映画も1本撮っているんです。それが、ウーピー・ゴールドバーグ主演の『カラーパープル』(日本公開86年)。ピューリッツァー賞を受賞したアリス・ウォーカーの同名小説を実写化した、黒人差別問題などを扱う硬派な文芸作品だったんですけど、それまでの娯楽に徹したスピルバーグ作品とは肌合いが違いすぎて、ファンは戸惑ってしまった。それに同業者のやっかみもあったのかもしれないけど、アカデミー賞でも無視されてしまったんです。スピルバーグとしては、『1941』( 79年/日本公開80年)が興行的に大コケして以来の挫折だったと思います」
そして、85年のスピルバーグは、もう一つ監督作品を残している。テレビシリーズ『世にも不思議なアメージング・ストーリー』の一篇「最後のミッション」がそれだ。佐々木はこの作品が、当時の時点でのスピルバーグの集大成だと指摘する。
「まだ売れる前のケビン・コスナーやキーファー・サザーランドが出ている、第二次世界大戦のアメリカ軍の戦闘機乗りが主役の密室劇なんですけど、それまでスピルバーグがやってきたことが結構詰め込まれている。まず第二次世界大戦を描いていて、敵がナチスで、あとはちょっとディズニーっぽい演出がある。45分くらいの短編なんですけど、これは見応えがありますよ。あと、85年で押さえておきたいのは、製作総指揮作品の『ヤング・シャーロック/ピラミッドの謎』(バリー・レヴィンソン監督/日本公開86年)。これはCG技術を使った最初期の作品です。僕は子供の時に映画館で観て、ステンドグラスの中から描かれた騎士が飛び出てくるっていうすごい映像があって。まぁ今考えたらちょっとショボいCGなんだけど(笑)、当時はびっくりしましたね。これは後々の『ジュラシック・パーク』(93年)につながっていく作品ですよね」
偶然成功してしまった〝映画作家〞
膨大なフィルモグラフィーを誇るスピルバーグ作品のなかでも、ややもすると忘れられがちなタイトルに目をつけている辺りが、筋金入りのスピルバーグファンらしい。そんな佐々木監督に、スピルバーグの監督としての魅力について訊いてみた。
「まず強調しておきたいのは、スピルバーグって〝娯楽映画の王様〞みたいな言われ方をしてますけど、本当は筋金入りの〝映画作家〞なんですよね。たまたま大成功してしまった映画作家なんです。魅力はいっぱいあるんですけど、第一に、過去の作品や巨匠監督からの影響を隠さない点です。まずディズニーからの影響があって、ジョン・フォード(※1)、デヴィッド・リーン(※2)、フランク・キャプラ(※3)、ハワード・ホークス(※4)、あとジョン・スタージェス(※5)。これらの監督たちからの影響が上手いこと絡み合っているというか、自作でリミックスしているんです。似たような性質の監督にタランティーノがいますけど、あの人は香港映画とか日本映画とか、どちらかというとサブカルチャーからの影響ですからね。それに対してスピルバーグは全部王道。それを上手いこと映画の映像表現に落とし込んでいる。あとは自分の出自。ユダヤ人っていうことで、差別されてきたという思いがあって、それに対する問題意識が作品に色濃く反映されてますよね」
※1…1894年生まれ。『駅馬車』などで「西部劇の巨匠」と呼ばれる。73年没。
※2…1908年生まれ。『戦場にかける橋』『ライアンの娘』など、大作で有名。91年没。
※3…1897年生まれ。社会風刺とヒューマニズムにあふれる作風を得意とする。91年没。
※4…1896年生まれ。男の友情や闘いをテーマにした骨太な作品が多い。77年没。
※5…1911年生まれ。『荒野の七人』『大脱走』など、名作西部劇やアクション映画を数々演出。92年没。
スピルバーグの作品の特徴は、細かな映像表現にも見ることができると言う。
「映像演出で言うと、必ず絶対出てくるのが、シルエットですね。影の使い方が上手い。『インディ・ジョーンズ』シリーズなんか、インディのシルエットが出てくるシーンが絶対あるんですよ。夕陽をバックに登場人物や被写体を浮かび上がらせる。それは完全にデヴィッド・リーンの『アラビアのロレンス』(62年)や『ドクトル・ジバゴ』(65年/日本公開66年)の影響だと思います。スピルバーグは映画を撮る前に、その2本と、フランク・キャプラの『素晴らしき哉、人生!』(46年/日本公開54年)は必ず観直すって言ってますからね。『すげえ影響を受けてんだな』っていうのは、『アラビアのロレンス』を初めて観た時に逆に思いましたからね。『カラーパープル』にも夕陽をバックにしたシーンがあるし。シルエットをいかに際立たせるかというのがスピルバーグだと。そういうシーンがほぼあるんで、あれを観るとスピルバーグの映画だなって思います。あとはアクションシーンのカットバックが上手い。『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』(89年)の、戦車の中と外で同時進行するアクションのカットバックとか、『カラーパープル』でも、主人公のウーピー・ゴールドバーグが、悪い夫のダニー・グローヴァーの髭を剃っているうちに思いが込み上げてきて殺そうとするカットと、もう一人の女がそれを止めようと走ってくるのをカットバックするとかね。そういうカットバックでサスペンスを盛り上げていくのはやっぱり上手いですね」
なくてはならないJ・ウィリアムズの音楽
次は、映像に次いで重要な要素である音響・音楽について語ってくれた。
「まず音響ですが、たとえば『インディ・ジョーンズ』の銃の音って独特なんですよ。コミックっぽいんだけどちょっと重厚っていうか。鞭の音も、スピルバーグのチームが開発したもので。常に音響にめちゃくちゃこだわっている。その甲斐があって、アカデミー賞でも音響賞を何度も受賞しているんですよ。『プライベート・ライアン』(98年)の銃撃戦もすごかった。音の構成が複雑だし細かいし、あれで本当に戦場のなかに入っちゃったみたいな錯覚に陥るんです。映像もすごいんだけど、やっぱり音が立体的なんですよね。そして、スピルバーグ映画の音楽とジョン・ウィリアムズ。数えてみたんですけど、スピルバーグの50年以上のキャリアで、音楽がジョン・ウィリアムズじゃなかった作品はたった5本しかないんです。だから基本的にジョン・ウィリアムズありきなんですよ。やっぱりジョン・ウィリアムズと出会わなかったらスピルバーグ映画はちょっと違ってたと思います」
『ロッキー』(76年/日本公開77年)や『燃えよドラゴン』(73年)など、このテーマ曲でないとその作品は成立しなかった、と思わせるような名作はいくつもある。スピルバーグ作品にとっても同じく、たとえばウィリアムズによる『ジョーズ』や『インディ・ジョーンズ』のテーマ曲も、完全に作品の〝顔〞となっている絶対必要不可欠な要素である。では、これからはさらにマニアックに、スピルバーグの作品
に対するこだわりについて、掘り下げていただこう。
「いちばん有名なこだわりは、フィルムで撮るっていうこと。ジョージ・ルーカスは『スター・ウォーズ』シリーズの新作を撮る時に、いち早くデジタルを導入したけど、スピルバーグはそれに否定的だった。タランティーノやノーランもそうだけど、やっぱり古き良き映画を愛しているんです。そこにある面倒くささも含めて大事にしているんじゃないかな。そこになんとも言えない、言葉にできない、映画の在り方っていうものを、スピルバーグはその〝奇跡〞を信じているんじゃないかと思いますね。あとは子供の目線が多い。『子供から見たこの世の中って恐ろしいところだよ、グロテスクなものだよ』っていうのをデフォルメして、結構グロいシーンをぶっ込んできますよね。『レイダース』で、アークの威力で人の顔が溶けちゃうところとか、『ポルターガイスト』(82年)も顔がグチャグチャになってこわかったし、ビジュアルだけじゃなくて、『E.T.』では大人のこわい部分も結構描かれている。あと、『グーニーズ』に出てくるスロース(※6)なんて、顔が極端にいびつですよね。でもスロースって、見た目で気持ち悪いって思われるけど、〝でも関係ないんだよ〞っていう多様性がメッセージとしてあるんですよ。やっぱり子供から見ると〝別に見た目は関係ないよ〞っていうのがあって、むしろ今の時代が追いついてきたというか。そのあたりやっぱりスピルバーグは時代の先を行ってますね。当時からグロテスクな表現がわりと多くて、やっぱり僕らは子供だったから、すごく覚えてるじゃないですか。『うわっ』なんて言って。インパクトがあってやっぱりそこが嫌なんだけど、でも見ちゃうっていうのがスピルバーグの特徴なんですよね」
※6…『グーニーズ』の敵キャラ・フラッテリー一家の三男。巨体と怪力が特徴。
理想の女性像は〝中学1年生〞のもの
『E.T.』や『グーニーズ』、『魔宮の伝説』など、子供が主役やメインキャラクター(キー・ホイ・クァンは2作品に出演)で登場する作品が多いのも特徴のひとつ。やはりスピルバーグは〝永遠の少年〞と言うか、子供の心をもった大人ということなのだろうか?
「いやもうね、中学1年生ぐらいだと思いますよ。女性の描き方が中1じゃない(笑)。中1が大体いいなと思う女の子ですよね。ちょっと男勝りなんだけど弱い部分もあるキャラクター。思春期の男子が理想とする、『こんなお姉さんがいたらいいな』っていう女性像。だからルーカスもそうだけど、童貞感がすごいでしょ(笑)。基本的には男目線だし、女の人がそこまで魅力的じゃないというか…まぁ、魅力的じゃないっていうのはちょっと言いすぎだけど、キャラの奥は深くないかなっていうところがね。ちょっとスピルバーグの弱点じゃないけど、まぁ作品にはまってるからそれでいいと思うんですけどね」
スピルバーグ作品にそこはかと漂う、いい意味での〝童貞臭〞。これが、少年時代の昭和50年男たちの心をつかんだ大きな要因になったのかもしれない。加えて佐々木は、〝少年っぽさ〞をキーワードに、日本が世界に誇るクリエイターである、手塚治虫と宮崎駿の世界観も、スピルバーグに相通じる部分があると指摘する。
「この巨匠たちは、おそらく思春期に理想としていた女性像を追って、描いている気がします。あと、三者ともディズニーから多大な影響を受けている。特に手塚さんなんて、〝ヒューマニズムの人〞って勝手に思われてますけど、殺人シーンが多く、描写も残酷なんですよ。手塚さんもスピルバーグも、殺すシーンをリアルに描くというか、スピルバーグはクローズアップするし、『殺すシーンに興味があるんだな』と。普通の単なるヒューマニズムの人じゃないっていうのは、僕は子供ながらに感じていました。『スピルバーグはいい人』ってみんな言うけど…まぁいい人だとは思うんだけど、道徳的にいい悪いではなく、それを問うている気がします」
〝ユダヤ人差別〞と〝家族問題〞へのこだわり
また、スピルバーグのこだわりと言えば、先ほども話題が出た〝ユダヤ人〞という出自と差別の問題がある。
「これは大きいですね。設定が第二次大戦時のものがすごく多いし、ナチス・ドイツもよく出てくる。あとは差別されている人物もよく出てきますね。差別されているとか、言語が通じない者同士のコミュニケーション。『E.T.』なんてまさにそうですよね。『カラーパープル』もそういう設定が出てくるし、『ターミナル』(2004年)も該当しますね。だからコミュニケーションについて悩んでいる人たちの話は、テーマ的にしょっちゅう出てくる。それはやっぱり自分が子供の頃にいじめられたりして、コミュニケーションが上手くいかなかったからっていうのがあったのかもしれない」
それに付随して、難民が登場する作品も多い。『宇宙戦争』(05年)などは、主人公たちが宇宙人の侵略によって難民になってしまう話だ。どこにも属することができず、本来自分たちの居場所ではないところに来てしまった人たちを描くのも、スピルバーグの特徴と言える。そのテーマは、家族の問題にも及ぶ。
「スピルバーグの映画に絶対出てくる設定なんですけど、『一度バラバラになった家族が再び出会う』っていう映画がもう、ほとんど全部そうです。ちょっとしたシーンもあるけど、『宇宙戦争』なんてまさにそうじゃないですか。『インディ・ジョーンズ』だって結局お父さんとの関係の話で、一回離れて一回戻るという構成だし。『E.T.』や『ジュラシック・パーク』も、製作総指揮で関わった『BTTF』や『グーニーズ』も全部、家族に再会するっていう話です。全部家族問題。両親が離婚した自分の思春期を想定してなのか、無意識にそうなっていたんでしょうね。スピルバーグ自身が8本目くらいで気づいたらしいですから。『こういう設定が多いなぁ』って(笑)。その家族離散設定のなかでも、『宇宙戦争』がすばらしいのは、トム・クルーズ扮する主人公が自分たちの子供を、自分は家族になれないのに、離婚した奥さんの新しい家族に送り届けるっていうハッピーエンドなのかアンハッピーエンドなのかわからない終わり方だったんですよね。なんか今度はこういう変化球できたなと」
次に佐々木が指摘するのは、スピルバーグの〝飛行機好き〞な点。『インディ・ジョーンズ』シリーズには飛行機アクションがあるし、89年(日本公開90年)の『オールウェイズ』は飛行機乗りが主人公。そして『ターミナル』は空港が舞台の話だ。
「飛行機大好きっていう、そこも宮崎監督に似てるんですよね。戦争に否定的なんだけど、戦闘機には愛情をもっているように見える。その矛盾しているところがやっぱり作家だと思うんですけど。まぁお二人とも国民的な監督じゃないですか。そういう点ですごく共通してますよね。その辺に一貫したテーマがある。戦争の悲惨さを描きながら、度を越した戦闘シーンへの気合いの入れ方とか。『プライベート・ライアン』のオープニングはそれまでの戦争映画のレベルを変えました。あんなにすさまじい戦場シーン他にないじゃないですか」
マイベストワン作品は『宇宙戦争』
ここまでいろいろとスピルバーグ作品を分析してきてもらったが、いよいよここで佐々木の、監督作品ベストワンを教えていただこう。(ちなみに、生涯のベストワンは『バック・トゥ・ザ・フューチャー』だそうである)
「酷な質問ですね(笑)。本当に難しい。でもやっぱり、『宇宙戦争』かな。これがスピルバーグの集大成だと思ってます。一般的に駄作だと思っている人って多いと思うんですけど、それってスピルバーグのことを〝映画作家〞として見てないからだと思うんですよ。ずっと大成功をスピルバーグだからこそ、こういう実験的なことができたんじゃないかって。要は、カタルシスを作ることなんて、簡単にできる人じゃないですか。いくらでもやってきてるわけだから。なのにこの『宇宙戦争』では、カタルシスになりそうな伏線をたくさん仕掛けておいて、全部スルーしてくるんですよね、実に上手いことに。それは、だからこっちの期待を敢えて外しているっていうのもあると思うんですけど、スピルバーグはこの作品で、本当の戦争というものを描きたかったんだと思います。要するに、本当の戦争にカタルシスはない、というのを描きたかったんだと。この映画でよく批判されるのが、『なぜトム・クルーズ扮する主人公の一家だけがあれだけ運よく助かるのか?』という部分なんですけど、その指摘が間違いで、そもそも、たまたま運よく助かった家族にフィーチャーしている映画なんですよ。
普通の家族を、トム・クルーズっていう希代のスターが演じる。トムはトップ中のトップなんだけど、笑顔の裏に強いコンプレックスが見え、いい意味で変態性も感じる。実際いい人だとは思うんだけど、なんか一緒に生活したいと思わないでしょ? だからキラキラしているだけじゃないんですよね、トム・クルーズって。そのトム・クルーズの本当に内面にある暗い部分みたいなのをこの『宇宙戦争』で上手くすくい上げて、正面から負け組を描いている。奥さんにも離婚されて、子供を取られて、工事現場の労働者で、クレーンの使い方だけ上手いっていう設定の男ですよ。冒頭にクレーンをすごく上手く使うから、『絶対これ後で出てくるな』と思ったけど全く出てこない(笑)。すごいフリなのに伏線を全く回収しないんですよ。
それであのラストも、結局『いつ終わったの?』って感じ。なんか急に宇宙人の弱点が解明されて、『あれ?』みたいな。『なんだったの?』っていう終わり方だったんだけど、それも一般市民から見た戦争って多分そういう終わり方なんですよ。『これいつ始まっていつ終わったの?』といった感じで。そういうのを多分やりたかったのだと思う。僕は観ていて本当にこわかったし、トム・クルーズも本当にいい演技だったと思うし、スピルバーグが今までのことを全部フリにしてこれをやったっていうのも含めて、本当に作家性を感じるし、でもちゃんと娯楽作品にもなっているし、一級の作品だなと。SFなんだけど戦争のリアリティが感じられる。スピルバーグは今までも戦争に対してたくさん描いているじゃないですか。『プライベート・ライアン』で最高の第二次世界大戦映画を作ったけど、まだ何か戦争っていうものに対して描きたいところがあったのかなと思いましたね」
スピルバーグ映画はキャラクターが命
そしてベストワン作品に続いて、スピルバーグ作品のベストキャラクターについてもうかがってみよう。
「これも難しいなぁ。でももう、インディ・ジョーンズでしょやっぱり。インディこそが、スピルバーグが理想としている…まぁもともとはルーカスの発案だったとはいえ、スピルバーグが『〝007〞をやりたい』って言ってそこから始まって、ジョン・フォードの映画の主人公にも見えるし、だけどインディって完璧な人間じゃないから。親との関係に悩んでいたり、女性に対して不器用だったり、そんな人間味があふれていて…。だからみんな、5作目まで40何年続いても観に行くわけじゃないですか。もちろんハリソン・フォードの魅力もあってのインディだと思うんですけどね。スピルバーグの理想が全部入っている。やっぱり人間くさいところがいいですよね…痛がるし。あとは本当にベタになっちゃうけど『E.T.』かな。個人的には『宇宙戦争』でトム・クルーズが演じたレイっていうキャラクターも、普通の一般市民代表っていうことで描いたのは光ってますね。トム・クルーズもよかったし、いいキャラクターだったなって思います。歴史に残るキャラクターじゃないけどね。『レイのフィギュア欲しいか』と言われたら、そこまで欲しくないでしょう(笑)」
最後に、スピルバーグの俳優に対してのこだわりについて訊いてみた。
「有名な話なんですけど、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のマーティの役って、マイケル・J・フォックスじゃなかったんですよね。エリック・ストルツ(※7)という役者で3分の2まで撮ったけどやっぱりちょっと、何かが違うと。実はスピルバーグの映画って一見気づかないけど暗い話が多くて、『BTTF』もそうなんですよ。エリックはすごく演技も上手いしイケメンだったんだけど、どうしてもシリアスになっちゃう。『BTTF』ってイカれた科学者がプルトニウム盗んでリビアの過激派に撃ち殺されるっていうひどいシーンから始まって、その後タイムスリップして、自分の実の母親に性的な目で見られるという悪夢みたいな話で(笑)。それがマイケルという、希代の天才コメディ俳優の魅力によって、あんなに楽しい映画になった。だからキャスティングが上手いっていうのもスピルバーグの特徴のひとつなんですよ」
※7…1961年生まれ。『キリング・ゾーイ』『パルプ・フィクション』など、通好みの作品で活躍。
(出典/「昭和50年男 2023年9月号 Vol.024」)
取材・文:山本俊輔 撮影:小林岳夫
関連する記事
-
- 2025.07.04
「The REAL McCOY’S CEO」辻本仁史さんの、一生手放せないヴィンテージ。
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)