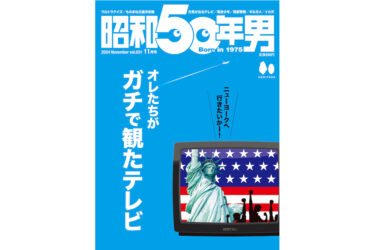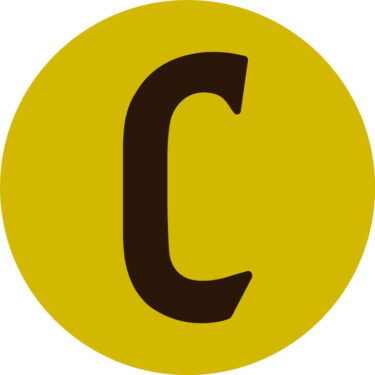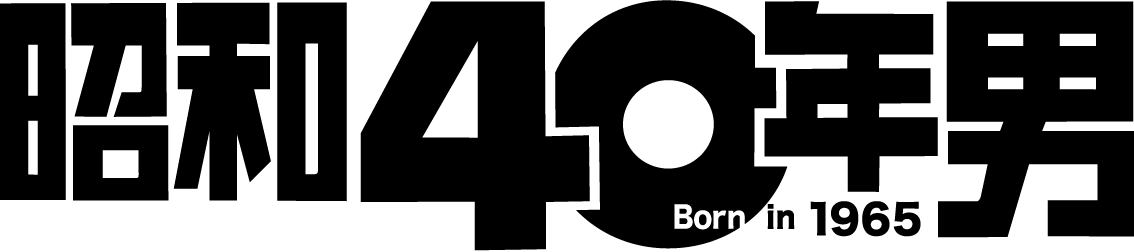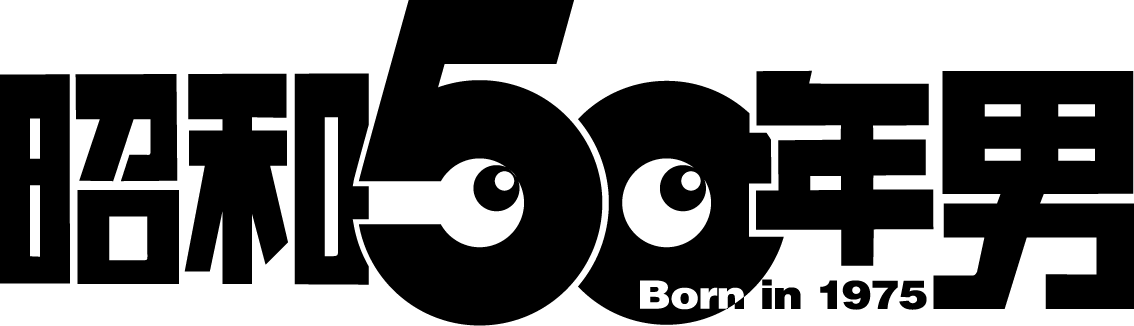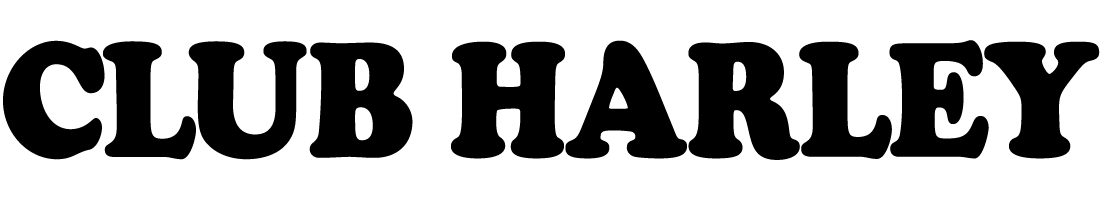とにかく驚いたスタローン役のオファー

シルヴェスター・スタローン、ディーン・マーティンなどの吹き替えでお馴染みの声優・羽佐間道夫は今年で90歳(!)になる声優界のリビングレジェンドだ。過去の吹替の思い出、声優仲間との交流、現在の取り組み、そして未来への展望について、たっぷり語ってもらった。羽佐間が吹き替えた作品の数は、一説によると7千本を超えると言われている。果たして本当なのだろうか?
「『嘘だろ!』と言われることもあるんですけど、僕がこの世界に入ってから60数年、だいたい毎週3回ぐらいずつ吹き替えをやっています。すると1ヶ月で12本、1年で144本。10年で1440本。60年で7千本を超える計算なんです(笑)。正確にカウントしたわけではないので、ご勘弁ください」
アフレコは一日に2本、3本と掛け持ちすることもあった。
「忙しかった!メシを食う暇もないぐらいですよ。何しろ人がいなかったからね。あと、(ギャラが)安かったんだよ。声優で金持ちになった人が一人もいない(笑)。ハリウッドだったら7千本も出演していたら大変だよ? 国とか買っちゃってるよ」
羽佐間が吹替の仕事を始めたのは、1950年代の終わり頃。コンテンツ不足だったテレビでは洋画や外国テレビドラマが数多く放送されるようになっていた。その頃は本番一発録り。ミスをしたら最初からアフレコのやり直しだった。
「(少し咳き込んで)これ、昔だったら大変だよ。(テープ1本分の) 28分ぶっ通しで収録するんだから、途中で咳をしたら全部最初からやり直し。最初の『ロッキー』はそうだったね。みんな、すごく緊張していましたよ」
若かりし頃は、劇団で俳優として腕を磨いていた。仲間たちはみんな貧しかった。
スタローンは絶対に俺の役じゃないと思っていた
「同じようなアルバイトをしている連中が集まってきて、わずかばかりのギャラで芝居をしていました。声優の仲間はだいたいみんな劇団で芝居をしていたんですよ。だから、アフレコの現場は『また親族が集まっちゃった』みたいな感じでしたね」
同じような苦労を重ねていた分、吹き替えの声優たちは仲がよかったという。そういえば、吹替はずっとアンサンブルを聴いているような気がしていた。
「ご指摘のとおりです。吹替の時、スタジオに入って何か違和感があるような作品はヒットしなかった。ちょっと異質な人が入ってくることがあったんです。スター気取りで『てめぇ、下手だなぁ』みたいなことを言うやつもいた。そういうのがいると、よくないんだよね」
吹き替えをしていて感動したことがあるという。ある日、親友の山田康雄から一通のはがきが送られてきた。
「『5つの銅貨』の放送があった翌日、山田康雄からはがきが届いたんです。『おまえ、テレビで泣かせるなヨ』って書いてあった。ここがよかった、あそこがよかった、とかじゃない。集大成の言葉をもらったような気がしたな」
吹替声優として多忙を極めていた羽佐間だったが、スタローン役のオファーがきた時は、とにかく驚いたという。軽妙洒脱な役柄を得意としており、マッチョなアクションスターを演じたことがなかったからだ。
「『なんで俺がスタローンを演るの?』と思ったよ。俺を選んだのはTBSの熊谷国雄というプロデューサーだけど、本当に驚いた。だって俺のなかに、あの『ウォー!』という野太い声とか、あのボリュームはなかったんだから。絶対に俺の役じゃないと思っていた。むしろ賢坊(内海賢二)がやった方がいいんじゃないかと思ってたんだから」
ロッキーのライバル、アポロ・クリード役のカール・ウェザースを吹き替えたのが内海賢二。二人の名コンビぶりが発揮された吹き替えは枚挙にいとまがない。
「賢坊はいちばんやりやすかったね。あと、ポーリー役の富田耕生がよかったな。富田が『(ロッキーは)絶対、羽佐間しかいない!』って言ったらしいんだよ。人から聞いた話だから、キャスティングの時の話なのか、後から言ったことなのかはわからないんだけどね。とにかく熊谷さんは無茶振りだった。そういう人は何人もいましたよ。『日曜洋画劇場』のプロデューサーだった圓井(一夫)さんもそう。『じゃ、羽佐間さんにしておきましょうか』という感じなんだから(笑)」
プロデューサーからの〝無茶振り〞は羽佐間の演技力の幅の広さ、適応力の高さの証明にほかならない。その後、羽佐間は『ロッキー』以外のスタローンのアクション作品も吹き替えを行っている。
「『ランボー』もやってますよ。乱暴なことだよねぇ(笑)」
広川太一郎とアドリブ合戦
ディーン・マーティンを演じたオールスター映画『キャノンボール』も忘れ難い。サミー・ディヴィスJr. を演じた内海賢二と見事なかけ合いを見せていた他、ロジャー・ムーアとマイケル・ホイの二役を演じた広川太一郎らと豪華な競演を聴かせてくれた。広川といえば多彩で突拍子もないアドリブが有名だが、羽佐間とアドリブ合戦になるようなこともあったという。
「広川と僕とでは、ちょっとアドリブが違うんですよ。あいつアドリブは意味がわからない(笑)。(モノマネで)『な〜んていっちゃってトンボのメガネのクソ』みたいな感じなんだよ。『トンボのメガネのクソ』ってなんだ?(笑)」
二人の交流は、広川が亡くなる直前まで続いた。最後に言葉を交わしたのは、広川が亡くなる二週間前だったという。『一緒にやった作品もいっぱいあったし、アドリブもいっぱいあったけど、意味がわからなかったな』と言ったら『わからないですか?全部デタラメですよ!』(笑)。そりゃそうだよな。でも、普段は本当に真面目な男でしたよ。とんでもないクソ真面目。だから、他人がアドリブをやると許せないんだよ(笑)」
アドリブといえば、バラエティ番組のナレーションでも活躍した滝口順平もすごかったという。
「滝口さんはアドリブを何日もかけて考えてくる。本番の日はスタジオの隅でじっとしてるんです。いきなり本番でアドリブを言うと、女の子たちが噴き出しちゃう。笑ったらやり直しだから、みんな必死に我慢する。それが滝口さんの楽しみだったんですよ」
アドリブは羽佐間も負けてはいない。意表を突いたアドリブや絶妙な間などは、若い頃にアルバイトしていた寄席で学んだ。
「劇団にいた頃、夜は神田須田町にあった立花亭のテケツでアルバイトしていました。テケツってのはチケット売り場のこと。板から手だけ出る穴だからテケツね。圓生がいて、志ん生がいて、文楽がいて、柳橋がいて、可楽もいた。いちばん仲がよかったのは三平でした。寄席では意表を突くことのおもしろさを学びましたし、芸人特有の間は自然に身につきました。ただ、アフレコでは間が決まっているから、人が画面から消えた時や背を向けた時に何か言う(笑)。ディーン・マーティンの映画で、ベッドシーンで起き上がって振り返った時、『この次はパンツ赤くしといて』ってアドリブをちょっと入れたんです(笑)。ドラマには何の関係もないんだけど、エロチックじゃないものが漂うんですよ。また、そんなことを言いそうなトボけた顔をしているんですよね、ディーン・マーティンって」
アドリブをやりすぎて怒られることもあったとか。
「僕はその場で感じたことを言ってるだけ。それを(翻訳の)作家が怒るんだよ。『僕は寝ずにこのセリフを考えてるのに、どうして一瞬で壊すんですか?』って」
破天荒な刑事ドラマ『俺がハマーだ!』は全編にわたって羽佐間のアドリブが炸裂する名作だ。もしかしたら全部アドリブなんじゃないかと思ってしまうほどだった。
「オープニングで『動くなよ、弾が外れるから。俺は羽佐間ァーだ!』って言ったら演出担当が怒っちゃった(笑)。『〝ザ〞はいらないんです』って」
ここでも相手役を演じていたのは内海賢二だった。
「賢坊はあまりアドリブが上手くなかったね。本当に真面目な人だった。彼は抑揚と大きな声で脅かしていたんです(笑)…あぁ、もうみんな死んじゃったな。二度と聴けないんだなぁ」
山寺宏一は弟子じゃなくて〝師匠〞
羽佐間は洋画の吹き替えが中心だったが、アニメでは『超時空要塞マクロス』(82年)のブルーノ艦長や、OVA『銀河英雄伝説』(89年〜)のシェーンコップなどを演じている。
「アニメの現場では、後輩の富山 敬とか小原乃梨子にいろいろなことを教えてもらいました。『ここで前に出るんですよ』と肩を叩かれて、ヨロヨロとマイクの前に出ていったりしてね。『銀河英雄伝説』は富山とずっと一緒でしたし、『マクロス』は小原乃梨子と一緒でした。ずいぶん背中に指紋がついたよ(笑)」
下の世代の声優たちとも積極的に共演と交流を続けてきた。声優界のトップランナー、山寺宏一はデビュー以前から指導している間柄だ。現在も海外ドラマ『マーダーズ・イン・ビルディング』で、山寺、林原めぐみと共演している。いろいろな刺激を受けているのではないだろうか。
「刺激どころか、山寺は私の師ですよ。タイミングの取り方なんて本当にすばらしい。林原めぐみは人間がいいね。あの人は元看護師さんだから、人の身体と心をやさしく治していくような部分が本質的にあるんだと思う」
90歳を目前にしていまだ現役。これから吹き替えしたい俳優を聞いてみたところ、すぐさま返事が返ってきた。
「クリストフ・ヴァルツ。タランティーノが使っている俳優でね、ドイツの将校がすごく上手いんだよ。余計なことをしてるわけじゃないのに何か出てくるものがある。あれは舞台で培って生まれてきたものでしょう。最近亡くなったアラン・アーキンも演じてみたいね」最近、気に入った役柄もあった。長いキャリアのなかでも滅多にないことなのだという。
「満足してしまったら終わりだからね。でも、『シェイクスピアの庭』のイアン・マッケランはよかった。主人公のシェイクスピアを心から愛している年老いた貴族という役です。これは生涯で演じた役のなかでも特に気に入っています」
羽佐間が今、力を入れているのが06年から続けている「声優口演」だ。チャップリンなどの無声映画を声優たちが活動弁士となってライブで吹き替えるというもので、羽佐間自身が企画、脚本、演出を担当する。ベテランから若手まで、数多くの声優が出演してきた。
「私は今年の秋、90歳を迎えます。今いちばん考えているのは、世代間の文化の違いを我々声優がどう克服するかということ。『声優口演』をやると、おじいちゃんの手を引いてやってくる若い人がいます。おじいちゃんは無声映画を観て『若い時に観た!』と言ってくれる。おじいちゃん、おばあちゃんと若い孫が一緒に来てくれて、手をつないで家に帰る時に『おもしろかったね』と言い合っている。そういう芸術、舞台はなかなかないんじゃないかな」
「声優口演」で上演されるのは、羽佐間が若い頃に見聞きした無声映画の数々だが、それを演じるのは、現在の人気声優たちであり、言葉も今のものになっている。自分たちの世代が受け継いできた文化を、世代を超えて伝えたいと熱く語る羽佐間は、それを若い人たちに「わからせようとしてはいけない」、むしろ「若い人にこそ学ばなければいけない」と言う。
「探究心を常にもたなければいけないと思っています。若い人に『なんだ、そんなこともできないのか』と言うのではなく、『できないなら一緒に考えよう!僕も一緒にやってみよう!』というコーチが人を育むんじゃないでしょうか」
90歳を間近にして、今も声を使って新しいチャレンジを続けている。
「近所の子供たちに紙芝居を聞かせているんです。30人ぐらい相手に『雪女』とか『屁っぴり嫁』とかをやっています。ボランティアですよ。『つまんねぇ!』と言われることもありますが(笑)。すごくおもしろい反応をもらえるのがいいですね」
(出典/「昭和50年男 2023年9月号 Vol.024」)
取材・文:大山くまお 撮影:吉場正和
関連する記事
-
- 2024.11.29
松浦祐也の埋蔵金への道。第10回 夏季最上川遠征・没頭捜索編 その2。
-
- 2024.11.22
渋谷発 革ジャン青春物語。「あの頃の憧れはいつもVANSONだった。」
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)