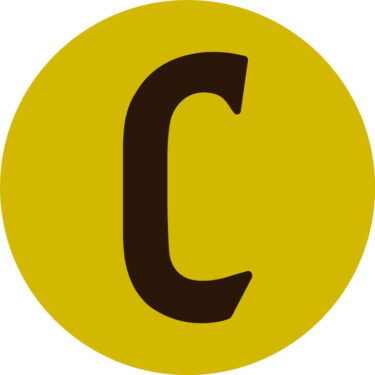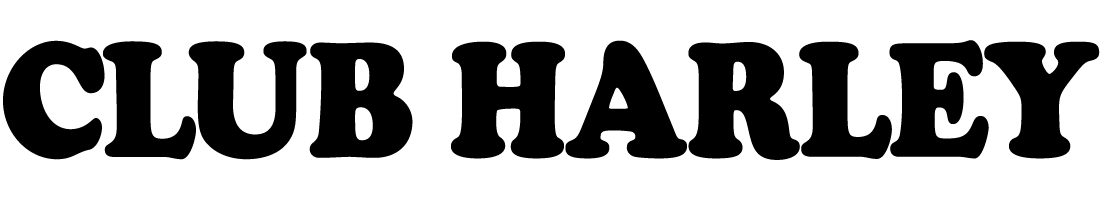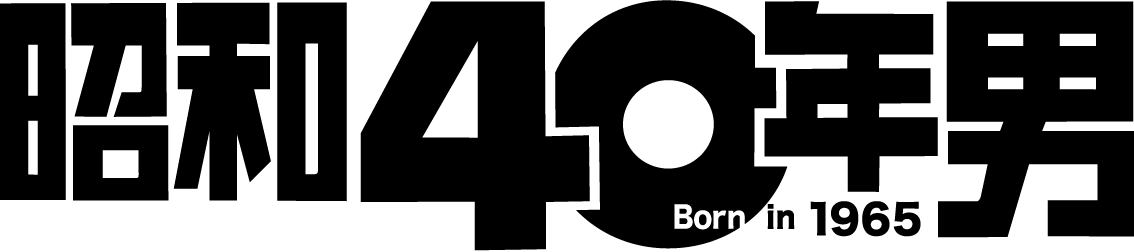スタイルある着こなしに学びたい7人のアメリカンヒーロー
1.カート・コバーン|ステージでも自然体。ナードな着こなしでパンクに殉じた男。
若干27歳で人生を燃やし尽くした夭折のヒーローが相当古着好きだったことは残された数々の写真を見ればわかる。モヘアのカーディガンにリーバイス501、そして足元はコンバース・オールスター。パジャマを普段着に着るなどエキセントリックな面もあったにせよ、’80年代に主流だった革ジャンや煌びやかな衣装をまとったロックバンドとはまったく異なる、ステージでも徹底して自然体だった着こなしこそがカート流だった。あえてナードな着こなしをしながら、それでいて思想はパンクに思いっきり殉じていたところがまた強烈に惹かれるのだ。
2.スティーブ・マックイーン|ボロボロに汚れ破れたバブアーをまとった姿こそ美しい。
数々の映画の劇中で魅せてくれた佇まいやファッションはもちろん素敵だが、アクティブな私生活もまた憧れの対象でもあったスティーブ・マックイーン。全米各地で開催されるオートバイレースのドキュメンタリー映画『栄光のライダー』にも登場するほど生粋のスピード狂として知られた男が、ライダースジャケットとして愛用していたのが英国王室御用達のバブアーインターナショナルだった。1964年にアメリカ代表としてISDEに出場した際にも共にした愛用品。ボロボロに汚れ、擦り切れた一張羅をまとうマックイーンこそがきっとありのままの姿なのだろう。
3.リバー・フェニックス|’90年代のアイコンは着崩したアメカジの達人だった。
リバー・フェニックスと聞いてすぐに『スタンド・バイ・ミー』を思い出すのは本誌読者の中でも比較的高年齢の方々。もうひとつの名作映画『マイ・プライベート・アイダホ』でオレンジ色にハンティジャケットやムートンジャケットにワークシャツをレイヤードしたワークスタイルの着こなしこそ’90年代のアメリカンヒーローに相応しい。私服だと思われる写真の数々を見てもアメカジをベースとしたデニムスタイルが多く、その着崩し感が絶妙で、非常にカッコよい。’90年代を代表するアメリカンヒーローが年を経たとき、一体どんな着こなしになったのか見てみたかった。
4.アーネスト・ヘミングウェイ|キューバとオープンカラーシャツ。文豪が辿り着いたシンプルで快適なもの。
20世紀を代表する文豪アーネスト・ヘミングウェイは、文学だけでなくその奔放なライフスタイルも多くの影響を与えた。アメリカに生まれ世界中を旅した後、晩年に定住したのがキューバ。その気風をこよなく愛し、結局22年もの間過ごした。首を締め付ける服が嫌いだったヘミングウェイはキューバの日々のほとんどを開放的なオープンカラーシャツで過ごしたという。若い頃から数々の愛用品にこだわってきた文豪が最終的に辿り着いたのは、シンプルかつ快適で、そして毎日着ても飽きないものだったのだろう。
5.アンディ・ウォーホル|ファッションはベーシック。それも計算された自己プロデュース!?
アメリカを代表するポップアートの旗手として名を馳せた現代美術家アンディ・ウォーホルは自身のプロデュース能力にも長けていた。バスキアやキース・へリングなど同時代のアーティストと異なり、ウォーホルの着こなしは常にシンプルかつベーシック。タイドアップするときはネイビーのジャケットに身を包み、カジュアルではセントジェームスのボーダー、レザージャケットやジージャン、足元はチェルシーブーツ。タイムレスな着こなしだからこそ、一層ウォーホルのキャラクターが一層際立ったともいえる。これこそ自己プロデュースの極意なのか。
6.エルヴィス・プレスリー|デニムを着用せずにナッソージャケットを好んだ理由。
映画の中ではリーバイス501XXや507XXも衣装として着こなしたエルヴィスだが、私生活でデニムを身に着けることはほとんどなかったという。ミシシッピ州の田舎町で生まれたエルヴィスはワークウエアにはほとんど興味を示さなかった。最も愛用したのはカピストラーノのストライプ柄ナッソージャケット。そして胸元にはいつもクリスチャンらしくセントクリストファーのネックレス。ハーレーに乗る際も足元はエンジニアブーツではなくクロスストラップシューズを選んだほどだから、徹底して野暮ったいものを避けていたのかもしれない。
7.エド・ロス|ラットフィンクの生みの親はワークウエアも正装もカッコ良かった。
イラストレータでありカスタムビルダーのエド“ビッグダディ” ロス。戦後、クルマにピンストライプを描き始めただけでは飽き足らず廃車置き場のスクラップパーツで自分だけの1台を組み上げてしまったクルマ好き。’61年に生み出したラットフィンクはミッキーマウスの父という設定だが、本人の投影のようにも思える。子供心を失わずホットロッドを愛した男は、ガレージでは着飾らない白Tかオープンカラーシャツ。ショップコートやジャケット姿で雑誌に登場することも多かったのはアメリカではカスタムビルダーの社会的地位が高かったから。
(出典/「Lightning2022年5月号 Vol.337」)
Text/K.Yoneda 米田圭一郎 Photo/S.Seiji 澤田聖司 Illustration/K.Mori 森海里
関連する記事
-
- 2025.05.30
本場で飲む格別の味! 「ジャックダニエル」の生まれた地、テネシーを行く。
-
- 2025.05.13
古着好きのなかで密かな話題に! アウトドアカルチャーの保管庫「ORA」へ本邦初潜入!
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)