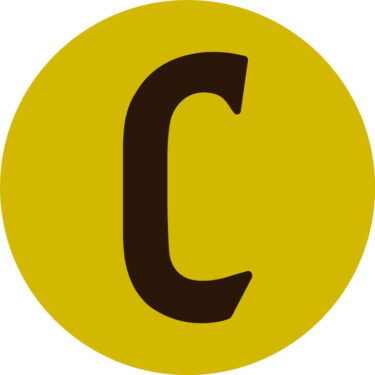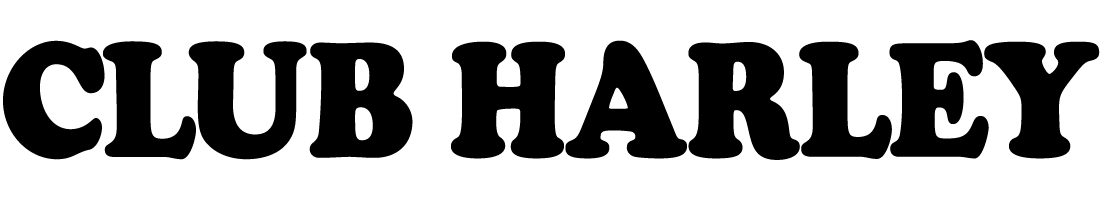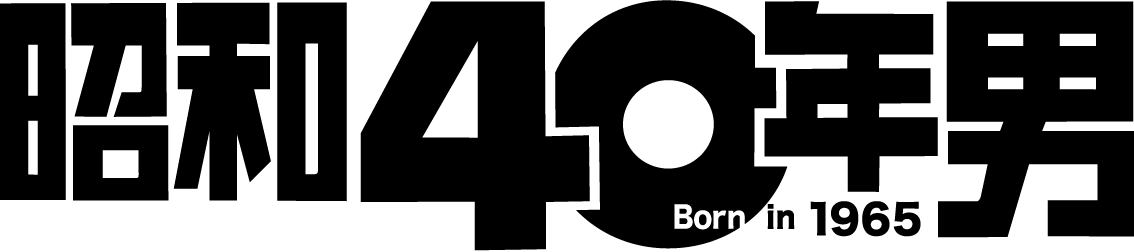ユースカルチャーの中心だった渋谷
渋谷直角は東京生まれ。
「…といっても練馬の生まれなんです。僕が生まれた頃はまだ畑があるような場所でした。だから、都内の中心部の人たちから比べたら、田舎出身というマインドですよね」

昭和50年男が思春期を迎える1980年代後半以降、東京・渋谷はユースカルチャーの中心だった。ファッションを例に挙げれば、DCブランドブームのカウンターとして現れた“渋カジ”が、日本初めてのストリートファッションだと言われている。アメカジの流れから派生して、雑誌『POPEYE』(76年) や『ホットドッグ・プレス』(79年)などで紹介されると、90年代にはキレカジやスケーター、モッズなど個々のライフスタイルによって細分化されていき、その後のさまざまなムーブメントの根幹となっていった。
そして、そんな渋谷の文化の多面性を支えていたのが、パルコだった。ファッションだけではなく、ライブハウスのCLUB QUATTRO、演劇・映画興行を行うSPACE PART3など、そこに行けば何かしらのカルチャーに触れることができた。
「西武線沿いの中学生が渋谷のパルコへ行くのは、ハードルが高いわけです。なので(西武沿線からバスで出られる)吉祥寺のパルコで慣れてから、渋谷へ行こう、と。中学時代に引っ越した埼玉の新所沢にもパルコはあったんですが(笑)。友達と渋谷へ行くようになってからは、東急文化会館の屋上でやっているフリーマーケットをあさって、レコード屋へ行ったり、センター街に行ったり、本場のパルコへ行ったり(笑)」
そしてパルコを語るには重要な施設、パルコブックセンターがあった。ファッション、映画、文学、アート、音楽、マンガ…ありとあらゆるカルチャーの入口となる書店だった。
「最初に新所沢のパルコで『i-D JAPAN』(※1)の創刊号(91年10月号)がうず高く積まれていたのを見たんですね。『STUDIO VOICE』(76年)とか、自主制作の雑誌『composite』(92年) と並んで、明らかに“これを手にするやつは大人だぞ”という雰囲気でした。他のクラスメイトに差をつけないと、と『i-D JAPAN』を手に取って。あと忘れてはいけないのが、『GOMES』(89年)というパルコのフリーペーパーです」
このフリーペーパーは、天久聖一とタナカカツキの『バカドリル』の連載をはじめ、岡崎京子、しりあがり寿など、豪華なメンバーが執筆していた。90年代は、上質なカルチャー誌が無料で手に入る贅沢な時代だったのだ。
元ネタにもセンスが必要“渋谷系”の謎
マンガ家志望だった直角は94年からアート系の専門学校へ進み、積極的にフリーペーパーを作るようになる。
「インターネットがなかったですから、何かを発信したかったらフリーペーパーを作るしかなかったんです。手書きの原稿を 切り貼りしてコピーを使って。この頃になると、フリーペーパーはたくさんあって、レコード屋さんをはじめ渋谷のお店だと、 お願いすれば店頭にフリーペーパーを置いてくれるお店が多かったんですよ」
直角のフリーペーパーを置いてくれたレコード屋…そう、90年代の渋谷は音楽の流行発信地でもあった。
「僕の感覚では当時、電気グルーヴとスチャダラパーとフリッパーズ・ギターって、今までの日本の音楽シーンとは違う押し 出し方をしていたと思うんです。メディアの取り上げ方も」
日本の音楽シーンは、80年代後半からの(第二次)バンドブームによって、多様なジャンルの音楽が流通されるようになっていた。渋谷では、90年にHMVが日本に初出店、93年にはCLUB QUATTROにWAVEが登場したのをはじめ、中古レコード屋も宇田川町だけで200軒超、またさまざまなライブハウス、クラブも登場。これらの文化を評価する雑誌やZINEも多く現れた。
こうした背景から、特に渋谷で流行した音楽を、マスコミは“渋谷系”と呼称するようになる。分類されるアーティストには、 ピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラブ、そしてフリッパーズ・ギターのメンバーだったコーネリアス(小山田圭吾)、小沢健 二などが挙げられる。
「渋谷系という名前がついた時には、もうフリッパーズ・ギターは解散した後で、カテゴライズされているアーティストたちにも、それぞれにファンがいて、音楽性も全く一緒なわけではない。渋谷のレコード店が応援していた人たちというだけで、具 体的にこういうものだ、ということは言えない人たちですよね」
この呼称には、当初は「渋谷で売れていて、よくわからないけど、カッコイイですね」と揶揄する意味合いで使う人もいたようだ。
ただ、ひとつだけ特徴を挙げるとしたら、レコードの街・渋谷の名にふさわしく、洋楽の名曲をそれとわかるようにオマージュを捧げる曲作りがあったことだ。その元ネタを取り入れるセンスとテクニックが必要な、ハイブロウな音楽と言えた。
「そうした元ネタ探しの文化も普通に受け入れてましたね。ヒップホップのサンプリングは新しいものだという認識が、雑誌 やテレビを通してすでにすり込まれていましたから、そのまま借りてくることで新しいモノを創るなんてカッコイイ、と思っていました」
渋谷系と呼ばれていたアーティストたちはこの頃のミリオンセラーのメジャーアーティストと比べると売れ行きこそ劣っていたとはいえ、音楽を愛する人たちから熱狂的な支持を得ていたことは確かだ。
ファッション誌にリアルなマンガがあった
また、直角はこの青年期に衝撃を受けたマンガ誌があったという。
「マンガ家になるのは無理かなぁ、なんて思っていた高校生から専門学校の頃、『COMIC アレ!』(93年)と『COMIC CUE』(94年)が出たんですよ」
前者は江口寿史が表紙で魚喃(なななん)キリコ、一條裕子などの新しい作家が登場。後者は江口寿史が責任編集長を務めたワンテーマ・マガジンであった。
「江口先生もそうですけど、この時期の魚喃キリコ先生、岡崎京子先生や井上三太先生などは、これまで抱いていたマンガ家のイメージを打ち壊してくれましたよね。もう、カルチャーなんだと」
さらに岡崎京子は『CUTiE』(89年)、井上三太は『Boon』(86年)と、マンガ誌以外のファッション誌にも連載していた。 「岡崎先生の作品でも、音楽とかクラブとかレコードの話が出てきて…とにかく、マンガに出てくる人たちの描き方がすごくリアルで、衝撃を受けました。こういうことを描いていいんだ、という気になりましたね」
ところで、『CUTiE』は女性ファッション誌だが…。
「あの頃、女性ファッション誌はおしゃれを目指す男性も読んでいたんですよ。『CUTiE』は 当時の女性誌としては珍しいス トリートファッションの雑誌だったんです。そのフレンドの男の子もストリートスナップで載っていましたし、藤原ヒロシさんや、電気グルーヴも連載をしていましたし…」
実はこの『CUTiE』、カルチャー誌だった同社の雑誌『宝島』のエッセンスが含まれていた。ちなみに、『i-D JAPAN』の元であるイギリス版『i-D』の影響があったというのも、奇妙な縁と言うべきだろうか。
もう海外に憧れなくていい時代
「基本的におしゃれなものが好きっていうのがベースにあるんですけど、おしゃれというのは極端に言うと、海外のカルチャーに影響を受けている人の作品のこと」と直角は言う。力まず、自然に生きるアーティストに憧れる若き編集者コーロキが、男を狂わせる女性と恋に落ちたことから始まる物語『奥田民生になりたいボーイ 出会う男すべて狂わせるガール』(扶桑社)で題材にした奥田民生もそうである。
「コーロキ同様、民生さんは好きでしたね。僕がその頃憧れた人はダウンタウンとか電気グルーヴとか、ちょっと攻撃的なタイプが多かったんですけど、民生さんはそんななかで飄々としていて、すごく魅力的に映ったんですよ」
奥田民生の泰然とした感じは、年を追うごとに顕著になっていった。解散直前(現在は再結成)、ユニコーンで奥田民生が発表した「あやかりたい」という曲がある。Gパンとエレキを手に入れて、ガイジンになりたかった…という、後にビートルズの影響を隠さなくなった奥田民生の、海外への憧れを率直に現した曲だ。そして、我々昭和50年男も奥田民生と同様に、文化と言えば海外に敵わない、と考えて青年期を生きてきた。
「ただ、僕のなかで、90年代中盤に『ドラゴンボール』がフランスで大ヒットしたと聞いた時に、変化を感じたんですよ。同じ時期に、ビースティ・ボーイズが裏原宿の服を着るとか、ヒステリック・グラマーがソニック・ユースのTシャツを作るとか、それまで欧米が上だと思っていた文化の逆転現象が起きたんですよね。海外で、日本の文化に素直なリスペクトが怒っている、という感覚が実感できた気がするんです」
ファッションの世界では、日本におけるヒップホップの先駆者・藤原ヒロシが、NIGO、高橋 盾などと共に“裏原宿系”として雑誌のグラビアを飾っていた。いわゆる“裏原宿系”という言葉が盛んに雑誌を賑やかすようになる97年、直角は『relax』(96年創刊)のライターとしてデビューする。
「僕が担当していたのはおしゃれでもなんでもない記事ですけどね(笑)。マンガも描けることがわかると、それも掲載してくれました。最初の原稿は『Olive』に載せた自社広告のマンガです。マンガ特集の号だったので、描いてみろ、ということに なったんだと思います」
その後00年から同誌にページのマンガ『RELAX BOY』を掲載、02年には連載をまとめた単行本を出版。05年からはマンガ家、コラムニスト、ライターとして、さまざまな媒体に活動の場を広げていく。渋谷直角と昭和50年男の青年期を通り過ぎた雑誌カルチャーは、彼の作品のなかに今も生き続けている。
※1…雑誌名の後の年は、創刊年。
[主な参考文献] 難波功士『族の系譜学 ユース・サブカルチャーズの戦後史』(青弓社)/川勝正幸『ポップ中毒者の手記(約10年分)』(河出文庫)/ 音楽ナタリー『渋谷系狂騒曲 街角から生まれたオルタナティヴ・カルチャー』(リットーミュージック)/増田海治郎『渋カジが、わたしを作った。 団塊ジュニア&渋谷発 ストリート・ファッションの歴史と変遷』(講談社)/別冊宝島1504『おしゃれ革命』(宝島社)- 1
- 2
関連する記事
-
- 2025.07.08
革ジャンの伝道師・モヒカン小川の私物大公開! 経年変化を楽しむ“茶芯”ってなんだ!?
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)