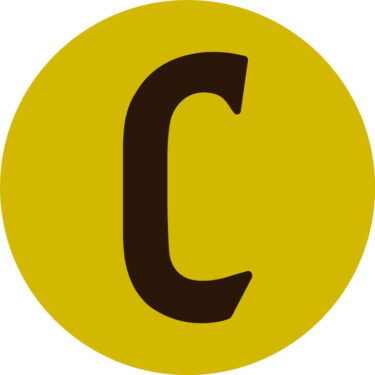自分のモノにしていく、これが革の楽しみ方だ。
1905年、アメリカ・イリノイ州シカゴで創業し、100年以上家族代々で経営してきたHorween社。革好きならきっとこのタンナーの名を一度は聞いたことがあるはずだ。Horween社オリジナルのクロムエクセルやシェルコードバンなど、上質な革を提供し続けてきた。その上質な革は、創業当初から変わらぬ技法で鞣されてきた。
4代目であり、現オーナーのスキップさんはこう語る。「伝統技法とは、時間をかけてじっくり作ること。マーケティングを意識せず、ひたすら良い革を提供することが我々の信念であり、この仕事にやりがいや生きがいを感じている。先祖代々、こう言っているよ、人生そのものだってね」
丁寧に鞣され、想いのこもったHorween社の革は、見て、触って、嗅いで、五感で感じるモノだと教えてくれる。

ファーストシェービングで大まかに削った後はセカンドシェービング。シェービングマシーンのペダルを足で微調整しながら、コードバン層を慎重に削り出していく。シェルコードバンとは馬の臀部ですべての馬にあるわけではなく、希少性が高い。

鞣された革は熟練のスタッフの見事な手捌きにより、カッティングされていく。Horween社のスタッフは数年、数十年とキャリアを積んだ職人が多く在籍している。自分が担当する工程でたしかな技術力を発揮し、つぎの工程へとバトンパスしていく。

最終工程の前に、植物性のオイルを90日間かけて、たっぷり染み込ませる。創業当初は、いまは使用できなくなったくじらのオイルなどを使用していたんだそう。ほぼ変わらぬレシピで作られたオイルにより、シェルコードバン特有のなめらかな表情へとエイジングしていくのだ。

「どこから削るか分かるかい? シェルコードバン層より下の層から削っていくんだ」。上から削るよりも、下から削ることで、コードバン層にはやく到達することができ、きれいな状態で削れるんだそう。


革の表面に光沢感を持たせるための作業、グレージング仕上げ。素早く動くガラスのローラーで革を擦っていく。単純作業に見えるが、この段階で革に傷がはいってしまった場合、すべてB品となる。一寸の狂いも許されない、重要な工程なのだ。

Owner/SKIP HORWEEN|2002年、Horween社4代目のオーナーとなる。大学へ進学し、青春時代を過ごした。ファミリービジネスでは珍しいとされる、外の世界を知る経験があったからこそ、改めて、家業の素晴らしさに気付くことができたんだそう。カスタマーに対するリスペクトの気持ちを大切にしている。
Horween社ならではの革を生み出す秘密はここにある。


一度に600枚の皮を入れられる大きなピット槽で植物性のタンニンを均等に漬け込んでいく。30日間漬け込む→シェービングする→30日間漬け込む→90日間乾燥させる、この工程だけで約3カ月間を要する。この手間暇こそが、まさに伝統技法なのだ。


革の鞣しや染色するうえで欠かせないタイコもしくはドラムと呼ばれる木製の樽。一定時間回し、革と薬品を混ぜ合わす役割を担っている。中を覗くと均等に配置された突起があり、これらが配置されていることで均等に混ぜ合わすことが可能になる。

スキップさんの祖父と父親はハーバード大学でフットボールチームに所属していた。フットボールと密接に関わっていた青春時代があり、祖父がフットボールレザーを開発。アメリカンフットボールの最高の大会と呼ばれるスーパーボウルの公式ボールに採用され、1950年代以降、100%Horween社製となる。

Horween社の始まりはシェービング用のヤスリをコードバンで作るところから始まる。創設者イシドール・ホーウィンは1893年、ウクライナからシカゴへ移民として渡ってから12年でHorween社を立ち上げ、アメリカンドリームと革好きの心を掴んだ。

スキップさんは従業員と深いコミニュケーションを取ることを大切にしている。工場内を回り、仕事に対してのアドバイスはもちろんのこと、プライベートのことも共有し、信頼関係を築きあげている。工場内の士気が高まることで、一貫した上質な革作りを実現している。

建物自体は1880年代から存在し、1920年代にこの建物へと移る。大通り沿いに面し、時代と共に変わっていった街並みの中で、旧きよき外観はいまも健在。建物近辺はタンナーストリートと呼ばれ、27社のタンナーが軒を連ねていたが、いまはHorween社のみが現存している。

【DATA】
HORWEEN LEATHER COMPANY
2015 North Elston Ave. Chicago, IL 60614
Tel. 773-772-2026
https://www.horween.com/
The Tannery Row Japan
Tel.03-6264-8494
https://www.songoriver.com
Photo by Tadashi Tawarayama 俵山忠
関連する記事
-
- 2026.02.07
日本の文具メーカー「ハイタイド」がニューヨークのグリニッジ・ビレッジに直営店をオープン
-
- 2026.01.28
初めてのアメリカで訪れた、“憧れの”ルート66【H-D偏愛主義】
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)