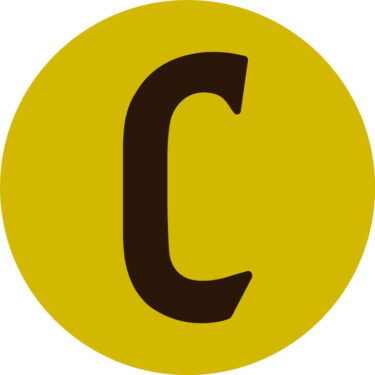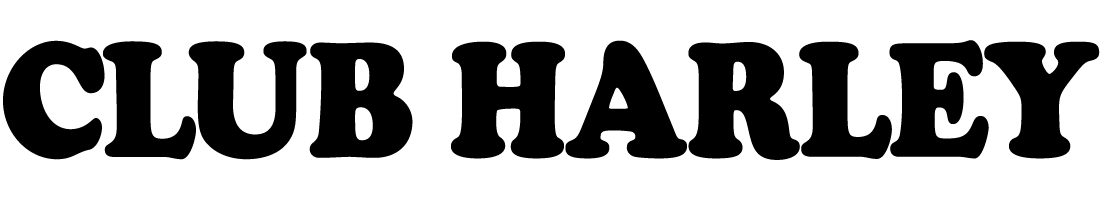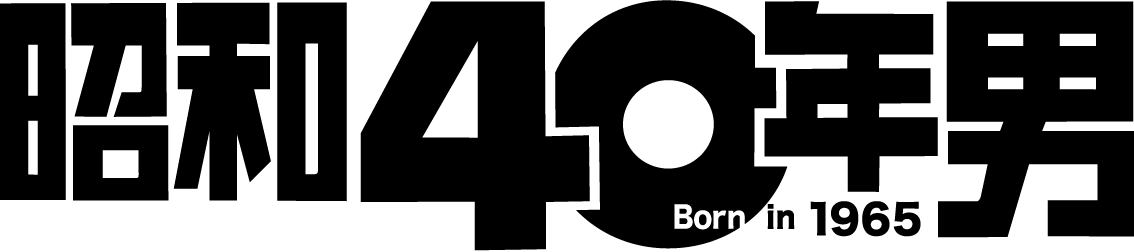本記事ナビゲーター「Pt.アルフレッド」代表・本江さんと児島さんとの関係とは?

三浦哲也さん著『自炊者になるための26週』の一節、“シェアすべきなのは、パーツではなくて、ホール(丸ごとの流れ)です”。最近、改めて考えてしまうこのキーワード。
本連載では洋服業界の御大を紹介させてもらってますが、今回は2007年の2nd創刊前に、メンズファッション業界の『丸ごとの流れ(ホール)』を、まだネットではなく本人の貪欲な好奇心と抜群のフットワークで情報を掻き集め編集してきた元ビギン編集長・児島さん。
「装苑」編集長もついこの前、退職されて〈Zoff〉に転職。このタイミングならと久しぶりに電話してみました。あの時代のことをキチンと書いてくれるならと快諾。取材時は勉強のためと編集部員全員同席で書けない話もたくさん出ましたが、絞りに絞っても特別拡大版になりました。
ファッション編集者を志したつもりはない。

2004年より雑誌『Begin(ビギン)』の編集長として、男性ファッション誌におけるひとつの黄金律を確立した児島幹規さん。圧倒的な情報量と物欲を掻き立てるワードセンスで読者を総識者化させ、就任当時には最高発行部数を叩き出した手腕の原点と、ファッション、そして出版メディアへの思いを訊いた。大学在学中より出版メディアに携わり、出版業界と広告代理店に絞って就職活動をした結果、1992年に世界文化社に入社。同年、ビギンへの配属が決まったものの「ファッション誌の編集者を志したつもりはなかった」と振り返る。
「大学在学中に編集アシスタントを経験し、出版業界に興味を持っていたことは事実ですが、当時携わりたかった雑誌は『SPA!』でしたし(笑)、配属先としてたまたまビギンに籍を置くことになりました。当時(1988年創刊)の同誌は完全なる“モノ”雑誌で、車、時計、パソコン、カメラ、靴、鞄などが軸でした。
編集長になる2004年までの12年間、一度も異動がなかったのは、上司に重宝がられたからだと思います。スタイリストに頼まずモノを選び、原稿もほとんど自分で書くから経費が浮きますよね(笑)。1997年に英国まで「グローブトロッター」の工場に行った時も、出張申請していません。
理由は行かせてもらえなかったからですが、それならばと休みにして行くのですから、扱いにくい部下でもあったかも(笑)。ダウンジャケットを誰も着ていない時代に「モンクレール」を仕掛けた後、ダウンの良し悪しを知りたくてハンガリーにも勝手に行きましたが、そこで“フィルパワー”という単位を知り、世に広めるきっかけになりました。
前述の通り、僕はファッション編集者を志したつもりはなかったですが、編集長になってからモノを軸にしつつもファッション寄りに軌道修正したとは自負しています」
アメトラ復興は市場へのアンチテーゼ。
2000年代初頭、男性ファッション誌は大きく二分され、裏原宿の余韻を残したストリート&カルチャー、バブル期を通過した中年層向けモテ&ラグジュアリーが主軸となり、往年のアメトラやアメカジが鳴りを潜めるなか、児島さんは編集長に就任。
同誌のアイデンティティでもあった“モノを愛でる”感覚を、時の気運に迎合することなく、いかに独自性を打ち出すかが最たる課題だったという。
「他誌と差別化を図りながら部数を伸ばすために考えたのは、当時ダサいとされ、売れていないもの中から、いいものを選びフォーカスすることでした。多くの雑誌はブランド名や見た目でモノを紹介しているからこそ、モノを愛でる感覚を持つ、見た目だけを価値基準にしない人々にどうアピールできるかを考えた末、イタリア一辺倒の時勢に、語り継がれる背景を持ち、長年愛し続ける人たちがいるアメリカ推しをはじめました。
それは自らの価値基準を持たず、見た目や高価なモノになびく人々に対するアンチテーゼでもあったと思います。その最たるが、デニムのロールアップでした。当時主流のデニムは海外セレブが穿くようなブーツカットばかりでしたが、あえてワンウォッシュかリジッドのストレートに絞り、当時最もダサいとされていたロールアップを推しました。その企画を見た他誌の編集者から「あんなカッコ悪いことよくできるね」と笑われましたが、半年後には日本中でロールアップが主流になりました(笑)。
僕は30代になった頃、下の世代、いわゆるチーマーやスケーター世代の感覚が全くわからずにいました。そこで仕事終わりの深夜に渋谷のセンター街や池袋に出向き、彼らのスタイルを観察したのです。夏の暑い時期はTシャツとショーツに足元は〈ヴァンズ〉だったのが、季節の移り変わりとともにTシャツの上にパーカを羽織りショーツがヴィンテージデニムになり、足元はくるぶし丈のスニーカーへ。
その世代はスタイルを大きく替えるのではなく、足し算していることに気が付けました。その感覚を持つ世代に向けて、彼らの足し算を逆手に取ったのがロールアップだったのです。デニムをロールアップさせれば、靴はロングノーズではなく、当時誰も履いていなかった「オールデン」や「クラークス」や「ニューバランス」などのラウンドトゥになるだろうと。
アメリカのトラディショナルに触れてもらうことが、人々の興味をモノの本質に戻しやすいという計算もあったとは思います。僕らよりも上の先輩方が影響を受けた、戦後のアメリカのカルチャーが今日のメンズカジュアルの軸となっているのは疑いようのない事実ですし。
自分で言うのもなんですが、あのタイミングでロールアップを仕掛けていなかったら、それからのアメカジやアメトラの復興はなかったのかもしれませんね(笑)」
アメリカ製ではなくアメリカ的という解釈。
また、当時の気運を語る上で欠かせない出来事のひとつが、消えゆく本国メイド。多くのブランドがコスト面や生産効率、リスク分散を理由にアジアや途上国へと生産拠点を移し、由緒正しき純アメリカ製や純英国製のプロダクトは次第に市場から姿を消していった。
「2000年代初頭頃から『ヘインズ』『ヘルスニット』『コンバース』など、名門や老舗と呼ばれる多くのブランドが生産拠点をアジアへと移していきました。米国製でなくなったから買わないという声がある中、編集者としてそのブランドやプロダクトが継続されることをどう受け止めるべきなのか。
当時「ビームス」とのダブルネームで話題になった『アンディアモ』(ミルスペックなバリスティックナイロンを用いたアメリカ製バッグブランド)がなくなる際、セルツの中川さんが同素材を使ったアメリカ製ラゲッジをなんとか世に残そうと日本企画で始めたのが「ブリーフィング〉」でした。
僕より上の世代に根付いている“ねばならない”という感覚を以てするなら、それらは買うに値しない、似て非なるモノになんでしょうけど、“昔は良かった”と語る人たちに耳を傾けないタイミングをどこかで作らないと未来がないと考え、米国製も米国製でなくなったものも一緒に紹介するために“アメリカ的ブランド”と名付けた苦肉の策が価値観を変えるきっかけになりました」
ファッション目線でプロダクトを語る。
「児島編集者時代に一気に読者の偏差値が上がり、頭のてっぺんから爪先まで高スペック、好ウンチクで固める通称“Beginくん”が氾濫した(笑)」と本江さんも振り返るように、読者の多くが靴の製法から木型までを完全に記憶するほど、モノを愛でる感覚に深度と強度がさらに加わっていった。
「僕が編集長になりファッション寄りに軌道修正したとはいえ、あくまで主役はプロダクト。そこでプロダクトをファッションとして扱うことに軸足を置きました。単にその背後やウンチクを語るだけではなく、バカバカしくて読みやすい原稿を接点として、いかにモノの本質を伝えていくか。
読んだ読者が自分主導で選んでいる感覚を持てる記事にしたいと常に考えていました。ですから取材で判明した事実を書くにしても、仰々しい上から目線ではなく、“らしい”、“みたいだ”と伝聞であることを強調し、誌面もあえてダサさというか、感覚的な余白を残しました。
上から目線でカッコつける誌面は、言い方を変えるなら誤魔化すことになり、伝えたかった本質から遠ざけることにもなります。モノに紐づく背景や誕生秘話も、美談にしなければ本来地味で泥臭いもの。
ですから、堅苦しいモノにはあえてユーモアを加え、安価なモノや身近なモノは重厚かつ学術的に伝えるなど、タイトルや原稿は逆方向からの視点を大切にしていましたね。どう書くかは掲載するモノ次第ですから、撮影前の商品全部に目を通していました。
特集で紹介する予定のモノを一旦編集部に全て集め、モノを見ながら構成を考え、その場でタイトルをつけながらどう撮影するかを部員と夜通し話し合うのが当時のスタイル。深夜のテンションだからこそ生まれた冗談みたいな企画もあります(笑)。
このご時世では全くお勧めできないやり方ですが、どの部員よりも僕が一番寝てなかったから、誰も文句が言えなかったのかも。荷物を机の上に残し、居るふりをしながら家で寝ていた部員もいました(苦笑)」
雑誌の顔でもある表紙をあえて“汚す”。
雑誌の誌面やレイアウト、写真や言葉遣いにも当然トレンドがあり、ジャンルや対象読者層によってそれぞれの流儀もある。時代感に沿ったアップデートは不可欠ながら、他誌との比較は無意味だと児島さんは続ける。
「他誌に真似されることはありましたけど、自分がテーマやデザインを真似したことはありません。自分が編集長になる前ですが、今も続く巻頭企画を主観で選ぶベスト10形式に新設したのは、他誌と比べられることで、独自性が消えると思ったからです。
僕は『ビギン』という雑誌をある意味で“カッコ悪く”作っていました。ファストファッションのタイアップを断ることで、掲載しているブランドを守り、ハイブランドを取り入れないことでブランディングに惑わされないようにするのも読者に対する正義じゃないかと。
当時『バーニーズ・ニューヨーク』のクリエイティブディレクターだった谷口さんと飲みに行った際、『児島さんは何を考えて雑誌を作っているんですか?』と問われ、『僕は表紙を汚しています(笑)』と即答したところ、『児島さんは無意識にわかっているんですよ』って言われたのです。
『現代人はキレイに慣れすぎている。広告に写る女優さんも全て修正済みで、ネットの情報だってキレイに導線化されている。キレイが当たり前になってしまうと、何かしらの違和感や変化がない限り、人の心を動かすことはできない。それを無意識に誌面に反映しているんですよ』と言われ、理解してくれる人がいると、自信に繋がったのを今でも覚えています。
僕はアメリカでもイタリアでも面白いと思えば節操なく掲載していましたし、表紙にもその節操のなさは意識しました。今年の春まで10年以上務めた『装苑』に関しても、ロンドンに行ってヴィヴィアン・ウエストウッドの連載を決めつつ、アイドルを表紙に起用して衣装特集をする。
『こうあるべき』、と『その破壊』がセットだからこそ新しい人たちに届く。媒体が変わっても基本的な考えは同じでした」
好きなモノだけを買うことが真のサステイナブル。
児島さんがビギン編集長に就任してから20年。時代の主流がデジタルに取って代わり、人々のライフスタイルも激変した。いま児島さんは何を思うのか。
「編集に関してはこんなに大変で、こんなに面白い仕事はないと思っていました。だから30年以上続けられたのでしょう。僕はInstagramを見たことがありません。ビギン時代にブログを頼まれても断っていたのは、誰が読むかわからないものを書けないから。広く浅く書くとストレスでしかないんですよ。
『装苑』時代に服飾専門学校で講義をするようになり、学生に対して『新しいことに挑め!』と話している自分がこのままでいいのか? という疑問から、以前からお話をいただいていた、メガネブランド『ゾフ』を運営するインターメスティックさんにお世話になりましたが、編集を離れて思うのは、出版というメディアがあの頃と変らなすぎだと。
後輩から「継承してます!」と言われたりしますが、時代が変化しているのに発信する側が変わらないのはおかしい。スマホの普及で、何を着ていようと他者と繋がれるようになり、ファッションでアイデンティティを伝える必要性が減りましたが、同時に“他人からどう見られているか”という、生きるのに邪魔なカルチャーが大きなビジネスになった今こそ、やれることはある。
僕がいま雑誌をやるとしたら、目先の数字に惑わされず、無名だけど本質を伝える人やモノをまとめながら、薄っぺらい情報源に喧嘩を売ることで支持者を集めて大きなウネリを狙う。旗を振る人がいないだけで、振ればついてくるもんです。ダサかったロールアップや、誰も履いていなかったニューバランスがこうなったように(笑)。
今後のファッションに関して言えば、いろんな企業がサスティナブルを謳っていますが、最もサスティナブルなのは、自分が好きな服だけを買うことだと思うので、紙媒体にはそういった思いを伝えてほしいですね」
様々な“完売伝説”を記録したあの頃の『Begin』誌面。

「新しいことは、人がやりたがらないことの中に必ず残っているから、面倒なことを楽しめる編集部にした」と語る児島さん。モノ選びのこだわりは当然、それに合わせて誌面には緩急をつけ、視覚的に印象に残すもの、現地取材など読み込ませるもの、さらには独自の提案に業界人を巻き込みその後の反響をイメージするなど、毎号異なる角度からの企画を盛り込んだという。「プレスリリースに載っていないことをどれだけ面白く書けるか」という個性的な原稿も人気だった。
児島さんが選ぶアメリカ的傑作10。
児島さんが作ったビギンの名物連載「BB10」になぞらえて、あの頃を思い出しながら“アメリカ的”視点で選出。「ボロボロになるまで履き込んだダナーライトやリーバイスなども候補にありましたが、当たり前のものより、当時を懐かしみつつの現役選手を軸に選びました。レアもの自慢ならほかにもありますが、使わない高級品より、使える傑作品を愛でる人が増えてほしいですね」
01…ありえない一着を読者のために♡|ビギン20周年記念別注のループウィラー

読者が好きなセレクトショップの名前を一着に入れ込みたい! とダメ元で各プレスに相談したところ実現した“読プレ”。部員にも一着ずつ配りました。テレビ番組『宇宙でイチバン逢いたい人』で和歌山のカネキチ(釣り網の工場)に行ったのが懐かしい。
02…最近はゴルフおじさんのイメージが強くなったので黒以外を引っ張り出しました|ブリーフィングのバッグ

黒はこの3倍持ってますが、昔のカーキを引っ張り出しました。最近ヘルメットバッグを見かけないので使ってみようかな。
03…誌面映えを考えて(笑)|エル・エル・ビーンのボート・アンド・トート

フリーポートの本店で読者と部員と自分用に購入。ワッペンは後付けです。現地で入れた刺繍がダサくてお気に入り(笑)
04…メイデンの加藤さんお元気ですか!|インディビジュアライズドシャツのBDシャツ

アメトラが売れない時代にこのシャツを仕入れていた加藤さんを応援してました! 写真のシャツは、今では考えられないほどのタイトフィット(懐)
05…パリのアナトミカで買った20年選手|オールデンのレースアップブーツ

実は“履かず嫌い”していました。パリのアナトミカでコイツ(カーフのアンライニングのモディファイドラスト)を見つけてから履き始めパリでは計7足購入。左は別注したコードバン。ハトメの緑青で、最近履いていないのがバレますね(笑)
06…この本は本家BB10でも一位でした|ラルフ・ローレン

到底アイテムを絞りきれないので写真集を! パリの新店がオープンした際、御大とお食事したのはよき思い出です。
07…実は576しか履いたことがありません|ニューバランスの576

UKメイドを理由に576から推しました。その思い出として、ボロでも捨てられない一足。
08…デニムの再構築は完全なるファッションでした|リーバイスレッド

限定店舗に超限定数。貸出してもらえない媒体が多かったのに、ビギンに必ず載っていたのは、日本に入る前から展開の相談に乗っていたから(笑)。欧州企画の再構築デニムは、その後に与えた影響も大きかったですね。
09…いまだヘビロテ|サニースポーツのシャンブレーシャツ

いま誰も着ていないアイテムは? から始まったGOODなシャンブレー探し。後にビギン編集長になる光木の紹介でした。
10…70年代アメリカの香りがしません?|パルサーのタイム・コンピューター

ポラロイドSX-70といい70年代のUSデザインはいいですね。コイツを紹介した後、LEDウォッチが大ブームに(なったと思ってます)
(出典/「2nd 2024年12月号 Vol.209」)
関連する記事
-
- 2025.07.12
柄が違うだけじゃない! 奥深きアロハシャツのディテール編
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)