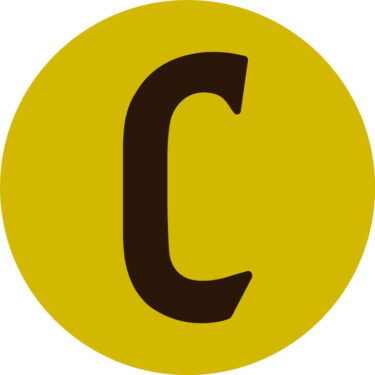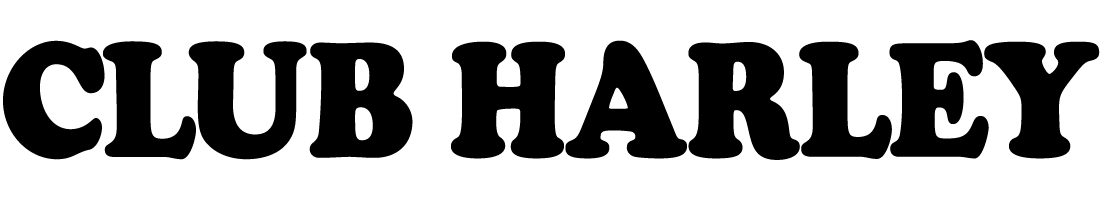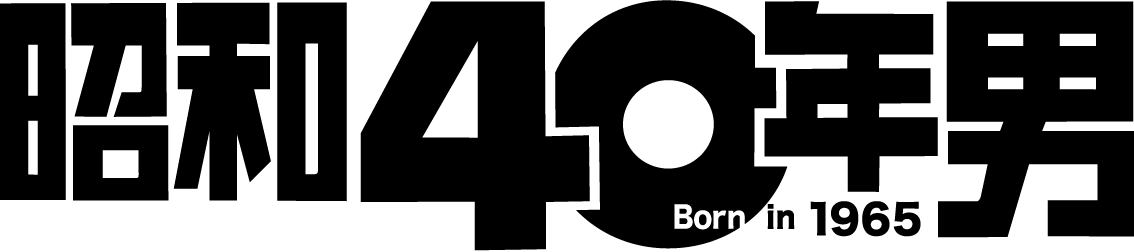「Pt.アルフレッド」代表・本江さんと「ナミキ&サンズ」代表・並木正明さんの出会いとは?
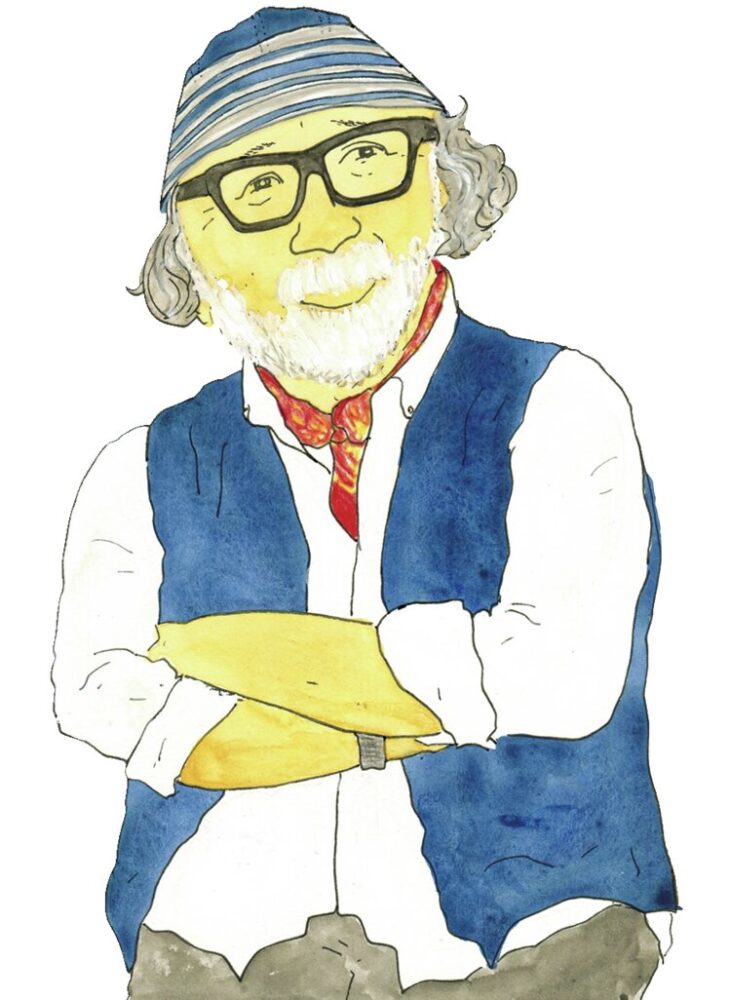
もう40年以上前ですが、当時勤めてた会社で営業担当を任せてもらったのが北関東エリア。そのなかでも街の規模感、大都会との距離感が個人的に故郷の高岡と重なり熊谷のナミキさんはホントによく通いました。この連載の企画がスタートした頃、たまたまテレビで最近話題の旧車系の番組を見ていたら矍鑠としたマスターのお姿が!! ずいぶんとご無沙汰をしていたのですが、早速SNSを掘ってみました。
息子の徹也くんは川越から熊谷に戻り、オリジナル商品を頑張っている話は業界の新聞で知り密かに応援してましたが、やはりマスターの歴史的な話は特別だと思い、早速連絡して登場を快諾していただきました。創業されてもうすぐ55年! 若い頃散々お世話になった並木社長、まだまだ現役バリバリの洋服屋のオヤジさんです。
拭い去れなかった 東京トラッドへの憧れ
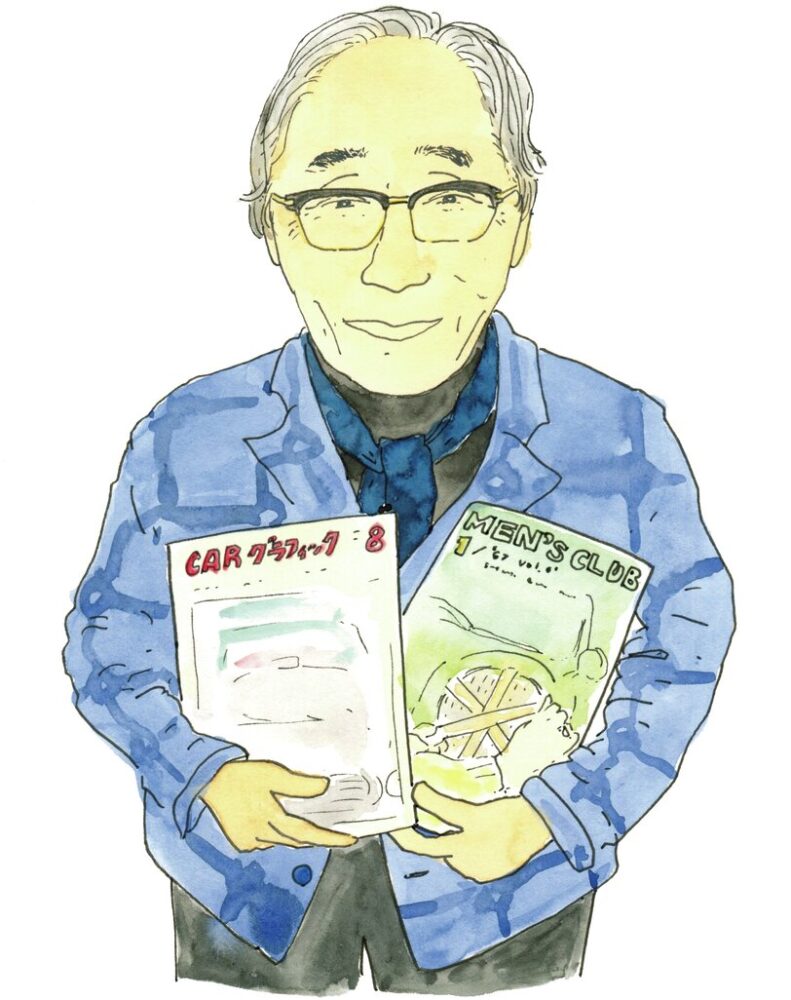
今から50年以上も前、並木さんは大学卒業と同時にアパレルの道を志した。当初の就職先は大阪の生地問屋。さらに数カ月後には当時学生服のメッカだった岡山に配属され、自問を繰り返す日々が続いた。
「軽トラで得意先に生地を納品するのが僕の主な仕事でした。そのなかに当時心斎橋にあった『VAN』も含まれていて。彼ら(スタッフたち)がコッパンにボタンダウンシャツを着て頭は七三分けなのに対し、僕はナッパ服(作業着)。当時としては結構頑張って大学まで出ていましたから『なんでこんな仕事を選んでしまったのか』と、若気の至りというか変なプライドもあって(笑)。そのうち岡山へ転勤が決まり、そこで『マルオ被服』の大島さんという方と知り合い、彼が「この先ジーパンをやりたいと考えているんだけど並木くん、ウチへ来ないか?」と誘ってくれたのですが、僕はもう関東に帰ることを決めていましたし、丁重にお断りして。
さらに岡山には石津(謙介)さんの親戚筋がやっている「スナミ」という特約店があり、毎週のように通っていたところスタッフさんとも仲良くなり、丈詰めに出していたパンツをわざわざ届けてくれたことがあって。その時、彼が乗っていた車がブルーの『トヨタ』S8だったのを鮮明に覚えていて、どうせ働くなら彼らのようにカッコよく働きたいという思いがさらに強くなっていきました」
件の生地問屋では都合4年のあいだ研鑽を積んだものの、結局は関西の水が合わず帰郷。ちなみに先出「マルオ被服」は後に「ビッグジョン」として国内デニム最大手の一角へと急成長を遂げている。
「大島さんの誘いに乗っていたら、また違った人生だったのかもしれませんね(笑)。ただ、僕はとにかく東京へ帰りたかった。でも、親父がネックになっていて。もともと足袋屋だった親父の口利きで就職した以上、ある程度結果を残すまでは帰れないと考えていたところ、当の親父が急逝し、そのタイミングに乗じて何のアテもなく地元へ帰り、どうにか「VAN」ができないかと、まずは地元の百貨店『八木橋』で小売りのノウハウを覚えることにしました」
1号店オープンVANの倒産
今でも熊谷のランドマークでもある「八木橋百貨店」は明治30年に「八木橋呉服店」としてスタートし、北関東ではいち早く「VAN」の商品を取り扱っていたという。
「2年間、『八木橋』の外商部で農協に金庫をセールスしていたのですが、どうしても『VAN』の特約店を自分でやってみたかった。そこで熊谷駅前に間口1.7メートルの物件を用意し、『メンズショップナミキ』という1号店を開業しました。お金があるワケでもないですし、そもそも『VAN』なんて一流どころではなく、その他の言わば類似ブランドでもイイんじゃないかと思われるかもしれませんが、当時の僕は『VAN』以外に考えがなかった。そこで無謀にも『VAN』の本社へ直談判に行ったのですが、間口が1.7メートルしかないとウインドウは作れないし、店にならないと断られしまって。神田の問屋街にいた兄を連れて2度目の直談判へ行ったところ、ようやくお付き合いできるようになり、『ナミキ』のキャリアがスタートしたワケです」
1号店はまさに順風満帆な船出を切り、瞬く間にエリア有数の有力店として5年が経った頃、第4次中東戦争に端を発したオイルショックの余波が残る1976年、絶頂期にあった「VAN」がまさかの倒産。とはいえ、そんな不景気に影響されることなく、事業は徐々に拡大していったという。
「近隣に大学があり、4月になると毎年新しいお客さんが増え、事業も軌道に乗り始めた頃、常連さんのひとりが雰囲気のいいマドラスシャツを着ていて、どこで買ったか訊いたら自由が丘の『ナック中村』というお店だというので早速行ってみると、ほとんどインポートものだったんですね。個人的には『VAN』だけでなく、アメリカやヨーロッパものをやりたいと考えていましたが、当時の商社が僕らのような小規模の小売店なんて相手にしてくれるはずがなく、かなり苦労したのを覚えています。

それが70年代半ばを迎える頃には、以前この企画にも登場されていた吉井さん(現カントリー貿易・代表)らがいた新進貿易など徐々にルートが開拓され、インポートものを取り扱うようになっていきました。とあるインポーターの方が主催したアメリカ西海岸ツアーにも同行したところ、僕はまだアイビー的なスタイルなのに対し、周りは皆ジーンズで『Made In U.S.A Catalog』で紹介されたスニーカーやワークブーツなどを掘り漁っていて、そこでまた意識改革が進み、インポートカジュアル中心の『カントリーロード』という店をオープンするに至りました」


レジェンドが思うファッションの現在地
敷地面積100坪という大型店舗を含め、80年代以降は川越含め数多くの店舗を展開。現在は御子息たちがそれぞれ後を継ぎ、今なお数十年にわたり通い詰める顧客も少なくない。
「熊谷というある意味至近にある都市ですから、僕含め東京に対するコンプレックスが強くあったと思うのです。特に学生時代の多感な時期は。お客さんのなかには、東京を想起させるブランドがウチでも展開されているのを嫌がる人もいたくらい(笑)。それほどに東京を特別視する界隈でもあると思うのです。とはいえ、この55年の間に僕がやりたかったことはある程度かたちにできたと考えています。足を引っ張られたり、常に順風満帆ではなかったものの、アパレルの世界でこれまでやってこれたのも当初のこだわりがあったからだと思っています。
ただ、ファッションというジャンルの影響力は80年代半ば頃までが最盛期だったとも思うのです。ワンポイントブーム(ブランドアイコンをワンポイントで飾ったウエア類)に代表されるファッション派生の流行は80年代を境に弱まっていきました。それぞれのライフスタイルや価値観の多様化が進み、遊び方や遊ぶ街さえも変わっていった。もちろん景気の影響もあったのかもしれませんが、アメ横ではなく渋谷や原宿や新宿に若い世代の興味が移り、サラリーマンの間でゴルフが台頭した辺りから、それまでとは若干異なる景色が見えてきた。あの頃のように誰もが同じウエアや遊びに飛び付くようなブームが、今はもう起こりづらくなっているのかもしれませんね」

そう語る並木さんははクラシックカーにも精通している。今なお現役で様々なイベントやミーティングに参加するなど、業界でも知る人ぞ知る旧車マニアのひとりでもある。
「クルマは常にファッションと同等に僕のなかでもプライオリティが高い趣味のひとつ。思い返せばモーターカルチャーとの親和性もこだわりのひとつなのかもしれません」
「メンズショップナミキ」のいち押し

フランス語でレースを意味する国産ブランド「コース」のイタリア製撥水シェルを使用した全天候型ドライビングジャケット。7万7000円

「オールデン」のコードバンパンチドキャップトゥはサイズさえ合えばかなりお値打ち価格。12万4300円(ともにメンズショップナミキTEL048-526-2006 http://namikiandsons.blogspot.jp)
本江MEMO

かつてめちゃくちゃお世話になっておきながら、ずいぶんとご無沙汰してしまいました。久しぶりの熊谷、変わらずいい街でした。帰りに五家宝を買って帰りましたが相変わらず旨かった。自動運転だのいろいろ簡単な時代に、あえて旧車をイジりながらキチンと運転されてる姿勢、簡単にネットで売ったり買ったりできる時代に、しっかり顔を見て話しながら販売する街の洋服屋の基本を再認識した取材でした。ウチは今年30周年ですが、あと25年…無理そうです!(笑)
(出典/「2nd 2024年7月・8月合併号 Vol.206」)
Text/Takehiro Hakusui Illustrator/Maki Kanai
関連する記事
-
- 2025.07.08
革ジャンの伝道師・モヒカン小川の私物大公開! 経年変化を楽しむ“茶芯”ってなんだ!?
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)