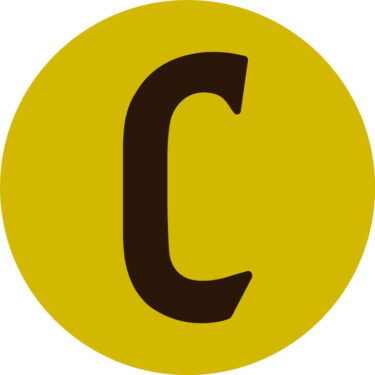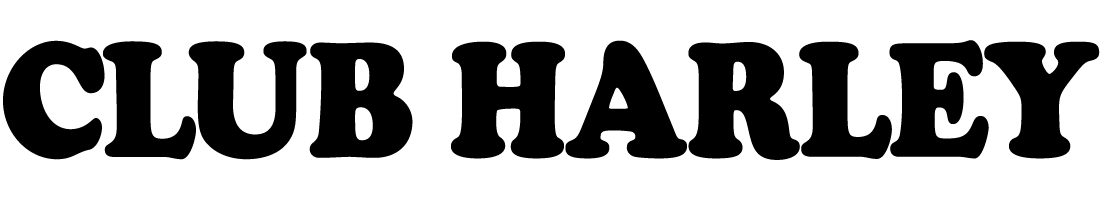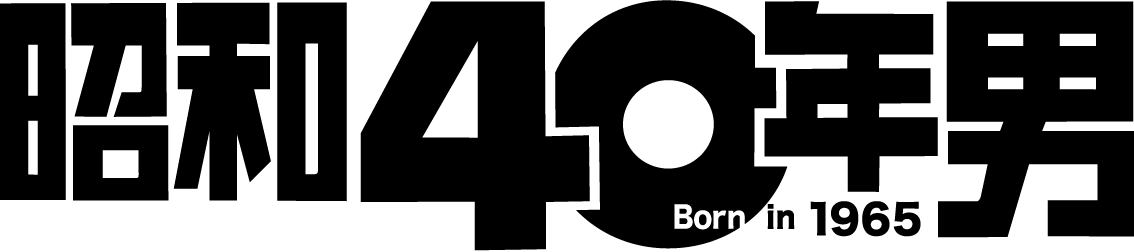「手法は絵でもなんでもよくて、それが世の中にないから作っている」
── まずMatisさんの人となりに触れたく、とりわけ影響を受けたコンテンツについて教えてください。
学生時代は周りと同じようにロックバンドに影響を受けました。JAGATARA、ブランキー・ジェット・シティ、フィッシュマンズ、この3つのバンドのクリエイションには尊敬を持って接していましたし、その後に様々なジャンルの音楽も聴きましたが、結局はいつまで経ってもそこに戻っていって。今でも10代の頃と同じ熱量で聴くことができます。中でもJAGATARAのクリエイションは、今現在の活動にも結果的に影響していて。
── 結果的に?
はい。JAGATARAの江戸アケミさんが残した「お前はお前の踊りを踊ればいい」的な名言があるのですが、彼の死後に盟友でもあった近田春夫さんが「確かにその人なりの踊りを踊ればいいとは思う。けど、踊りってやっぱりカッコよくなければダメだよね」とコメントしていたネットプログラムを観て、ガツンとヤラれたというか。
創作活動において、たとえ無二のオリジナリティがあったとしても、カッコよくなければ意味がないんじゃないかと考えるようになりました。創作活動を続けている以上、“ないから自分で作り出す”が大前提ながら、他人からも評価されるものでなければあまり意味も持たないと、それ以来より強く考えるようになりましたね。
── 他にもありますか?
おそらく漫画『殺し屋1』の受け売りだと思うのですが、大学時代の友人が常々「必然性が大事だ」と言っていたんですね。当時は正直なところ、何を言いたいのかあまり理解していなかったと思います(笑)。でも、今になってその意味合いにだんだん気づくようになって。
「これを作る意味があるのか」、「自分がやる意味があるのか」、「世の中に必要なのか」、「今やらなきゃいけないのか」とか、モノ作りをする前段でそう自問するようになったのは彼のお陰でもあると。
── 大学での専攻は?
映像です。高校時代まではグラフィックデザインの方へ進みたいと考えていましたが、いざトライしてみたら、それほど身が入りませんでした。そこで映像学科へ進み、映画を撮るワケですけど、基本的には集団で作り上げるものじゃないですか。それがまた自分の性には合いませんでした。すべてを自分のみで完結する方が本来の力を発揮できると考え、ある程度は絵も描けたので、ならばアニメーションだろうと。
── どんなアニメーションだったのでしょうか?
それまでは所謂、商業的な娯楽作品かNHKで流れるようなものしか知りませんでしたが、学校に入ってからアートアニメという世界があることを知りました。ユーリ・ノルシュテインというロシアの監督が制作した『ケルジェネツの戦い』という作品を観てからはこういう作品を自分ひとりで撮ってみたいと考えるようになって。
一応、卒業制作まではそれほど本腰とまでは言えないまでもアニメーションを作り続け、卒業後は東京藝術大学大学院のアニメーション学科に進もうと受験したまではいいものの、見事に落ちてしまって(笑)。それからは一旦(約4年間)創作活動から距離を置き学童クラブで働くようになりました。
── 学童クラブでは何をされていたのですか?
僕が務めていたところは、下校からご両親の仕事終わりまで子どもたちを預かるといった一般的な学童ではなく、子どもと一緒に揉まれて、ぐちゃぐちゃになって、ともに生活もして一人ひとりに寄り添うスタンスだったんで、かなり貴重な経験だったと思いますし、今の創作活動にも少なからず影響があったと考えていますね。
── その間は一切創作活動から離れていたと。
なんとなく続けていたというか。でも、再び本腰を入れて向き合うようになったのは、僕のデザインをレザークラフトで興してくれる友人たちといろいろ作ることになり、それならば屋号が必要だろうということで、かつてその友人が運営する工房のショップカードを制作した際に引用した文言を着想にMatisと命名して。28歳の頃ですね。
「表現したいニュアンスと同時にそれに見合うだろう質感がまず浮かぶ」
── それからはイラストレーターとして活躍されていますが、その作風は多岐にわたりますよね。ご自身的にはどのラインを基軸と考えているのでしょうか?
今は貼り絵とカリグラフィー、といってもカリグラフィーに関しては自称“インチキカリグラフィー”としてやっていて(笑)。正統派の手法では何度トライしてもダメだったので。とはいえ、イラストレーターとして活動している以上、オーダーがあればなるべく応えているつもりです。
ただ、先にもお話したように必然性を常に考えているので、自分がやって本当に意味があるか自問しながら続けているのが現状です。貼り絵に関しては学童クラブ時代に行ったキャンプの文集を作った際、挿絵を描きました。その際、時間が許すのであれば自分が求める質感があって、それを後になって突き詰めたところが貼り絵でした。


── アーティストという肩書には抵抗がありますか?
抵抗がないかと言われたら嘘になりますね。僕の場合、表現したいニュアンスと同時に、それに見合うだろう質感がまず浮かびます。つまり表現に手法や技術を寄せている部分があって。でも、いわゆるアーティストと呼ばれる人たちは、何より自身の手法や技術を表に出している。それはそれで素晴らしいですが、ひとつの表現法を続けていくことに対して、個人的にはあまり魅力を感じないのかもしれません。
また、わかりづらくてカッコイイ抽象的なものにももちろん惹かれますが、現時点でのマインドとしては、わかりやすくてカッコイイもの、言わばコマーシャル的なものに惹かれているので、アーティスト的な立ち位置が今は居心地悪いのかもしれません。まあ、天邪鬼なのは自覚していますし、あまり僕自身が前に出るスタンスには抵抗を感じているのかも(笑)。

── 自称“インチキカリグラフィー”については?
カリグラフィーってセンスも技術も必要で。私は単純にあこがれから入ったので、ひたすら練習からはじめました。私の描き方は専用のペンを使用しないので正攻法の人から見たらメチャクチャです。ですが、やることは同じで、反復練習、考察を通して線のストロークを体に覚えこませる。
学生の頃はデッサンにしてもあれだけ練習していたのに、大人になって絵を描くと“自分の表現”ばかりが先行して地道な努力をしなくなる。カリグラフィーという伝統技術を通じて、当たり前のことに気づかされたのは、とてもよかったと思っています。

── 「わかりやすくてカッコイイもの」が今現在のモードとのことですが、見る側、伝わる側には、どのように作品に接して欲しいとお考えですか?
やっぱりどんな作品にもブームやトレンドみたいな時流が反映されているとは思います。10年、20年先に振り返って「ああ、そんな時代があったね」みたいに、ひとつの流行としてまとめられてしまうものも少なからずあると。とはいえ、個人的にはそんな時流に乗ること、言わばその時々のメインストリームを真似したり真似されたりすることには、かなりの抵抗があります。
ひとつのトレンドを作ることも真似ることも本当に簡単な時代ですし、ともすればオリジネーターよりも真似をしたフォロワーのが評価されることまである。そんな流れになるべく乗らないよう、本能的に仕事を選んでいるのかもしれません(笑)。
── これからトライしてみたいことは?
やりたいことを自分なりにまとめているネタ帳があるのですが、まずはそれらを自分なりに消化したいと考えています。切絵や貼り絵が特にそうなのですが、実際にやってみてイメージ通りにならないことも少なくないので、まずは自分に課した課題をひとつずつクリアするところから徐々に進めていきたいですね。

(出典/「2nd 2024年2月・3月合併号 Vol.202」)
Photo/Ryota Yukitake Text/Takehiro Hakusui
関連する記事
-
- 2025.07.12
柄が違うだけじゃない! 奥深きアロハシャツのディテール編
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)