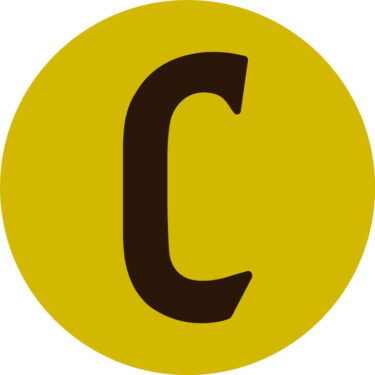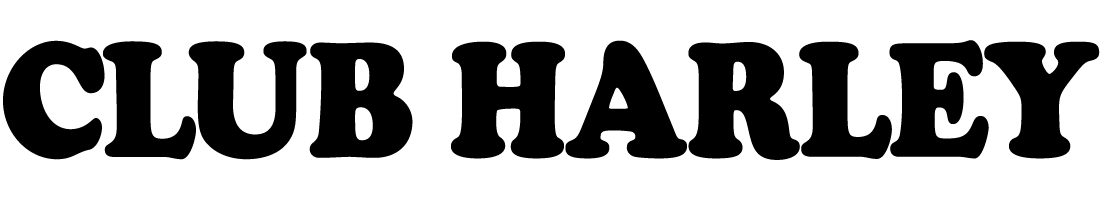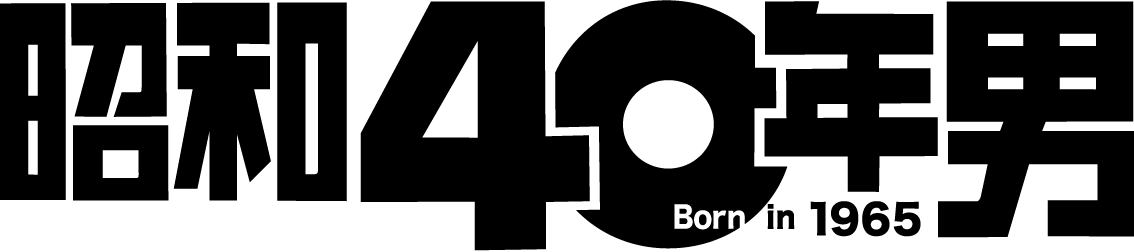「様々な仕事をしていますが、素敵なものを作りたい、その一心です」

ファッションデザイナーとして自身のブランドを持ち、映画やドラマの衣装にも携わりながら、現在は「ブルーチップ アトリエ」名義でアートピースとしてのキルト制作も手がける玉置博人さん。有機的なつながりで極めて自然に拡がってきた氏の創作活動のこれまでとこれからを伺った。
——玉置さんの活動の最初期はファッションデザイナーですが、そのきっかけを教えてください。
もともと洋服のバイヤーに興味があって、将来はそういう方向がいいかな、なんて考えていました。あるときイタリアの「マランゴーニ学院」というファッション、デザイン系の名門専門学校が渋谷で1カ月間の短期コースを開催するのを知って、当時、僕は京都に住んでいたのですが、それに参加してみることに。これがきっかけとなりデザイナーになりたいという思いが膨らんでいきました。
そのコースを終えて東京から帰ってすぐに大学に通いながら受講できるファッションの学校を探して、大阪の「バンタンデザイン研究所」の土日コースに通いはじめたんです。大学の3回生のときですね。バンタンではファッションデザイン、パターン、縫製を選択し、1年半、必死に勉強して服づくりの基礎を身につけました。
——バンタンを出られたあと、パリの「ステュディオ・ベルソー」に入学するんですよね。
基礎を学んだらそこから先はヨーロッパの学校で、と考えていて。まずバンタンを出たあと2年くらいはその資金を貯めるために京都の「藤井大丸」のなかのお直し屋さんで縫製のアルバイトをしました。ベルソーを選んだのは授業がほぼデザインについてだったから。2年間ほぼ家と学校、そして資料やデザインソース、コンセプトのもとになるものを探しに図書館や美術館、蚤の市に出かける日々でした。
「パリで生活」というと聞こえはいいですけど、食事や睡眠を極限まで削ってデザインに明け暮れていたので楽しかったというよりは苦しかったですね。ただ、振り返ってみるとあんなにも濃密な時間はあとにも先にもなかった。そのくらい贅沢な時間だったと思います。ちなみにその頃のあだ名は「プチ(小さい)・ヨウジ(山本耀司)」でした(笑)。それでベルソーを出たあと、フランスのいくつかのブランド、メゾンで働き、その終着点が〈バレンシアガ〉だったんです。
——バレンシアガではどんなお仕事をされていたんでしょう。
在籍したのは2シーズンと短期間なんですが、ニコラ・ゲスキエールがデザイナーを務めていたときでかなり話題になっていた時代のコレクション(2007年/2008年秋冬)に携わることができました。
僕がいたのはデザインがパタンナーに行く前に本生地でフォルムやディティールの研究をする部署。ガイルという女性と僕のふたりの部署で、そのシーズンのコレクションはすべて僕らのところを通って、それをニコラがチェックして初めてパタンナーにデザインが渡されるんです。素材やフォルムのすべてを見られたのは貴重な経験でした。

——それは得難い経験ですね、本当に。その後、帰国してご自身のブランド〈エ モモナキア〉をスタートするのが2008年。やはり自分のブランドを持ちたいと思ってのことでしょうか?
僕がバレンシアガで働いていた、ちょうど同じ時期にランバンで働かれていた城賀直人さんが、「日本で一緒にブランドをやらないか」と声をかけてくれて始めることになりました。その頃の僕は先のことなど何も考えられていなくて。映画のコスチュームやってみたいな、とかテキスタイルに興味があるな、という程度のものはあったんですが、自分でブランドを立ち上げようとは思っていなかったですね。バレンシアガに残るか帰国して共同でブランドを始めるか2週間くらい悩みました。
——そうだったんですね。〈エ モモナキア〉は実にユニークなブランドという印象でした。
スタートするにあたってまず城賀さんがやりたいことをヒアリングするところから始めました。そこで出てきたのがドレスを中心にラグジュアリーなものを、ということだったんです。パリではお互い歴史のあるブランドで働いていたのもあってその方向を目指しましたね。
最初のコレクションはビジネス目的でなくお披露目のプレゼンテーションでしたが、それを面白がってくれる人や媒体もいて、雑誌の『GINZA』が1ページ割いて紹介してくれたり、〈グラフペーパー〉をやっている南貴之さんが注目してくださったりしました。その後、南さんにはいろいろとサポートしていただきました。

——その後、ブランドは?
2016年/2017年秋冬まで続けてブランドは休止することになるんです。2014年頃はブランドは横ばいでしたし、僕自身、もともと人づきあいがあまり得意な方ではなかったのもあってファッション業界にいろいろと疲れてしまっていて。そんなタイミングで出会ったのが人物デザイナーの柘植伊佐夫さんでした。
知人から「柘植さんというヘアメイクですごく著名な方がいて、ぜひ一度会っていただきたい」と紹介されました。それでお会いした場で柘植さんから「映画やってみない?」と突然言われて。その映画というのが『寄生獣』です。とてもありがたい出会いで、今まで生き延びてこられたのもこの出会いがあったからこそだと思っています。
——衣装デザインについては「この作品も玉置さんが関わっていたんだ」という驚きがありました。
僕が携わった映画は原作が現代ものでなくファンタジーという作品が多く、そういう場合、イチから衣装をデザイン、制作するのですが、デザインから担当することもあれば、その補佐として入ったり、衣装制作として携わることもあったりと作品によって関わり方はさまざまですね。NHKの大河ドラマ『どうする家康』ではまさかの染色。この作品は柘植さんが人物デザイン監修で僕はその補佐として入っているのですが、染色もやることになりました。
——なるほど。ファッションデザイナーとしての経験は映画の衣装デザインや制作にどのように活かされていると思いますか?
ブランドをやっていたときは売れる売れないやコストの問題よりも、ただ素敵なものを作りたい一心でした。つまりどちらかといえば一点ものを制作する感覚で、今思えばそういうやり方は衣装制作に近いのかなと。なので衣装デザインや制作にすんなり入っていけたんだと思います。
「キルトを制作するだけでなく、空間での見え方をつねに意識します」

——現在は衣装デザインのお仕事に加えて、〈ブルーチップ アトリエ〉名義でアートピースとしてのキルトを発表していますね。
僕は4年ちょっと前に京都から東京に拠点を移したんですが、その頃、空間とかインテリアとかアートへの興味が高まっていたんです。衣装の仕事はすごく贅沢な仕事なんですけど、自分が携わるのはあくまでも作品の一部で、自分の表現の純度という意味では当然ながら制約があるわけです。それでちょうどこの時期、ブランドを休止したこともあり自分を表現することに飢えていて、何か始めたいな……、でも洋服じゃないなぁなどと考えていたんです。
そんなとき、たまたまアメリカンキルトをやっているブランドを知る機会があって、それに大きな衝撃を受けました。それで「キルトやってみたいかも」と思ったのが発端です。キルトってモダンな印象はないと思うんですけど、それを洗練させてアートとして提案できたら面白いんじゃないかと。
ちょうど同じ頃に、台東区千束にあるギャラリー「es quart(エス クォート)」のオーナーである鈴木(貞則)くんと出会えたのも大きいと思います。空間についていろいろと話すなかで「キルトをやってみようと思う」と言ったところ、彼も投資目的のファインアートじゃなくて、生活空間のなかで飾りたいと思えるアートを紹介したいと考えていたところだったと。そんな縁もあって、「es quart」で展開してもらうことになりました。



——キルト制作は玉置さんにとってどんな存在と考えますか?
キルト制作をしているときは、それに没頭して静かな時間が訪れるのですが、そういう時間は自分にとってすごく大切なものですね。精神的にも安定します。
——こうして伺ってゆくと初期から現在までの創作活動が自然なかたちでつながっているのがよくわかります。玉置さんの創作の源泉というと、どんなことでしょう?
いろんなことのサイクルがどんどん早くなっているじゃないですか。それに対するカウンターというのはあります。時代がどんなにファストになっても僕は変えませんよ、静かな時間を大切にしますよ、と。ただ一方で自分が40歳を過ぎて時間の有限さは意識するようになりました。基本的には何もせずボーッとしていたい人なんですが、いい意味で焦りの感覚を得たことでより積極的に創作に向き合えているように感じますね。
——効率化が最優先される時代にあって、自分をしっかり持つことの大切さを改めて実感しました。最後にこれから取り組んでみたいことがあれば教えてください。
キルトはありがたいことに個人の方のほか、パブリックスペースに展示していただいたり、海外からのオファーもあったりという状況ですが、全体像を見てもらう機会を設けたいと思っています。来年の春頃を目指して「es quart」でのエキジビションを企画しているところです。ちょうど壮大なコンセプトが決まったばかりなので楽しみにしていて下さい。









(出典/「2nd 2023年6月号 Vol.195」)
Photo/Ryota Yukitake Text/Kenichi Aono
関連する記事
-
- 2025.07.12
柄が違うだけじゃない! 奥深きアロハシャツのディテール編
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)