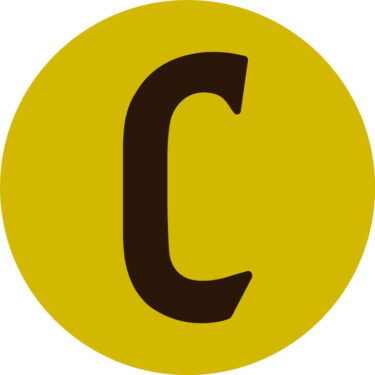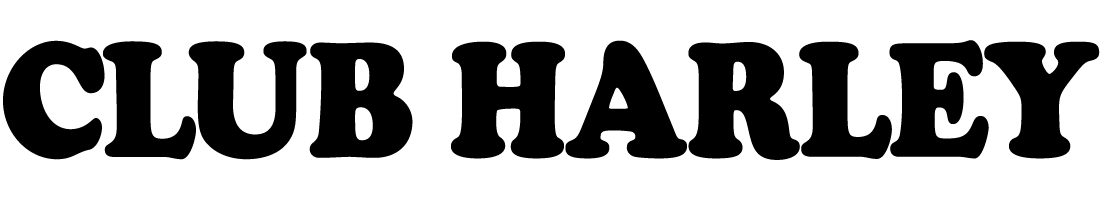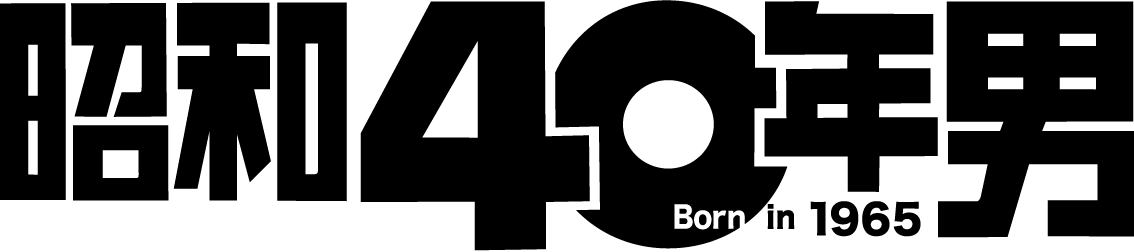日本独自の進化を遂げたシティポップ
「そもそも、日本のポップスって独特な変化をしてきた音楽だと思うんです。僕らミュージシャンは洋楽に憧れて、洋楽のような音楽を作りたいと思って音楽を始めたんだけど、歌詞は日本語で、これはある種ガラパゴス的な音楽と言っていいのかもしれないですよね。シティポップについても、僕は思うんだけど、これはラーメンやカレーに似ているのではないかと。カレーはインドが発祥のはずなのに、日本では立ち食いカレーから蕎麦屋のカレー、カツカレー、家庭のカレーとか、いろいろなパターンがあって、ラーメンも同様。もはや本物とはかなりかけ離れてしまっているのに、それぞれが美味しい」
確かに、その傾向は音楽に限ったことではない。日本という国自体が、時代の流れの中で海外の文化や技術を積極的に取り入れ、自国文化と融合させながら発展してきた歴史がある。なかには、オリジナルを凌ぐ製品まで開発してしまうこともある。それが日本の技であった。
「ビートルズで言えば、僕が最初に聞いたビートルズは『ビートルズ!』『ビートルズNO.2』という日本編集盤なんですね。あとから『プリーズ・プリーズ・ミー』がデビューアルバムだと言われてもピンと来ない。曲のタイトルにしても「抱きしめたい」という邦題だからあの曲のエネルギーを表現できているのであって、原題の「アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド」のままでは、曲のイメージが出来ない。そういうように、日本は独自の解釈によって文化を広げてきて気がするんです。曲が生まれたあと、世に出た場所によって、それぞれの運命を背負っていくのが、ポップスのおもしろいところで、シティポップもそういうことなんだと思いますね」
同じような話を聞いたことがある。ビートルズやピンク・フロイド、レッド・ツェッペリンなど洋楽のレコードは、音は同じでも、イギリスのレコード屋に並んでいるレコードと日本のレコード屋に並んでいるレコードは別物である、と。帯、邦題、歌詞カード、ライナーノーツによって日本仕様の日本盤は別物であるという。シティポップも、70年代後半から80年代前半にかけての日本で作られた音楽で、聴こえ方は当時のままだが、新たな価値観により、時代と国境を越えて独自の解釈で親しまれている。
「自分は地方出身者なので、シティポップと言われること自体がおこがましいのですが、昔作った音楽を今また聴いてもらえるのはとても嬉しいですね。最近、15歳の女の子から熱いファンレターも来て、すごく詳しく書かれた内容だったので驚いたんですが、サブスクやストリーミングの普及で、古い曲も新しい曲も同時に聞ける時代になっているのかなと思いますね。国境を超えていることも実感します。僕のライブで後ろの方にやたらノリのいい人がいるなと思ったら金髪の女性の外国人だったり。あと、ぼくはライブで村田和人くんの「一本の音楽」をよく歌うんですが、こないだは西洋人の男の人が日本語で一緒に歌っているんですよ。ちょっとそれにはグッときましたね」
転機となった大滝詠一との出会い

村田和人さんは杉さんと親しい間柄だったシンガーソングライターだが、2016年に急逝。「村田くんに見せてあげたかった」と杉さんは言う。また、杉さんに大きな影響を与えた大滝詠一さんも亡くなってから早10年の歳月が経つ。大滝さんが生きていたら今のシティポップの状況をどう見ているのか。その解説を聞いてみたかった。話は大滝さんのことに。
「僕のアーティスト人生にとって、NIAGARA TRIANGLE Vol.2に参加したことはとても大きい経験でした。大滝さんが僕の『NOBODY』っていう曲を推してくれたことで、いろいろなことが動いていったんです。当初まわりからは『今、ビートルズっぽい曲をやっても若い人には理解できないから』って言われていたんですが、『いちばん杉らしいからやりなよ』って言ってくれて、結果的に『NIAGARA TRIANGLE Vol.2』に収録したあの曲で僕のことを知ってくれた人が多かったんです。そのとき結局、自分がいちばん好きなことをやるのがいいんだなと。ミュージシャンって、まわりの人の意見と時代との両者の折り合いをつけて物事を進めていくけど、最後は自分なのかなって。時代は無責任ですからね」
50年近くプロのミュージシャンとして一線で活動してきた人の言葉は重い。80年代はバブル景気によって大型家電や娯楽家電が充実し、日常生活も目まぐるしく変化。レコーディング技術の進歩により、音楽制作環境も刷新された。
「80年代はボブ・クリアマウンテンの作った大きなドラムの音が人気で、それが主流になってからは、どんな大物アーティストも取り入れた。当時は、ドラムの音を大きくしないと不安になるくらいでした。でも今聞くと、やりすぎていたと気づいて恥ずかしくて、時代は責任取ってくれないなと。時代は感じつつ、エバーグリーンなものを目指したいと思いますね。なので基準は自分、責任も自分ということになりますね。そういう意味で僕は、音楽趣味人の大仙人のような大滝さんと早いうちにやれたことがよかったと思っているんです」
今振り返る80年代の音楽の魔法
杉さんは当時自分がシティポップを作っていると自覚をしていたのだろうか。そして今はどうなのだろうか。当時を思い起こせば、シティポップという言葉は一般的ではなく、自作自演の音楽はすべてニューミュージックとして括られていたように記憶している。
「全然自覚がなくて、今もまるで他人事のような感じなんです。70年代後半から80年代前半にシティポップをやっていた人は皆、売れるとか注目されるとか、そういうことを考えていた人はいなかったんじゃないですかね。僕も数字とか、よこしまなことは考えずに、すべてのエネルギーを音楽に注いでいたんです。まわりからは、『君たちみたいな音楽は売れない』と言われたし、自分も売れるとは思っていなかった。これは、皆同じだったんじゃないかな」
それでも杉さんのレコードは売れた部類に入る。名盤『スターゲイザー』『ミストーン』は当時のチャートでトップ10にランクされているし、先述の「NOBODY」「バカンスはいつも雨」など今も歌い継がれている名曲は多い。でもこのムーブメントで大量の隠れた名盤が注目を集め、再評価されたりして思うのは、杉さんの言うとおり、“売れる、売りたい”と言う意識が希薄であるレコードが多いことだ。なんでこのレコードが出ていたのか、と首をかしげたくなることも少なくない。
「日本の経済や景気の影響もあったのでしょうが、80年代は若い人たちの音楽への接し方が大きく変わった時代でした。ウォークマンやラジカセが出てきて、音楽の聴き方に突然変異が起こって、それによって空気感が変わったと言うのか、音楽を聴く人のすそ野が広がって、僕らみたいなマイノリティな音楽を聴いてくれる人が増えた感じがしました」
音楽需要が拡大し、音楽が一気に産業化した80年代。その頃の杉さんの活動を振り返ると、ほぼ一年に一枚のペースでオリジナルアルバムを作るほか、ツアーを行い、先述のNIAGARA TRIANGLE Vol.2への参加や、松田聖子など他人への楽曲提供、さらには松任谷由実、須藤薫とのジョイントコンサートや松尾清憲とのバンド、BOXなど活動が多岐にわたる。その原動力はなんだったのだろうか。
「忙しいのが楽しいんですよね。しかも、当時のことは全部覚えています。去年、人に書いた曲だけを集めたCDを出したんですが、気づいたら300曲も書いていたんですね。僕は曲を書くたびに、これが最後の曲になってもいい、これが自分の最高傑作だ、という思いを込めているんです。自分の作った曲すべてに恋をしている、そう思っていないと曲は作れないですよ。あとは、人と共同作業できるのが音楽の良さだと思っているんです。文学や絵画では共同作業はできませんよね。音楽はいろいろな人と関われるから、逆にその人たちから自分の行きたいところを教えてもらう。自分らしさに気付ける近道だと思っています。みんなと音楽をやるのが純粋に好きなんです」
シティポップ・スタジオLIVEへの思い

今回の「シティポップ・スタジオLIVE」もまさにみんなと音楽をやる楽しさが味わえるイベントになりそうだ。いろいろなアーティストが参加して当時のシティポップを披露し、色鮮やかで、明るく華やかだった80年代を思い出すことができるのだろう。
「先程の話で言えば、ラーメン博物館みたいなもので(笑)、シティポップのおいしいところが観られて聞けるイベントになると思います。僕は単なる出演者なので、選曲はシティポップが好きな人に任せているんですが、それがおもしろい。僕は今回、『君は天然色』を歌わせてもらいます。自分が歌うのはおこがましいとは思うけど、普通にみんなが『君は天然色』を聞いて楽しんでくれるなら大滝さんは喜ぶかなと思って。大滝さんはもうこの世にはいないわけだから生では聞けないわけですよね。まぁ、生きていたとしても歌わないと思うけど。でも大滝さんが残した名曲を神棚に飾っておくのは、惜しいじゃないですか。僕らは新鮮な気持ちで演奏しますので、皆さんも新鮮な気持ちで聴いてもらえると嬉しいです」

【公演概要】
シティポップ・スタジオLIVE
公演日:2月12日
会場:神奈川県民ホール 大ホール
出演者:(※50音順)
安部恭弘/EPO/黒沢薫(ゴスペラーズ)/桑江知子/小比類巻かほる/杉真理/鈴木雄大/土岐麻子/濱田金吾/一十三十一/松尾一彦(ex.オフコース)/マリーン/山本達彦/芳野藤丸(SHOGUN)
※未就学児入場不可
【チケット取り扱い】一般発売日:12月1日(金)10:00
キョードー東京 0570-550-799
オペレータ受付時間 平日11:00~18:00 土日祝日10:00~18:00
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)