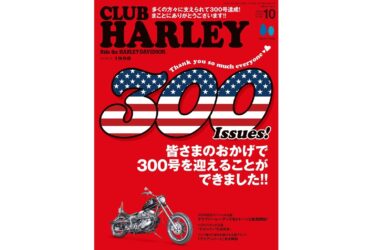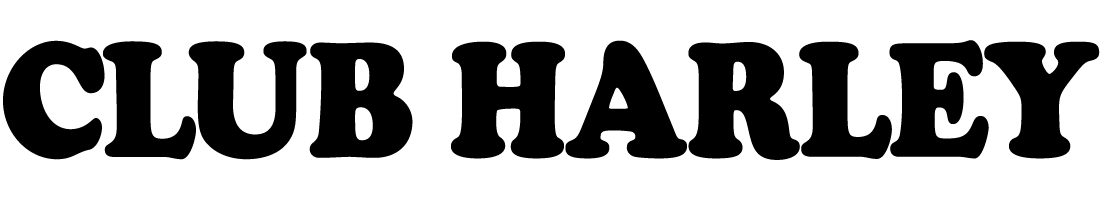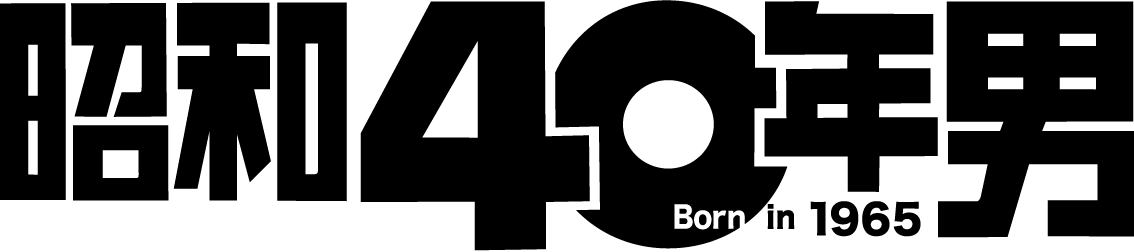前回流用のように見えますが、あくまでも新規撮影デス!
モノクロページ(誌面ではモノクロ)にも関わらず毎度、毎度、ペイントネタを繰り返している当コーナーですが、今回も相も変わらず同じような内容の展開。まるでドラマの『古畑任三郎』のオープニングの如くワンパターンなコトになっているゆえ、ともすれば手抜きに思われてしまうかもしれないが、実は西川きよしの選挙時の演説の如く「小さなことからコツコツと」サボらずシッカリと作業を行っていることを、まずは最初のイイワケとして、ここに記しておきたいと思う。
このコーナーを担当するワタクシ、不肖マコナベの記憶を辿ったところ2024年の9月号から八王子の「グランツ」さんにレッドショベルのフレームを持ち込み、この作業を行っているが、もとのペイントを残しつつ、少しづつ修復していく工程はズバリ言ってかな~り地味。まずはクレーター状に深くキズがついた箇所は筆で塗料を乗っけるようにタッチアップし、細かいキズはエアブラシで修復し──というコトを、これまでもイヤというホドにサンザンお伝えしてきたのだが今回、またしてもコイツを繰り返す地獄にハマっているのが現状なんである。
その状況をば説明すると「タッチアップをする→乾くまで待つ→ぼっこりと膨らんだ箇所をペーパーがけする→またペイントがハゲる→そこをまたエアブラシで修復する」という工程を延々と繰り返しているのだが、マジでコレが無限地獄。決してサボっているつもりはないのだが、ループで繰り返すこの作業は、まるで映画の『猿の惑星』をシリーズで観賞したときに起こるような現象であり、『続・猿の惑星』から『新・猿の惑星』、そして『猿の惑星・征服』から『後の猿の惑星』までをイッキ観すると、結局は最終作のオチからストーリーが続く最初の『猿の惑星』へと戻って観たくなる(もちろん1968~1973年に公開されたオリジナル版)という感情と似たようなモンかもしれない。
まぁ、こうしてクダラナイ比喩を書いているコトからもお察しのとおり、今回も同じような作業が続いたゆえ、ストーリー上、まったく進展がナイっていうのも正直なところなんであるが、やはりボチボチ妥協点を見つけなければ、先程の説明どおりのペイント地獄が延々と続き、貴重なページで同じような内容を繰り返すことは必至。もういいかげん読者のミナサンからダンプ松本バリのブーイングを浴びそうなので、そろそろ妥協して次に進みたいとも思う。
で、今回は無理矢理に各部のピンストライプを修復するという工程に作業をススメてみたのだが、サスガにこのピンストライプというヤツはワタクシのようなシロウトには難しいので、今回はグランツの中島パイセンに作業を丸投げ。オーブンに調理途中の料理をほおりこんだら、次のカットでは既にできあがっている『グラハム・カーの世界の料理ショー(1974~1979年まで東京12チャンネルで放映)』のようなスタイルで、時短で作業したんであるが、グラハム・カーの如くスタッフのスティーブと他愛のない下ネタトークをしつつ、ワイングラスを傾けていたらホドなく料理が完成、というのがワタクシがこの先に思い描く理想のプランである。
で、今回はグランツの中島パイセンに残りのピンスト作業を託し、ワタクシめはグラハム・カーが「溶かしバターをパイ生地に塗ったくる」かの如く、再びフレームにペタペタとタッチアップを施し、八王子を後にしたのだが、次回こそ、またタッチアップの気に入らない箇所を発見してペーパーがけをし、そこをまた修復して──というコトを繰り返さないよう注意たいところである。はい。



ホコリをカブったフレームを磨き、タッチアップでボコついた箇所をペーパーがけし、ブライト(コンパウンド)でまた磨きという罰ゲームに等しい作業を今回も繰り返すハメに……タンクやフェンダーなどが取り付けられる箇所は、往年のオチアイ選手の如く、それなりに手抜きしてもいいのだが、意外とマジメな性格なのです。

モノクロ写真(誌面ではモノクロ)ではわかりづらいかもしれないが、ゴシゴシとペーパーがけした結果、またしても白っちゃけてしまったメインフレーム。こうした作業の繰り返しは、まじで地獄ッス。

フレームのタッチアップ箇所をムキーっとペーパーがけしたところ見事にペイントがブラマヨ小杉の頭皮の如くハゲあがり、ご覧の状態に。こうした箇所は再びエアブラシで修復するのだが、マジで作業の終わりが見えません。
- 1
- 2
関連する記事
-
- 2025.09.10
シートの張り替えが完了して愛車の満足度が爆上がり中!!
-
- 2025.07.22
古着をリペア! デニムパンツの裾上げ方法を伝授!【ふるぎ道】
-
- 2025.06.25
古着をリペア! Tシャツの裾上げの方法を伝授!【ふるぎ道】
-
- 2025.06.11
古着をリペア! シャツの襟の修理の方法を伝授!【ふるぎ道】
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)