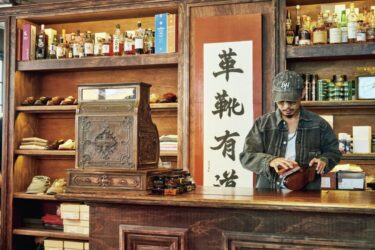FMは一人でこっそり聴く“密かな楽しみ”でした
TOKYO FMで18年にもわたって放送中の人気長寿番組『NISSAN あ、安部礼司〜beyond the average〜』(以下、『安部礼司』)は、「FMらしくない番組」とも言われている。タイトルロールの安部礼司を演じる俳優・小林タカ鹿は、FMにどのようなイメージをもっていたのだろうか。お笑いが好きなテレビっ子だった小学生時代を経て、十代の頃はスポーツに打ち込んでいた小林。ラジオ体験はAMから始まった。
「ラジオを聴き始めたのは十代の頃です。よく聴いていたのは、岸谷五朗さんの『東京RADIO CLUB』(TBSラジオ)。1回だけはがきを出して、読まれたこともあります。確か“夏休みの失敗談”というお題で、どんな内容だったかは覚えていないのですが、プールの招待券をプレゼントしてもらえるはずが番組のステッカーしか届かなくて憤慨したことは覚えています(笑)。その前にやっていた三宅裕司さんの『ヤングパラダイス』(ニッポン放送)もちょこちょこ聴いていました」
小林がFMを聴くようになったのは、もう少し後のこと。
「NHK-FMで森高千里さんの『ミュージック・スクエア』を聴いていました」
90年から始まった『ミュージック・スクエア』は、桑田佳祐、布袋寅泰、中島みゆきらの豪華アーティストが日替わりでパーソナリティを務めた音楽番組。森高千里は永井真理子の後を継いで、水曜パーソナリティを93年から2年間担当した。すでに人気者だった森高だが、この番組が小林の友人たちの間で話題になることはなかったという。
「学校でラジオの話題が出ることはほとんどありませんでした。やっぱりラジオは個人の楽しみだった気がします。テレビとは違って、『俺はこれを聴いているんだ』という感じの、密かな楽しみでした。FMの森高さんの番組も、みんなに内緒で聴いている気持ちになっていて(笑)。『森高さんが好き』と公言しているわけでもないのに、こっそり『いいな』と思いながら聴いている感覚がありました」
FMは“密かな楽しみ”だったと小林は言う。それはFMのもっている独特な雰囲気によるものだった。
「特にNHK-FMはBGMのない時間が多くて、ひっそりしているんですよね。AMの『盛り上げるぞー!』という感じじゃなくて、『個人的にお話を聞かせてもらってます』という感じなのがよかったですね。FMは、それを求めて聴いていたかもしれませんね」
AMが庶民の世界なら、FMは浮世離れした世界
やがて大学に入学して演劇を始めた小林は、芝居の合間にコントをやろうと思いつく。その時、コントのベースになったのがFMだった。
「音だけのコントを作りたいと思ってMDなんかに録音していたのですが、コントのベースになるものとしてFMのDJを考えついたんです。FMって、ちょっと浮世離れしている感じがあると思っていて。普段、あんなにいい声でしゃべる人はいないじゃないですか(笑)」
“More Music Less Talk”(トークよりもよりたくさんの音楽を)路線を打ち出したJ-WAVEの放送が始まったのが88年のこと。音楽に特化した番組編成とバイリンガルのDJ(ナビゲーター)による心地よいトークによって大人気を博した。ただし、「全く音楽に興味がなかった」という小林にとっては、ちょっと不思議な世界だった。
「FMのイメージってスマートですよね。ある意味、カッコつけたところの裏側にあるものの笑いが好きでした。“カッコつけてるものっておもしろいよね”という感じです。AMが庶民の世界だとすると、FMは異世界。洋楽がかかっているし、いい声でしゃべっている人がいる。カッコよくて、浮世離れしている世界だな、と。決してバカにしているのではなく、自分にはなじみのない、少しおもしろい世界だという感じの距離感で見ていました。だから、“FMってコントになるな”と思ったんです。バッキー木場さんのパロディで『ナビゲーターのバッキー小林です』なんて言って、コントのナビゲートをしていましたね(笑)」
ちょっと美意識がズレていておもしろい。それが当時の小林のFMに対するイメージだった。
「特定の番組とかパーソナリティというより、ざっくりとした“FMってこうだよね”という先入観やイメージです。偏見ですよね(笑)。その頃のFM界独特の雰囲気を勝手に独断と偏見でイジってたんです。その発想はあまり変わっていなくて、何年か前にWANTEDという二人組でコントをしていた時もDJがはがきを読んでコントに入るというフォーマットでやっていました」
確かに90年代初頭までのFMはどこかエレガントで浮世離れした雰囲気をまとっていた。俳優の細川俊之がパーソナリティを務めた『ワールド・オブ・エレガンス』(FM東京)はその最たるものだ。
「そういえば、細川俊之さんは同じ大学のずっと先輩なんですよ。現役の頃、演劇部のOB会にいらっしゃった時にお話を聞かせていただいたことがあります。細川さんはとてもしっとりした雰囲気の方なんですけど、お会いしてもそういう感じで『貧乏な学生の頃、ラーメンしか食べるものがなくても、とても上品に食べていた。人の雰囲気を作るのは物じゃなくてマインドなんだ』というお話をされていました。一度、番組を聴いてみたかったですね」
ラジオドラマとの出会いと『安部礼司』スタート
演劇を始めてから身近になった存在が、FMで放送されていたラジオドラマだった。ラジオ放送が始まった頃から多くの人に親しまれていたラジオドラマだったが、この頃は本数を減らしていた。小林が最初に触れたラジオドラマは『青春アドベンチャー』(NHK-FM)である。
「大学で演劇を始めた頃、聴き始めたラジオドラマだったと思います。『ラジオでドラマをやってるんだ!』という新鮮さがありました」
NHK-FMでは当時、帯番組の『青春アドベンチャー』と一話完結の『FMシアター』が放送されていたが、小林はどちらにも出演するようになる。『青春アドベンチャー』ではポール・オースター原作のファンタジーもの「ザ・ワンダーボーイ」(02年)に出演した後、地底世界を舞台にした「スウィート・アンダーグラウンド」(02年)に主演。『FMシアター』でも倉持裕作のコメディ『遠い隣人』(03年)など3本の作品に出演している。その後、ラジオドラマの世界に新風を吹き込んだ『安部礼司』へと連なっていく。
「(ラジオドラマからの)影響はあったと思います。今でも演劇をやっている時のベースにある考え方は、『舞台は声と身体を見せているもの』です。どんな名優でもセリフが聞き取れなかったら、舞台ではなんの意味もありません。劇場のいちばん奥のお客さんにセリフが届かなければいけないんです。僕にとって、声がお客さんに何かをイメージさせたり、シーンや感情を伝えたりするのに、ラジオドラマでの経験が活かされていると思いますね」
『安部礼司』がTOKYO FMでスタートしたのは06年4月。当初、小林はFMであることを意識しなかったという。
「“こういうことをFMでやるんだか”とは思いましたが、『FMだからこう演じよう』とは全く考えませんでした。演出的にも『FMだからこうしてくれ』とは言われなかったので、すんなりと入れましたね」
『安部礼司』の中心になっているのは、身近な話題をもとにしたラジオドラマと、ちょっと懐かしい今さらツボな選曲。どちらも“浮世離れ”していたかつてのFMのイメージとは、全く異なるものだ。
「『FMらしくない』という反響を直接聞いたわけではありませんが、聴いている人たちがそういう感覚があるのはすごくわかりました。番組をやっていくなかで『やっぱりFMにこんなのはなかったよな』とじわじわ思うようになっていきましたね。当時はラジオドラマが少なかった時期だったので、それも新鮮に感じてもらえたかもしれませんね」
近年、AMとFMの境目がどんどんなくなっている。80年代後半は音楽を多くという傾向があったFMだが、90年代半ばにはトークを重視するようになった。10年にradikoが登場してからは、多くの人がAMとFMの分け隔てなく、聴きたい番組を選ぶようになった。そのような流れを小林は肌で感じているという。
「今は『AMだから』『FMだから』ということはなくなっていると思います。全部まとめて『ラジオ』という受け入れられ方になっているのではないでしょうか。どちらもおもしろいものを作ろうとする気持ちは同じだと思います。僕自身もAMとFMの境目が昔より気にならなくなってきました」
親近感があって浮世離れしていないけど、どこかスマートさが感じられる。かつて昭和50年生まれ世代が抱いていたAMとFMのイメージのちょうど境目にあるのが『安部礼司』なのかもしれない。
「『安部礼司』はちょうどいいところにいるのかもしれないですね。安部礼司は、全く浮世離れしていなくて、すごく身近な存在です。昔のアイドルは浮世離れしていたけど最近のアイドルが身近な存在になったように、きっと浮世離れしていたFMも身近な存在になってきたんですね。その過程のなかで『安部礼司』が生まれたんだと思います」
長寿番組を飽きずに続けられる秘訣
『安部礼司』では、お客さんを入れた番組イベントや公開録音を大切にしている。コロナ禍によって久しくイベントが開催できなかったが、今年7月に4年ぶりの公開録音を神戸で開催した。珍しいラジオドラマのイベントながら、この日も多くのファンが来場した。
「もともと舞台出身なので、お客さんの前で何かやりたくてイベントをやっているところがあります。やっぱり顔が見えるお客さんがいるのは安心感がありますね。『安部礼司』のイベントでは、リアルに僕がひとつぐらいミスをするのですが、この前も段取りを一つ忘れてしまいました(笑)。『さすが安部、やってくれるな』と思ったのですが、それを目の前のお客さんが喜んでくれるのがありがたいですね。安部礼司の失敗を受け入れてくれるお客さんがいるうれしさをあらためて感じました」
いまや長寿番組となった『安部礼司』だが、長く一緒に時間を共有してきたリスナーと共に価値を作り出してきたと小林は語る。
「長く続けた歴史があるので、リスナーと一緒にいろいろな時代を乗り越えてきた感じがします。それこそリーマンショックとか3.11とか、いろいろありましたからね。ラジオの聴かれ方も変わっていったと思います。そんななかで、いつも同じことを続けてきた『安部礼司』の価値というものも出てきたのではないでしょうか」
ファンの顔が見えているからこそ、大切にしたいという気持ちが強くなる。
「イベントなどで顔が見えるお客さんたちを笑わせたいし、楽しませたい。今までどおりのことを、新鮮に、あの人たちを楽しませるために、続けていきたいという気持ちが強くありますし、それが届けばいいなと思います。とにかく聴いている人が飽きずに聴いてくれている以上、こちらも飽きずにやり続けることが大事。今も全く飽きていないんですけどね」
小林に“飽きずに続けられる秘訣”をたずねてみたところ、“心のもち方”だと答えてくれた。
「『安部礼司』はすごく日常的なことをやっているのですが、日常と一緒で、毎日は同じようで同じではないんですよね。『毎日同じだなぁ』と思えばそう見えてしまうし、『毎日似てるけど何か違う。そこから何か学ぼう』と思えば新しい経験になっていくでしょう。『五十嵐物産と何回揉めてるんだよ』とも思うんですけど(笑)」
安部礼司は同じ失敗を繰り返してしまう男ではあるが、アラフィフになっても成長しようとしている。そこが大きいんじゃないかと小林は言う。
「昨日たまたま知ったイチローさんの『精神的な脂肪はなかなかとれない』という言葉に感動したんです。スポーツ選手は現役を退くと身体に脂肪がついてしまいますが、それと同じで、偉くなったり、周りに持ち上げられたりして、それを受け入れてしまうと精神に脂肪がついて、もう成長はないんだと。安部礼司は現役を全く降りていないんですね。上手くいかないから、成長しようとして悪戦苦闘している。だけど、やめようとはしていないんです。僕自身もそうあろうと思って、向かい合っています。だから飽きずにできるんでしょうね」
安部礼司と小林タカ鹿は全く別人のはずなのに、どこか重なって見えて(聴こえて)しまうのは、こんな共通点があるからなのかもしれない。だからこそ、リスナーは応援したいと思うのだろう。
「安部礼司みたいに悪戦苦闘するのが人生ですよね。それを聴いて『なんかがんばってるな』『オレと同じだな』と思って応援してくれる人が多いんだと思います。そういう悪戦苦闘をこれからも続けていきたいと思います」
青春アドベンチャー(NHK-FM /月~金曜21:30 ~21:45)
1992年から開始したラジオドラマ番組。一日15分の帯番組で、大作は数週間に及ぶことがある。タイトルからもわかるように、若い世代に向けて幅の広いジャンルでエンターテイメント性の高い作品を放送してきた。吉田秋生原作の『BANANA FISH』、あさのあつこ原作の『バッテリー』、上橋奈穂子原作の『精霊の守り人』など、この番組で最も早くドラマ化している作品は数多い。
『青春アドベンチャー』公式サイト https://www.nhk.jp/p/rs/X4X6N1XG8Z/
『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』(TOKYO FM /JFN全国38局ネット/毎週日曜日17:00~17:55)
ごくごく平均的なサラリーマン・安部礼司の会社や家庭を舞台とするコメディタッチのラジオドラマ。劇中に流れる、1980年代以降にヒットした今さらツボな楽曲も人気。定期的にイベントを開催し、2015年には会場となった日本武道館に8000人ものリスナーを集めた。

(出典/「昭和50年男 2023年11月号 Vol.025」)
取材・文:大山くまお 撮影:松蔭浩之
関連する記事
-
- 2026.01.07
「GLAD HAND」の創設者が昨年スタートさせたアメリカンクラシックなブランドに注目
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)