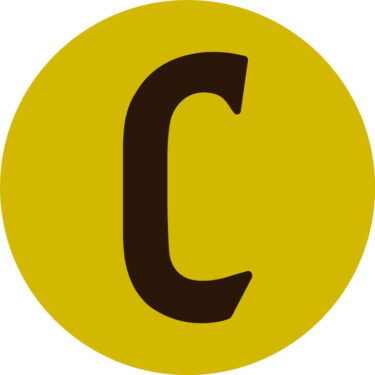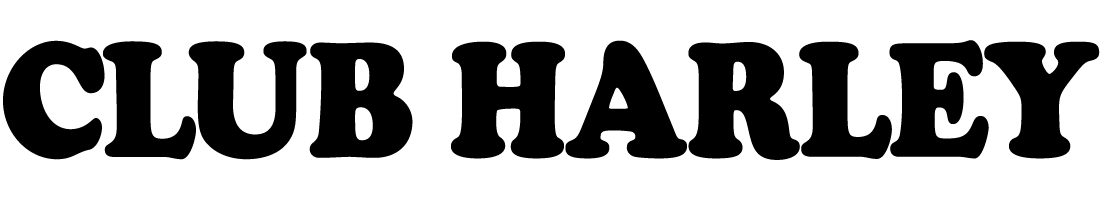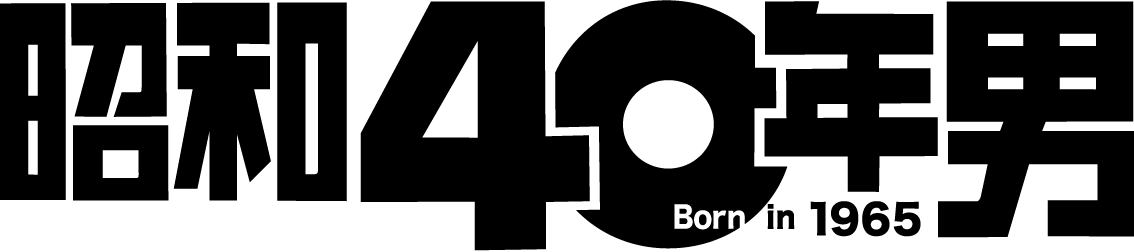発見されたポールのバイオリンベースの謎

竹部:最近の森川さんのブログで、盗まれたポールのバイオリンベースの謎について書かれていました。このカールヘフナー500/1の61年モデルについて、森川さんはずっと前から言及されていましたよね。
森川:デビュー当時のビートルズサウンドを知るうえでも最も貴重なビートルズアイテムですから、あのベースはどこにあるうだろう、誰のもとでひっそり眠っているのだろう、って考えながら、無事であること祈っていましたよ。
竹部:最初にこの話を聞いたとき、本当なのかって思いましたが。
森川:あれだけ長いこと行方不明になっていたのに、プロジェクトが立ち上がったらあっけなく出てきたでしょ。最初は僕も信じられなかった。
竹部:盗難時と比べるとベースの状態はどうなんでしょうか。
森川:ブリッジの位置がおかしいって言う人がいるけど、あのベースのブリッジは固定されてないから弦を緩めたら簡単に外れちゃうんですよ。だから位置がズレただけなんじゃないのかな?あとサイドバックの傷もマニアの間で問題になってるみたいだけど50年以上放置された状態だったらしいから、湿気と乾燥を繰り返し経年劣化が進んで元の状態からは大きく変化してるはず。写真だけではウェザーチェックとか判断難しいと思います。
竹部:初期はライブもレコーディングもあのベース1本で弾いていたんですよね。
森川:そうですね。「シー・ラブズ・ユー」のレコーディングあたりまで使っていたとか。あの1本目のベースはピックアップの取り付けがよくなかったのかな?フロントのピックアップをテープで固定している写真を見たことがあります。63年秋頃にモデルチェンジした2本目を手に入れ、それ以降1本目の方はステージ上でスペア・ベースとしてアンプ周辺にセットされてはいたものの使用されることはなかったと思います。その後、65年頃に大がかりな修理が施されピックアップの箇所はマウントをつけて固定、塗装もやり直されていました。66年の武道館のバックステージの写真でこのベースは確認できます。つまり日本にも持って来ていたんですね。その後「レボリューション」のPVで登場した時はピックガードも外されていましたね。69年に『ヤング720』でそのPVが公開された際、そのベースがブラウン管の中に再び登場した時の感動は今でも覚えてます。それ以降は映画『レット・イット・ビー』、つまり「ゲット・バック・セッション」で使ったのを最後に見かけることがなかったから、気になっていたんですよ。
竹部:「ループトップ・セッション」ではBASSMANのシールが付いたやつを使っていますよね。
森川:だからそのあたりで500/1の61年モデルは失くなっていたんじゃないかと思ってました。
竹部:今回のニュースによれば、72年にウイングスのツアーバスから盗まれたという。
森川:そのニュースが事実だとしたら、盗んだ人もそれがウイングスのバンだと思わなかったんじゃないかな。しかも、ビートルズに興味がなくて、よくわからなかったから、知り合いのパブの家主に安値で売ったのではないかな。
竹部:犯人はすでに亡くなっていて、息子が名乗り出たんですよね。
森川:そして犯人からベースを譲り受けたロン・ゲストというパブの家主から彼の息子たちに引き継がれ、その家の屋根裏に人知れず忘れられたかのように放置されていたという……。
竹部:ロン・ゲストの孫がTwitterで写真をアップして一気に拡散していきました。事件の奇妙さと、50年という年月を感じますね。
森川:やはりあれが本物だと思うのは、60年代の初めって、レフトハンド仕様のギターってほとんどないんですよ。ギブソンやフェンダーでさえオーダー以外は製作していなかったんじゃないですかね。最初の頃、ポールは通常の右利きのギターを逆にして弾いていたというでしょ。それで61年にハンブルグの楽器屋でシンメトリックなフォルムのホフナーバイオリンベースを見つけて左利き用をオーダーしたらしい。そう考えるとやっぱりあれはポールのために作られた唯一無二のベースだと思う。 昨年12月にポールに返却されて、その後、鑑定にホフナー社が約2か月費やしたということだけど、ポール本人も本物ならば正式にコメントしてほしいよね。というか、ポールにはホフナーベースをハンブルグで手に入れた過程や経緯をもっと明確に語ってほしい。ホフナーベースとジョンのリッケンバッカー325は今も昔もビートルズ少年にとっては憧れのギターですから。

最後の新曲「ナウ・アンド・ゼン」に思うこと
竹部:そうですね。本人があのベースでプレイする姿をインスタにあげてほしい。このように、ビートルズは話題に事欠きませんね。
森川:ビートルズのニュースって、やっぱり嬉しいですよ。「ナウ・アンド・ゼン」も嬉しかったし。僕は「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」の続きみたいな感じで聴きましたけど。
竹部:「ナウ・アンド・ゼン」の95年バージョンって聴きました?僕はブートで聴きましたけど、あれを今回のバージョンに作り直したのは、いろいろな意味ですごいなって思いました。
森川:「ナウ・アンド・ゼン」を作り直したのは、ポールとリンゴがやり残したことがあると思ったからなんだろうね。あの曲でジョンが”恋しい、つまり I Miss You ”と歌っているのはヨーコのことだと思うけど、ポールは自分たち(ザ・ビートルズ)に向けたジョンからのメッセージと言うコンセプトで仕上げたかったんだろうね。
竹部:それが美しい気がします。
森川:だから、サビのところの歌詞を抜いたんだと思う。不完全だったし、95年ヴァージョンのサビには “♪Abuse You……Confuse you”って歌ってる箇所がある。「ジェラス・ガイ」なんかもそうだけど、結構ジョンは言葉上でのことなのかもしれないけど粗暴な面というか暴力的なところがあるよね。で、「AISUMASEN」じゃないけど謝ったり反省したりね。映画『NOWHERE BOY』でポールを殴るシーンがあるじゃないですか。そのシーンについてポールが「僕はジョンに殴られたことなんて一度もない」ってコメントを出してたくらいだから、あの“Abuse You”ってフレーズが入っている未完の歌詞の部分は省きたかったんじゃないのかな。
竹部:本来はヨーコへのラブソングですよね。
森川:でもヨーコさんには申しわけないけどビートルズのラストソングっていう風に考えるだけでワクワクするじゃない。
竹部:出来すぎというか、美しすぎますけどね。
森川:『アンソロジー』の時にリンゴが言うじゃないですか。「僕らはお互いを愛しみ、思いやっていた。嘘みたいに仲が良かったんだ。僕らは心から愛し合っていた。ほんとにビートルズは素晴らしかった」って。まさにそれを物語っていますよ。4人のイーブンな関係というか。僕は「ナウ・アンド・ゼン」をそういうふうに受け取りたい。勝手にそう思って聴いてます。

『ハード・デイズ・ナイト』から始まったビートルズ人生
竹部:その『アンソロジー』プロジェクトで、元ビートルズの3人は初めて公式に過去を振り返ったわけですが、その時の彼らの年齢って50代半ば。僕もその年齢になったので、それにあやかって自分のビートルズ史を振り返ってみようと思って始めたのが、この連載なんですね。「ビートルズのことを考えない日は一日もなかった」というタイトルは、以前森川さんが僕に言った言葉なんですが、勝手に拝借してしまいました。
森川:そうでしたか(笑)。別にいいですよ。僕は相変わらずそうですし。時間が空いたら、YouTubeでビートルズの映像や話題を検索したりしているし。キャパが狭いともいえるんだけど、僕にはそれしかないんですよ。誤解を招いちゃうかもしれないけど、自分がこういう仕事をしていて、その血となり肉となっているのは、やっぱりビートルズ。
竹部:それを詰めていくと、来日公演を観た66年7月1日ってことなんでしょうか。
森川:その2年前の64年、僕が小学校6年のときに初めてビートルズを知った頃から始まっていたんだと思う。それまで僕が聴いていたものはテレビで日本人が歌っている歌謡曲やアメリカンポップスのカバーものばかりでした。小学校5年生くらいになるとラジオで洋楽を聴き始めていました。今で言うオールディーズ。ビートルズの登場はなんだか違和感があり、少し奇妙に響きました。今までのものとは明らかに違っていたし。ところが、気がつけばいつの間にかビートルズに夢中になっていた。決定的だったのは、あれだと思う。64年の冬休みに池袋で観た『ハード・デイズ・ナイト』。あれを観た日。あんな衝撃はなかったんですよ。
竹部:僕も同じです。映画『ハード・デイズ・ナイト』なんです。1980年にフィルムコンサートで観た。
森川:映画が始まって、すぐに3人が転ぶでしょ。あれに驚いた。まず『ハード・デイズ・ナイト』を1回観て、同時上映だった『踊れサーフィン』を観て。そんな映画は観たくなかったけど(笑)、もう一度ビートルズを観たいから我慢して、最終上映を観て家に帰ってきたら親に怒られた。家に帰る途中で考えていたのが「ビートルズで誰が好きなんだろう?」っていうこと。ジョンかな、ジョージかな。ボールかリンゴかなって。それでわかったんだけど、 あの4人が好きなんだなと思って。4人が好きっていうか、4人に魅力を感じたんだよね。僕もあんな仲間がいたらいいなぁとか。あんな思いや何かに虜になってしまうような体験はそれまでなかったから。まだ12歳の子供でしたし、なかなかその気持ちを言葉に出来なかった。
竹部:わかります。4人のキャラ込みのルックス。
森川:そう、ルックスは大きかった。『ハード・デイズ・ナイト』を最初に観たとき、ビートルズの曲をまだ全部は知らなかったわけですよ。ラジオで聞いたことのある曲はいくつか知ってたけど、僕が持っていたレコードは誕生日に叔母から買ってもらった「プリーズ・ミスター・ポストマン」、そして電気屋の友人がいて、そいつがくれた「シー・ラブズ・ユー」のシングル。東芝のセールスマンが持って来てくれたもの。その後、ステレオコンパクト盤の『ハード・デイズ・ナイト』そしてもう1枚出ていたコンパクト盤、「抱きしめたい」や「ツイスト&シャウト」「プリーズ・プリーズ・ミー」「シー・ラブズ・ユー」が入っているものを親に買ってもらってた。それで年明け2月に『ビートルズ・フォー・セール』を買ったんですよ、お年玉で。LPは1枚も持っていなかったから、何を買おうか迷ったけど、いちばん新しいアルバムの『フォー・セール』を選んだ。前後しますが65年になるとどんどん情報が入ってきました。2月にはテレビで『エド・サリバン・ショー』がオンエアされたし。それで「オール・マイ・ラヴィング」「アイ・ソウ・ハー・スタンディグ・ゼア」とかを聴いて覚えていった感じです。
竹部:その放送では「ティル・ゼア・ワズ・ユー」に邦題が付いていたって話ですよね。「君が来るまで」。森川さんの証言として、大村亨さんの著書『ビートルズと日本 熱狂の記録』に書かれています。『ハード・デイズ・ナイト』は、好奇心で観に行きたくなったっていうことなんですか。
森川:森永のチョコレートのテレビCMで映画のワンシーンが使われていて、それで興味をもったんですよ。あと、その前、64年の夏前頃かな?『高橋圭三ショー』ってバラエティ番組があって、で「海外でビートルズがすごい人気」っていうような特集をやったんです。その時に初めて動くビートルズを見ているんです。それまでラジオと写真でしかビートルズについては知らなかったんだけだったけど、なんか動くヴィジュアルに魅かれたのかな。ビートルズにもだけど女の子たちの大騒ぎを見てびっくりしたんだよね。『ハード・デイズ・ナイト』の宣伝番組みたいなものだったと僕はずっと思っていたんだけど、大村さんの本を読んだら、使用されてた映像は『カム・トゥ・タウン』だったみたい。つまりあれはABCシネママンチェスターコンサートの映像だったんですね。
竹部:チョコレートのCMというのは「ストロングチョコ」って製品ですね。
森川:今で言う映画とのタイアップだったんだろうね。「ストロングチョコ」のCMは『ハード・デイズ・ナイト』のスカラシアターでの「恋する二人」のシーン。ジョージのあのギター弾いてる時のステップがなんだかやたらカッコ良くて、訳もわからず放課後にホウキを持って真似してました。早く映画が観たいって思ってました。ちなみに僕がビートルズ4人の名前と顔が一致したのは夏休みです。夏休みに入って、従兄の家にあった『スクリーン』って雑誌に映画が紹介されていて、リンゴの名前は知ってたけど、その雑誌で初めて4人全員の名前を覚えた。でもまだポールが左利きなんてことに気づいていなかった。ギターなんて触ったこともなかったしね。それで、『ハード・デイズ・ナイト』を観て、ポールのベースの持ち方が違うって思ったの。映画は確か夏に封切られたはず。で、僕が観たのが冬休みに入る日。だから半年くらいロングラン上映だったのかな?いずれにせよ、あのときにすべてが始まった気がするんです。
『ヤング720』で観たアマチュア時代の清志郎
竹部:ちょうど60年前ですか。
森川:そう、60年前。1964年東京オリンピックがあった年。あれから60年間、毎日ビートルズのことを考えているということになる(笑)。
竹部:還暦ですね(笑)。音楽を仕事にしたいっていうのもその頃から思っていたんですか。自分もビートルズになりたいと。
森川:ビートルズは自分たちで曲を書いているということにも驚いたわけ。職業作詞・作曲家がいなくても曲は作れるのかと思った。そういうことをやり始めたのは 中学2年になる頃かな。中古のギター買ってたし。ビートルズが日本に来るかもしれないっていう噂が出始めた春先、ブラスバンド部だったから日曜日とか学校にギターを持って行ったりしてた。普段の日は教師がうるさかったしね。ギターなんてとんでもないって。
竹部:バンドを組んで早い時期にテレビのオーディションにも出られているんですよね。
森川:『ヤング720』のアマチュアバンドコーナー。そこで清志郎に会ってるんですよ。彼らと一緒に僕らも合格したはずなのに僕らにはお呼びが来なかった。それは69年のこと。そのあと渋谷公会堂でやった東芝主催のコンテストに清志郎たちが出たんですよ。ゲストが加藤和彦さん。そこで観た生のRCサクセションに驚いた。テレビで観たよりよっぽどすごいと思った。
竹部:そこでプロの壁を感じるわけですか?清志郎さんが森川さんの夢、ミュージシャンの道をあきらめさせたということ?
森川:あきらめるも何もそんなこと考えてもいなかった。どうやったらプロになれるのか?とか音楽で仕事なんてできるはずがないと思ってましたから。でも友人達とバンドみたいなものをやりつつオリジナルなんかも作ってました。その後僕らのバンドはRCの前座を2回やっているんですよ。武蔵野美術大学と明治大学の学園祭でした。71年と73年かな。RCはもうデビューしていて、ムサビでやったときは「僕の好きな先生」が出る前でした。 明治大学和泉祭の時は「僕の好きな先生」がヒットした1年後です。
竹部:のちに、深い関係となる清志郎さんとは不思議な縁ですよね。ビートルズで関係が深まったということはあったんですか。
森川:清志郎はオーティス・レディングとか、そういうソウルミュージックが好きだったけど、根底にビートルズはあったと思う。作る曲の中にも、「ここなんとなくビートルズっぽい」って感じる部分もあったし。意識しているわけじゃないけど、雰囲気を感じさせる曲はありましたよ。ちょっとコード進行が歪だったりハーモニーワークが似てたり。オリジナルメンバーの破廉ケンチが左利きのところとかね。
竹部:なるほど! 90年代初め、フジテレビの深夜に『OIOI PERSONAL COUNTDOWN Ten』っていう番組があったんですが、それに清志郎さんが出たとき、1位にビートルズを挙げていたんです。ちょっと意外な気もしたんです。
森川:そうなんですか。RC、そもそも清志郎はビートルズ好きだったと思いますよ。80年代中頃に「ワシントン・コロシアム」のビデオをコピーして彼の家に持って行ったんです。食い入るように観入ってましたよ。で、ジョンがステージで変なステップ踏むじゃないですか、あれを早速RCのステージで取り入れて客を煽ってました。

桜上水で買った海賊盤『Live At Atlanta Whiskey Flat』
竹部:それは新事実‼ ところで、僕が最初に森川さんと会ったのは97年なんです。『フレミング・パイ』っていうポールのアルバムが出たタイミング。それに絡めたポールの特集が『オリコン』であって、そこで僕がポールへの愛を託した文章を書いたんです。それを森川さんが読んでくれて、会社に電話をくれた。
森川:僕から連絡したんだよね。
竹部:はい。「オフィスオーガスタの森川さんっていう人から電話です」と言われて、「誰だろう?」と思って電話に出たら「君、ビートルズ好きなの?僕もビートルズ好きなんだよ。ちょっと君に会いたいんだけど」と言われて、次の日に六本木のオフィスまで来てくれたんです。
森川:僕から会いに行ったんだ? COILの音源を持って行った?竹部くんの文章を読んで確かCOILを聴いてほしいと思ったんだよね。
竹部:COILは98年デビューですからまだです。スガシカオさんが『ポップジャム』に出るという話をしてくれました。「黄金の月」が出たくらい。その時の森川さんは、デニムジャケットに派手なバッヂつけて、髪の毛は坊主に近かった。坊主時期のジョン・レノンみたいな(笑)。
森川:坊主だった?か。くせ毛がおさまらなくて坊主にしていた時期ありました。
竹部:怖い人なのかな、と思って話を聞いていたら、この人の名前、どっかで見たことあると思い出したんですよ。ジョン・レノンの追悼本『JOHN ONO YOKO』で原稿を書かれていた。それから、RCの『ラプソディー』の裏ジャケのライナーを書いたフランシス森川につながったんです。
森川:そうか、そうだった。COILのプロモーションで会ったような気がしていたけど、その前があるのか。でも竹部くんの書いたポールの考察文に驚いたんだと思いますよ。若い人なのによく知ってる、よく書けているなぁって。
竹部:そのとき初対面で3時間くらい話をしたと思うんです。その後は、まだメールがないんでたまに手紙が来て、手紙のやり取りをしました。覚えているのは、「ジョンの墓はどこにあるのか。ジョンの脳みそはどうなっているのか」みたいなことが書かれていたんです。
森川:杏子の「JOHNNY MOON DOGの行方に関する仮説」という曲をレコーディングしたときだ。
竹部:そんな手紙のやり取りをした後、頻繁にお会いするようになって、それからあれよあれよという間に、オフィスオーガスタが大きくなっていったんですよね。あれから気づくともう27年も時間が経っています。約30年!
森川:20年ってあっという間な気がするけど、30年って長いよ。本当に長い。偶然ロンドンで会ったこともあったよね。
竹部:同じ時期にロンドンにいたので、ホテルで落ち合ってインドカレーを食べました。やたら店内が暗いカレー屋で。懐かしいです。森川さんはプロデューサーとして多くのヒットを作っているわけですが、いろいろなアーティストや曲を手がけていくなかで、やっぱりビートルズからの影響というのは知らず知らずのうちに反映されていくわけですよね。
森川:いろんな曲に反映されていると思う。無意識で入っていたり、悪く言えばパクっているものもあるかもしれない。ビートルズを聴きこんでいない人しかわからないものもある。RCやってた頃、スタジオでなんかでアイデアを出したりすると「また、ビートルズかよ!」って清志郎に言われたり。
竹部:(笑)。そういえば、新しい『赤盤』『青盤』は聴かれました?
森川:まだ聴いてない。
竹部:かなり大胆にリミックスしていて、面白くなっているのはいいんですが、明らかに改ざんじゃないかと思うものもあって、それまで聴いてきたビートルズのレコードとは違う印象で、ジャイルズ・マーティンを信じていいのかどうなのか、って思わされる部分もあるんです。あれ?と思うポイントは挙げればきりがないのですが。今の話で言えば、ジャイルズって、どのくらいビートルズを聴きこんでいるのかなって思ってしまうんです。
森川:それはしょうがないかもしれないね。父親(ジョージ・マーティン)の仕事を引き継いでがやっているだけで、それが世界のビートルズだったという。でも60年代以降に生まれたビートルズファンって、僕からしたらほんとに聴き込んでいると思いますよ。僕も随分聴いているほうだけど。ビートルズをリアルタイムで経験していた僕らより今の人は熱心に研究しているというか。
竹部:最近はネットで知る新事実も多いです。
森川:僕は初期のステレオコンパクト盤2枚を持ってたから早い時期からテイク違いがあることに気付いたりはしていた、ラジオでかかるものと違うぞって。ラジオはモノラルがオンエアされてたでしょ?ステレオ盤の「プリーズ・プリーズ・ミー」は歌詞も間違えてるしさ。「恋する二人」はイントロのハーモニカがブレイクするし。その辺りは何曲か気付いてたけど当時はまだ音源が乏しかった。聴き始めた頃はそんな程度でした。つまり同時進行で段階的にビートルズを聴いていたわけだから。まだビートルズ現象のプロセスっていう感じだったのかも。海賊盤について知ったのも70年の秋でした。ラジオで八木誠ってDJが毎回2曲ずつオンエアしたんです。それは『Live At Atlanta Whiskey Flat』っていうアルバムからの紹介でした。必死でそのアルバムを探しました。そして京王線桜上水の「ドンキー」って小さなレコード店で見つけた。4000円!珍しいし、高かったですね。なぜかそんなローカルな場所にあったんですよ。これは衝撃的な出来事でした。当時の新譜アルバム『レット・イット・ビー』より聴いていたかも。

66年7月3日、ビートルズはもう日本に来ないと思った
竹部:それは貴重な話です! 後に森川さん、『ビートルズ海賊盤事典』に関わるんですよね。我々60年代生まれのファンは情報がありましたが、森川さんの時代はなかったわけですよね。情報は少ないけど、その少ない情報から頭で考えて行動に移す。やはり、リアルタイムで体験した人をうらやましく思いますよ。
森川:CHABO(仲井戸麗市)ともよく話すんだけど、あの時代にラジオからビートルズが聴こえてきたっていうことがいちばん衝撃だったって。だから毎日ラジオをつけてはビートルズのオンエアを待ち望んでた。レコードとかってそう簡単に買えないしね。ビートルズに興味ある奴がいたらお互い持ってるレコードを貸し借りしたりさ。ビートルズを聴いてる、好きだとかなかなか大っぴらには言えなかったんだよ。世間的にも偏見や誤解もあったからさ。今でもカーラジオから突然ビートルズが流れたりするとさ、あの時あの頃、その曲を初めて聴いた日の空気感みたいなものが蘇るんだよね。
竹部:ビートルズファン=不良の時代があったって考えられないですね。確かに今でも急に街中とかお店でビートルズが流れたりするとドキッとします。
森川:さっきの話の続きだけど、65年初めに『フォー・セール』を買う少し前かな、ラジオで「のっぽのサリー」を聴いたんですよ。それが「ツイスト&シャウト」を聴いた時ぐらいの衝撃で。なんてやかましくてカッコイイんだって!! とにかくレコードが欲しくて、ひばりが丘にあったレコード屋に発売前だったけどさ、何度か通ってた。当然まだ売ってないわけだけど。他のシングル盤のジャケット眺めながらさ、4人の顔を見られるだけでも嬉しかったのを覚えてます。
竹部:「のっぽのサリー」のポールのボーカルは強烈ですよね。
森川:強烈ですよ。ジョンが「ツイスト&シャウト」ならポールは「のっぽのサリー」って感じで。アルバムからのシングルカットや新曲がどんどんリリースされていって、次はなんていうタイトルだろう、どんな曲だろうって期待して、だから、次に出るレコードが待ち遠しくてしょうがなかった。ラジオでいち早く新曲を聴いた奴がいたら羨ましいやら悔しいやらで。
竹部:後追いファンの感覚とは全く違いますね。僕なんてビートルズを好きになった頃は、オフコースとかYMO、松田聖子や田原俊彦の時代で、ビートルズは昔のバンドという扱いでした。
森川:「ガール」っていう曲があるでしょ。あれを初めてラジオで聴いた時に今までのビートルズとは違うって思ったのを覚えてます。なんかジョンの声が柔らかいというかさ。生々しくて。で、途中から「チュチュチュチュ」ってコーラスが入ってくるじゃない。あれも斬新でさ。しばらく経ってテレビでだったかな、スパイダースの「サマー・ガール」を聴いて「コーラスがビートルズの真似してる!」ってビートルズ好きの友達と学校で話してた(笑)。
竹部:ビートルズの変化をリアルタイムで体験することの楽しさが伝わってきます。それで、66年の来日公演なんですが。この話はいろいろなところでされていますので深く聞きませんが、驚くのは、ビートルズが帰国した7月3日の朝にもう2度とビートルズは日本来ないと思ったっていう話。当時のファンとしての実感がこもっているなって思うんです。だって、あの時にツアーが終わるなんてことは誰も知らないわけじゃないですか。
森川:武道館を観たあと、気が抜けたんだろうね。それまでビートルズを観るために頑張ってきたんだから完全に脱力状態でした。僕は7月1日の夜の公演に行ったんだけど、ライブの前にE・H・エリックが「皆さんが自分の席でちゃんと聞いてくれたら、ビートルズはまた日本に来ると言っています」って言ったんですよ。残っている映像は「皆さんその席に座ってお聞きください」だけでしょ。でも、7月1日夜の部ではエリックがビートルズ登場前にそう言ったんですよ。で、嘘つけって思った。ビートルズがそんなこと言うわけがない。なんでそう思ったのかと言ったら、上手く言えないけど僕はすでに全エネルギー使い果たしてさ、崖っぷちに自分がいるような感じがしてたから。そんな簡単にビートルズが再び戻ってくるわけないって気持ちだったのかな。もう思い詰めた感情と言うか張り裂けそうな気持ちでビートルズの登場を待っていたから。だからこんなことはもう二度と起きないだろうって。これが終わったらビートルズは帰っちゃうんだよって。つまりビートルズは絶対日本に来ない。
竹部:ものすごい感性ですね。
森川:公演を観たのが金曜日、日本公演が終わった7月2日が土曜日、帰ったのは7月3日の日曜日。それで月曜日から学校でしょ。全身が疲弊してるようなすごく悲しい気持ちになってたのを覚えています。クラスに帰国子女の女の子がいたんですよ。その子は7月2日の夜の最終公演を見に行ったんだけど、僕にこう言ったの。「ジョンがメガネかけていた」って。へえって思った。その証拠を見るまでに随分時間が掛かったけど。とにかくビートルズ公演が終わった後は喪失感でいっぱいだった。
竹部:悲しいといえば、解散の時はいかがでしたか。
森川:むしろ悲しいと言うよりついにその時が来たかって感じが強かったかな。66年のときは、ビートルズはもう帰って来ないと思ったけど、いつかこっちから会いに行けば、つまりアメリカやイギリスに行けばイイやとか。あと『リボルバー』を聴いて少し立ち直ったんですよ。ジャケットはものすごく奇妙で変わっていると思ったけど、 音楽はそんなに変わってないと思った。多分まだどこかにバンド感というのかそのバランスが保たれていた。その前の『ラバー・ソウル』で進化し始めていたからさほどリボルバーに関しては驚きはなかったですね。逆に良い曲多いなぁって。ほんとに変わったと思ったのは「ストロベリー・フィールズ」ですよ。最初はこの曲ナニ !?って感じだった。「ストロベリー」が出る前かな?『オールディーズ』が出た頃、ビートルズ解散の噂が出たんですよ。すでに解散したってラジオで話してるDJもいた。思えば、どこかあの頃から解散の予感がずっと付きまとい始めてた。ポールの脱退宣言の前に「レット・イット・ビー」のシングルが出たんですよ。日本盤は70年の3月に出たのかな。あの曲、葬送曲の始まりみたいですごく悲しく響いた。あれが出て1か月後ぐらいにポールが辞めるっていうニュースがあって、最初にそのニュースを聞いた時は予期していたとは言え信じられなくもあり、その反面どこか受け入れてたような。 今思えば親の臨終に立ち合った時の気持ちとどっか似てるかも。冷静でしたよ。それで夏休みの終わりに有楽町のスカラ座に初日朝一で映画『レット・イット・ビー』を観に行った。あの時は単体での上映だったから立て続けに2回観た。
竹部:69年頭に『ホワイト・アルバム』、69年夏に『アビー・ロード』、明けて3月にシングル「レット・イット・ビー」。そして4月に解散宣言って激動ですよね。
森川:その時期は、ほかにも「ヘイ・ジュード」「ゲット・バック」「ジョンとヨーコのバラード」のシングルがあって、ジョージの『ワンダー・ウォール』なんかもあった。その間、次のビートルズ本体のアルバムはいつなんだって、『ホワイト・アルバム』から1年も経ってないのにずっと思ってた。『アビー・ロード』までがすごく長く感じられたんですよ。

69年1月、「そんなはずじゃないだろうビートルズ」
竹部:後追いだと『アビー・ロード』が最後っていう感覚がぬぐい切れないですよね。時系列がわかっていても。
森川:「ジ・エンド」を聴いても、バンドはまだ続くって思っていたんですよ。『アビー・ロード』は作品としてまとまっていたし。その前の『ホワイト・アルバム』は4人がバラバラでファンとしては悲しかったわけですよ。真っ白なジャケットにも驚いたし。だから、『アビー・ロード』を聞いて、まだビートルズは大丈夫だって自分に言い聞かせてた。
竹部:それは当時のファンでしかわからない皮膚感覚ですよね。
森川:CHABOに「新宿語る 冬」って曲があるんですよ。僕はあの曲を聞くと無性に1969年明け、冬の新宿の光景が蘇る。その中に「そんなはずじゃないだろうビートルズ」っていう歌詞があるの。それを聴くと僕が『ホワイト・アルバム』を買った日のこと思い出す。1969年1月19日。レコードを買って家に帰ってきたら、テレビのニュースが東大安田講堂の事件を伝えていて……。
竹部:なんと、そんな時代背景だったんですね。
森川:『ホワイト・アルバム』はビートルズの統一感というか堅牢なビートルズ4人の絆みたいなものがバラバラになって行くように思たんですよ。『サージェント・ペパーズ』や『マジカル・ミステリー・ツアー』の頃から薄々とそれは変わって行き始めた感はどこかあった。僕の友人のタモツって洋楽通がいて、そいつも帰国子女なんだけど、『サージェント』を聴いて「ビートルズはもう終わっちゃったよ」ってなんて言ってたし。ビートルズはポール中心に回って来てると言うんですかね。彼一人頑張っているけど他の3人が追いついていけてないというか。僕はそんな感じに思えていました。68年になるとオノ・ヨーコの登場がそんな雰囲気に拍車をかけた。だから『ホワイト・アルバム』が出た時、「そんなはずじゃないよな?」ってどこか思ったんです。最初はその理由がよくわからなかったんだけど針を落としたら「バック・イン・ザ・USSR」が始まるでしょ?あの時、なんかBEATって言うのかな?何かが違うって。後々わかるんだけどあの曲のドラムはリンゴじゃなくポールだった。そんなビートルズの当時のバンド内のムードをあのオープニングから感じてたのかも。ビートルズは大丈夫なのかな?って。この先どうなるのかな?って。ずっと考えてたような気がする。
竹部:そうなんですね。それを知って「新宿語る 冬」を聴くと沁みるでしょうね。
森川:『ホワイト・アルバム』が出た頃、社会全体が怖かったんですよ。東大安田講堂事件のほかに、永山則夫の連続射殺事件もあったし。ベトナム戦争は激化して行くし。
竹部:僕も永山則夫に関しては、昔から興味があって本を読んだりして、中上健次じゃないですけど、自分の中の永山則夫を探すときがあります。
森川:永山則夫が捕まってあとに出た週刊誌には「永山は人を殺すことを楽しんでいた」なんて記事が出ていたけど、そんなもんじゃない。『無知の涙』を読んで、ものすごく過酷な人生だったことを知るわけ。
竹部:今でも東京プリンスホテルに行くと、ここが現場のひとつだったんだと思ってしまいます。
森川:そうそう。最終的に彼が捕まったのは、千駄ヶ谷のビジネススクールなんだよね。
竹部:ビートルズの出来事と日本の事件や社会情勢、そして自分史を入れてくと面白いですね。
森川:日本もアンダーグラウンドなフォークが登場したり、文化も社会も70年安保を前にいろいろ日本は混沌として、時代は劇的に変わってくんだなと思っていたよね。
竹部:そういう時代背景で「レボリューション」を聞くと臨場感があったんでしょうね。
森川:後付けかもしれないけど、ポール「ブラックバード」もそうだったんだろうし。
ジェンダーレスの時代の先駆者だったビートルズ
竹部:話を戻しますが、ビートルズがご自身のクリエイティブに与えた影響を言葉にすると、どういうことになりますか。
森川:うまく言えないけど、なんか偉そうな言い方になるけど、オリジナルってことだったんじゃないですかね。ビートルズは他の人がやってないことをやった先駆者でしょ。だから自分も偉そうに、そういうことをやりたいって思ったんじゃないのかな。 ビートルズのエッセンスの入っている音楽は好きだけど、自分がやろうとしたのは、新しいものを取り入れたいと思いましたよ。あとは、曲のタイトルの付け方とか言葉のセンスとかユーモアも。自分では気が付かなかったけど、そういうこだわりは影響を受けていたと思います。
竹部:よくいう話ですけど、ビートルズは何度聞いても新しくて、いろんな発見がありますよね。
森川:本当にあるんですよ。今になって、ようやく彼らの声を聞き分けられるようになって、驚いた曲もある。
竹部:ジョンもポールもジョージも声は似てないんですが、1曲の中で歌うと似ていて区別がつかないんですよね。
森川:「シー・ラブズ・ユー」なんか、ジョンとポールが歌っているところに、途中でジョージが入って混ざってくるから余計わからなくなる(笑)。
竹部:こういうのは他のバンドではないですね。
森川:ない。あと、ビートルズは本当に音がいいということ。ジョージ・マーティンはあの当時ビートルズの他にもいろいろなバンドのプロデュースをしているのに、ビートルズだけ別格にレコードの音がいい。同時代のほかのバンド、たとえばストーンズなんかと比べても全然違う。不思議ですよ。それがマジックなんだと思う。
竹部:今回の『青盤』で「ストロベリー・フィールズ」を聞くと、とんでもなく音がクリアですからね。
森川:いろんな冒険していたこともわかるし。いろいろ試しているうちにレコーディングのおもしろさや可能性に気づいていったんじゃないのかな。まさにマルチレコーディングの元祖だし。「ミッシェル」を最初に聞いた時、間奏は何の楽器だろうと思ったんですよ。木管楽器かな?なんて。ギターには聞こえなかった。当時はそういうことがわからないから。エンジニアのノーマン・スミスに相談しながらギターの音を変えてったわけだよね。
竹部:同時代の、そしてその後の多くのアーティストやエンジニアに影響を与えたんでしょうね。
森川:ビートルズのレコーディングが複雑になっていった時期とフォーク・クルセダースが出た時期って重なっているでしょ。ちょうど、フォークルは『サージェント・ペパーズ』と『ホワイト・アルバム』の間に出ているんだけど、最初にフォークルを見たときに、加藤さんってジョンの影響を受けているなって思いましたよ。
竹部:当時のプロフィールに“加藤和彦、ニックネーム:ジョン”って書いてありますよね。まだトノバンではない。そういえば、加藤さんの映画見ましたよ。『トノバン』。森川さん、出ていましたよね。
森川:「あの素晴しい愛をもう一度」を歌うので来てくれって言われて行った。加藤さんのジョンってニックネームはキングストントリオのジョン・スチュワートが由来だって言ってたけどどう考えてもジョン・レノンだと思えてしまうよね。
竹部:あの映画でも映った加藤さんとミカさんの結婚式の映像、完全にジョンとヨーコの『ウェディング・アルバム』でしたよね。それにしても、あの映画はよくまとめていましたね。感動しました。
森川:今でも加藤さん亡くなったのは悔しいし惜しいと思う。
竹部:加藤さんはビートルズみたいところがあって、誰もやったことがないことを誰よりも先にやっていました。森川さんと会うと、こうやってビートルズの話からトノバンの話でも盛り上がりますよね。
森川:そうそう。ファッションもそうだし、ヘアスタイルもそうだし。ビートルズの音楽的なところだけじゃなくて、僕たちが成長していく中で、ものすごく影響力のあった人ですよ。人間はこんなふうにして変わってくんだみたいなことを、加藤さんを通じて教わった。
竹部:ミカさんがクリス・トーマスのところに行かなかったら、と映画を観て思いましたが。
森川:“もし”はないからね。もし、ジョンとヨーコが出会っていなかったら。最初からなにか運命的にそう書き込まれていたと思うしかないよね。晩年の作品「ウーマン」で“♪After all it is written in the stars”と歌ってるし。
竹部:ヨーコも言っていますよね。自分が人生を選択したように思うけど、違うのよって。最初から私とジョンは会うことが決まってたのよ。86年あたりのインタビューで語っていました。それでも今度のメイバンの映画『失われた週末』を観ると、“もし”って、考えてしまうんですよね。ジョンは74年の時点では、メイ・パンとずっといるつもりだったんですから。
森川:最初にオノ・ヨーコが登場したとき、日本のファン、とくに女の子はみんな嫌だと言っていました。僕も、ジョンはどうなっちゃったんだろうと、思って心配していたけど。一方で、公然と自分のパートナーを公に紹介するのってカッコいいなと思った。ビートルズのメンバーはみんな公の場で平気な顔して彼女と手をつないでいたでしょ。いま“ジェンダーレスの時代”とか言われているけど、ひょっとしたらそういう意識って、ビートルズが最初なんじゃないかなと思う。
竹部:確かにそうですね。初期はアイドルなのに、当然のように彼女と一緒にプレミア試写会に現われて。
森川:それがかっこよかったんですよ。僕もいずれは女の子を連れて公の場に出たいって、そんなふうに思ったもんね(笑)。
竹部:加藤さんとミカ、その後の安井さんのツーショットも絵になりましたよね。ああいうふうに年を重ねたいと思いました。
森川:そういえば、僕が清志郎の本を書いていたとき、清志郎から当時のノートをたくさん借りたんですよ。そのなかに高校生の頃のノートがあって、そこに“RCサクセションとフォーク・クルセダースの比較”って書いてあったの。同じ3人組だったし、もちろんビートルズが好きだとか。清志郎もどこかフォークルに影響受けていたんだと思う。その存在っていうかね。
竹部:『GOTTA 忌野清志郎』ですね。名著!
森川:話がずいぶん行ったり来たりで、外れちゃっているけど、僕は、ビートルズ、加藤さん、それとRCですね。
竹部:話の本質はブレてないので大丈夫です。そう考えると、ジョンが死んで、RCがブレイクした1980年というのはひとつの転機といっていいのでしょうか。
森川:変わり目でした。僕が松本常男くんと出会ったのも80年。ジョンの事件の1週間ぐらい前に初めて会った。それがきっかけになって宝島で『JOHN ONO LENNON』を作ることになったんだけど、本当はジョンの新しいアルバム『ダブル・ファンタジー』に合わせた特集号だったんですよ。それがあの事件で追悼本になってしまいました。
竹部:『JOHN ONO LENNON』は大好きな本です。
森川:松本くんはその頃からブートのビデオをすごい数持っていて、いろいろ観させてもらって。久々に、つまり日本でのテレビ初放映から16年ぶりに『エド・サリバン・ショー』を観て感動したんだよね。しかも、ブートで音は知ってたけど観たこともないマイアミ・ヴァージョンの映像なんかも持ってて。
竹部:僕がコンプリート・ビートルズ・ファンクラブのフィルムコンサートで観たやつですかね。僕はファンクラブ会員だったので、松本さんにかなり影響を受けました。ボランティアで荻窪の事務所に手伝いに行っていたこともあるくらいで。あとになって松本さんと森川さんが友達だったと知って驚きましたから。
森川:80年に始まった流れがずっと続いているんですよ。
竹部:RCは80年1月の屋根裏から快進撃が本格化していくわけですよね。
森川:そう。本当はウイングスの来日公演を全部観るつもりだったのに、ポールの逮捕で公演がキャンセルになって、結果RCの屋根裏を4日間全日観ることになった。本来ならウイングスと被ってるRC屋根裏は2日しか行けなかったはずだったけどさ。ウイングスを観ることができなかったのは残念だけど、あの屋根裏4日間は凄まじいものがあった。それがオレの運命なんだって妙に納得した。
グロウイング・アップ・ウィズ・ザ・ビートルズ

竹部:そこから『ラプソディー』につながるわけですからね。ヨーコの言う通り、決まっていたのかもしれませんね。では時間もなくなってきたので、最後に、今後の森川さんのビートルズライフについてお聞きしたいのですが。
森川:どうしたらいいんだろう、と思うんですよ。突然死んでしまったら、自分の持っているコレクションと言うかこの60年間に僕の元に集まってきた物の数々。それがどこかに没収されるなんて、嫌な話じゃない。誰かに渡していくという方法もあるかもしれないけど。僕のまわりには松本くんをはじめ、コレクターがいるからみんなでミュージアムみたいなものを作ったらどうかなって考えたこともあるんですよ。
竹部:コレクションの話は、ファンにとっては問題ですよね。
森川:ほかには、まだ観たことのないビートルズの映像があれば観てみたいし、未完の音源があるのであれば聴いてみたいと思う。あとはなんだろう。まだまだ自分を納得させるためにビートルズを研究していきたいっていう気持ちはある。『ビートルズ史』(マーク・ルイソン)の続きも読みたいし。あれを読むと新しい発見があるわけですよ。そういえば、「ハロー・リトル・ガール」ってあるでしょ? ビートルズがデッカ・オーディションで歌ったのは62年だけど、その前にロイド・プライスって黒人歌手が同じタイトルのレコードを出しているんですよ。この間、その曲を聴いてみたらサビで「I Wanna Hold Your Hand」って歌っていて驚いた。ジョンはそのレコードを聴いていて、言い回しというかそのフレーズや言葉のヒントを得たんじゃないかと思ったんだけど、どうかな。
竹部:それは興味深い。
森川:あとは趣味で自分のビートルズ体験を書いていこうかなと思うんですよ。60年代に、あの曲を最初に聞いたとき思ったこととか。幸い日記をつけていたから、当時の記録がだいたい残っているんです。
竹部:日記があるんですか? それは貴重。僕はこの連載で80年以降のビートルズ史を自分目線で書こうと思っているんですよ。
森川:それはやるといいですよ。僕はは64年からになるんだけどね。前に『グロウイング・アップ・ウィズ・ザ・ビートルズ』っていう洋書があったんだけど、あれは筆者が小学校から中学、高校、大学って育っていくなかで、ビートルズの音楽を聴いていたことを書いていておもしろかった。著者が僕と同じ年というのもあるんだけど。あとロバート・R・マキャモンっていう作家知ってる?『スティンガー』っていうSF小説を書いている人なんだけど、彼が書いた『少年時代』っていう小説があるんですよ。彼もまた僕と同じ年で、自分の少年時代のことを回想した小説なんだけど、これも面白くて。その中にやっぱりビートルズが出てくるんですよ。
竹部:今日の話でも十分面白いのでぜひ森川さん版の「グロウイング・アップ・ウィズ・ザ・ビートルズ」を読んでみたいです。
森川:ビートルズに近かった関係者よりもファンのほうが些細なことまで詳しかったり、どうでもいいようなことまでよく覚えていたりするんですよね。ほかの人からも僕のリアルタイム体験話を読んでみたいと言われたことあって、なんかやりたいですね。
竹部:僕が編集しますのでやりましょうよ。お願いします。今日はほかにポールに会った時のこととかも聞きたかったんですが、そこまで行けませんでした。また次回、登場をお願いできればと思います。
森川:楽しかったです。脈絡のない話でごめんなさい。ビートルズのことになるとあれもこれもって感じで話が後から後から出て来てすみません。
竹部:とんでもないです。お時間いただきありがとうございました。

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)