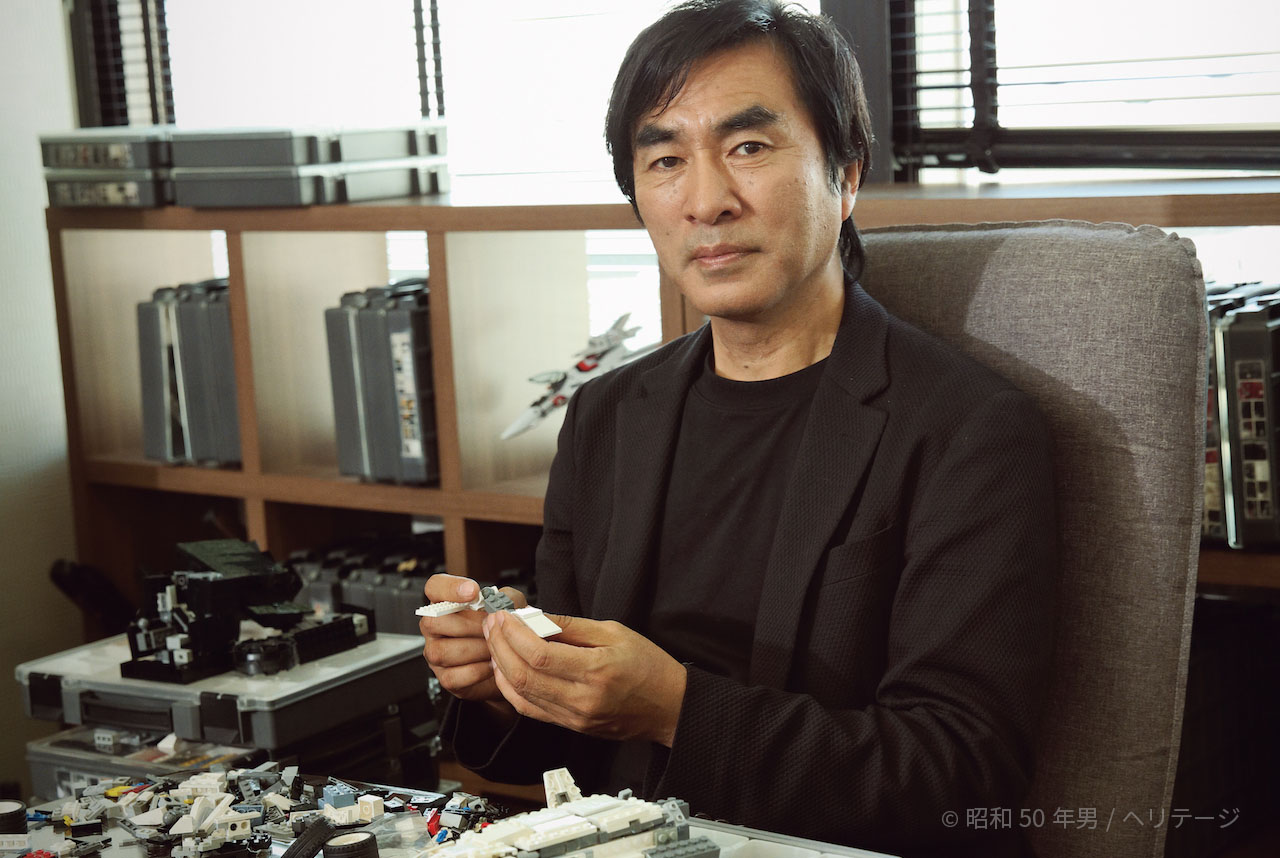リアルな戦闘機が変形バルキリーの誕生

河森正治は、中学3年生の時に『宇宙戦艦ヤマト』(74〜75年)を観て衝撃を受け、友人たちと一緒になってハマってしまったという。同作には、宮武一貴、加藤直之らが所属する企画制作スタジオ・スタジオぬえがメカニックデザインとして参加しており、河森は、放送が終わった春休みにぬえを見学に行った。
「6〜7畳あるかないかぐらいのところに4人が寝泊まりしていて。ここで未来SFが作られているのかって思って、あまりのギャップに衝撃でしたね。だからこそ思考は無限大なのだと実感しました」
高校生の頃からぬえに出入りするようになると、大学在学中の19歳で社員に。大学に通いながらメカデザインの仕事に就いていたのだが、1年ほど経った時に、ぬえで「ジェノサイダス」という企画が立ち上がる。しかしこの「ジェノサイダス」はハードSFだったため、なかなか企画が通らず、その当て馬のような形で、少しライトなものとして考えられたのが「マクロス」の前身企画「メガロード」だった。
今でこそSFアニメは一般的なジャンルとなっているが、当時は本格的なSFアニメがそんなに多くはなかった時代で、オリジナル志向が強いぬえのメンバーは「せっかくやるなら、オリジナルで何かできないか」と模索していた。また、時代的には『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダム』のヒットがあり、「なんとかそことの差別化をしたい、何がなんでも違うものを作りたいという思いはありました」と、河森は振り返る。
「もともと『ジェノサイダス』は、人型ロボットに代わる主役メカを作ろうということでスタートしているんです。そこに出てくるのが鳥脚メカ、つまりガウォークだったんです」
しかしスポンサーから、「人型ロボットじゃないと玩具が売れない」と却下されたため、ぬえは人型ロボットへの変形メカ企画「メガロード」をダミーとして出す。
「だから、大型戦闘空母も変形するし、戦闘機も変形するんです。この時はまだ、戦闘機というより、従来の変形メカに毛が生えた程度だったのですが、まずはそんなところからスタートしたんです。ただ、巨大戦艦を人型にするだけだと、他の人も考えそうだなと思ったので、どうせなら中に街を入れてしまおうと思いつきました。街には一般市民も住んでいるから、そこに中華料理屋などのお店もあって…ということで、高校時代の同級生・美樹本(晴彦)くんがそこの看板娘が歌っている絵を描いてきたのですが、このキャラがとてもよくて。店で歌うだけじゃなくて、いっそ歌手にしてしまおう、歌手が出てくるロボットアニメなんてほぼないだろうから…となって、後のリン・ミンメイになるんです」
こうしてアイデアを進めていくうち、「ジェノサイダス」よりも「メガロード」の方が企画として通りそうになり、ぬえもこちらに本腰を入れるようになる。
「もともと宇宙”戦艦”だとヤマトになっちゃうから、メガロードは”空母”になってるんです。だから、空母の艦載機ならもっと本物の飛行機に近いものにできないかと思って。そして、 F-14トムキャットのプラモデルを見ている時に、左右のジェットエンジンの間に腕が入ることを思いつき、そこから変形方法を全部改めて、今のバルキリーができ上がっていきました。おもちゃ屋さん(メーカー)からは『飛行機は売れないからやめてくれ』と言われたんですけど、そんなに言うならもっと飛行機にしようってF-14に近い形にして、バルサと紙と金属のヒンジで試作品を作ったんです。
それをさらにぬえの近所にあったモックアップメーカーに依頼してモックアップも作ってもらって、おもちゃ屋さんに持ち込んだら、やっと納得してもらえたんです。ちなみに、その試作品を作っている段階で、脚を逆関節に曲げると、ガウォーク形態になることがわかって、『ジェノサイダス』の案も復活すること ができました」
『マクロス』といえばバルキリーを思い浮かべる人も多いだろう。今なお色あせない名作メカだが、その完成までには紆余曲折があったようだ。
「内容面で言うと、ストーリーにしても演出方法にしても、極力他の作品に似せない、特に『ガンダム』には似せないということを心がけていたんです。自分も『ガンダム』のファンクラブも作るほど好きだったんですけど、 好きだからこそ絶対に似せないって思っていました。基本的に『マクロス』系のデザインがわざと人型のプロポーションから外しているのも、そうした意識からきているんです。でも、やっぱり『ガンダム』のフォーマット自体が強すぎるんですよね。たとえば、カットインでロボットの前にキャラを見せるとか、戦闘中に敵と味方で対話するような演出とかも、あれをやらないようにするとなると、すごい手間がかかるんです(笑)」
リスペクトがあるがゆえに、偉業の大きさを実感したわけだ。ただ、いずれにしても、河森およびスタジオぬえのオリジナリティを追求する姿勢、そこから具現化された画は、とにかく印象的である。
若気の至りからつかんだマクロスらしさ
「メガロード」の企画は一気に動き出し、「マクロス」と名前を変えて、実際の制作体制が整っていく。監督には、『ヤマト』の頃からぬえとの関わりがあった 石黒 昇。キャラクターデザインの美樹本はまだプロになる前後 ぐらいだったため、『マクロス』をきっかけに石黒率いる制作プロダクション、アートランドに入ることになる。
「石黒さんは、何やっても野放しにしてくれて、ありがたかったですね。僕らぬえのメンバーは原作者側だから原作者特権みたいなもので認めてもらって『とりあえずそれでいいよ』と。そういう意味では懐の深い方でした」
またこの頃、河森は映画『クラッシャージョウ』(83年公開) の現場で、アニメーターの板野一郎に出会っており、メカ作画監督として参加してもらうことになる。板野の印象を聞いてみた。
「板野さんって、メカアクションのカットを何度描いても演出の人にタイミングをいじられちゃうからって、倉庫に勝手に入ってシートを書き直したら、やっと富野(由悠季)さんに認められた人なんですよね。その映像を見た時から、僕も空間把握が他と全然違うな、すごいなって思っていました。やっぱり参加していただいてありがたかっ たです。あと、板野さんのフォロワーで、きれいなミサイルを飛ばす人は出るかもしれないけど、板野さんのように”当たると痛いミサイル”を描ける人はあまりいないと思います」
河森いわく「システマチックにというより、人との出会いと、若気の至りのような勢いで作ってきた部分が大きい」という『マクロス』は、こうして動き出す。河森はというと、メカニックデザイン、設定監修だけでなく、 構成、演出、脚本など多岐にわたって関わっている。当時はまだ大学に通いながらで、他のアニメでもゲストメカデザインも数作受けもっていた。しかも、まだアニメ制作にも慣れていなゆえ、自己流で仕事をこなしていたことを考えると、相当に苦労したことは想像に難くない。加えて、制作スケジュール自体もひっ迫しているという状況だった。
「制作が追い込まれすぎて、ストーリーの半ばの頃に総集編を作らなきゃいけなくなったんです。それが14話『グローバル・レポート』だったんですけど、それにもかかわらずまた総集編を作らなきゃいけなくなって。それが 17話『ファンタズム』なんですけど、2週間でオンエアしないといけなかったんです。まず、新作30〜40カット作っていいと言われたんで、新作カットだけを考えて打ち合わせして。
それから、当時はまだビデオ編集室なんてなかったから、家にあるベータプロデッキを3台並べて、録画していた放送済のビデオを自分で編集。さらに既存の口パクに合わせたセリフを考えて、一本ストーリーを作り上げるということをやりました。あれは本当に大変だったけど、映画とかアニメの本質が”アングルと編集にあり”っていうのがよくわかって、いい勉強になりましたね」
『超時空要塞マクロス』は1年の放送予定だったが、いろいろあって2クール、さらに3クールへと変更され、制作しながら内容を圧縮する改編作業が行われたという。そんな苦労を重ねながらも、河森のこだわりが形になる伝説回が生まれる。27話「愛は流れる」だ。
「どうしてもメカ戦とか、武器の力で解決しちゃうと、他のSFアニメ、戦争映画とも変わらないので、何かないかって思っていたんです。もともとミンメイの歌が文化を知らないゼントラーディに影響を与えているところまでは設定していたんで、じゃあ歌の影響だけで勝てないかって提案したんです。多くの反対を受けたんですけど、一応 原作者特権ってことで、コンテから何から責任をもってやるのでどうしてもやらせてほしいって言って、その案が通ったんです。実際にやってみて、アニメで歌わせることがどれだけ大変かってことがよくわかりましたけど(笑)。
でも、自分としても手応えがありましたし、周囲や視聴者からの反応を見たら、SFとしてもすごく納得してもらえた。宇宙戦争を歌で終わらせちゃうっていうのは、ロジックに飛躍があったからこそ、SFに慣れたかなって思います」
結果、情報量の多い戦闘シーンにアイドルの歌が重なるという前代未聞の映像ができ上がった27話「愛は流れる」。『マクロス』の評価は、ここで一気に高まったと言っていい。その後、番組は玩具が好調で 2クールから3クールへと延長されたため、36話まで放送。さらに、劇場版の話がもち上がる。すると河森は、石黒との共同監督として抜擢されることになった。
「アニメフレンドのプロデュー サーだった岩田 弘さんが、『ファンタズム』や『愛は流れる』での作業の様子を見て、監督に推薦してくれた形なんです。話がきた時は、再編集版+αかと思ったら、完全新作でいいと言われまして。完全新作なら、キャラも変えちゃおう、大画面で出しやすいようなデザインにブラッシュアップしよう、ってことにしました。それからどのように設定を変えれば、2時間弱に収まるかを考えたんですけど、今思えばデザインも設定もリセットするわけですから、ものすごく効率が悪いですよね(笑)。まだアニメの現場のこともよく 知らないから、やったらダメってことばっかりやってたし、周りのスタッフは大変だったと思います。若気の至りですよね(笑)。
それから、テレビと映画 だと結構ロジックが違うからどうするかとか、そこはすごく考えました。これは僕の感覚なんですけど、テレビはだいたい20分くらいの尺で、倍の尺になると1.5〜2倍難しくなって、3倍になると二乗で難しくなる。そう考えると、最後のパートになると難しさ16倍とかになる。だから、アイデアの注ぎ込み方とか、まとめ方とかを、後半になるほど、前半をどう乗り越えていくかって考えなきゃいけない。その構想を考えるのが、『愛・おぼえていますか』ではいちばん大変だったかな」
こうして制作された『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』(84年公開)は、テレビシリーズでは正直思いどおりにならなかった部分がすべて解消されており、しかも今なおセルアニメ史上最高レベルと呼ばれるほどクオリティの高い作画、映像を生み出した。河森が”若気の至り”でこだわった『マクロス』でやりたかったことは、やっと理想型と言えるものになった。
シリーズでの変化と変わらないもの
『マクロス』シリーズは、10周年記念作品としてOVA『超時空要塞マクロスII -LOVERSAGAIN-』(92年)が登場するが、本作に河森らスタジオぬえや板野は参加していない。河森が再び『マクロス』の現場に戻ってくるのはOVA『マクロスプラス』(94年)とテレビシリーズ『マクロス7』(94年)の頃である。当時のことを河森はこう振り返る。
「若い頃は、同じことは二度とやりたくない、ただしメディアが変わればやる、とか言ってたんですよね。だから、映画はメディアが違ったからやったし、OVAはビデオ編集機が使えればやるとか言って『超時空要塞マクロス Flash Back 2012』(87年)を作ってみたり、ゲームもやるしといった感じだったんです。でも、走行しているうちになかなか企画が通らないし、作品も作れなくなっていて。そんな時に、若くして亡くなった高梨(実)プロデューサーから『10年経ったらもう時効だから。またマクロスをやらないか』と言われて。そうか、時効という手があるかと(笑)」
高梨の話を受け、気持ちに変化が生まれた。しかしやるんだったら初代とも違う切り口の『マクロス』ができなければ、やっても意味がない。そこで1週間ほど時間をもらい、企画を考えることになる。
「最初は歌って戦うパイロットというアイデアを思いついたのですが、それだとまだ誰か思いつきそうだなと思って。だったら空前絶後を狙おうと、歌って”戦わない”パイロットにしたんです。ただそうするとメカファン向きじゃなくなるんで、メカファン向きもちゃんとやる『マクロスプラス』の企画も考えました。その2本(『マクロスプラス』と『マクロス7』)の企画を出して、2本とも通るんだったらいいですよって言ったら、高梨さんが本当に通してくれて、それで復活したんです」
”他人の真似をしない”どころか”他人に真似されたくない”まで考えるのだから、その情熱には脱帽である。そして河森いわく、あの頃から『マクロス』は毎回スタイルを変えようと考えていたとのこと。
「最初のテレビシリーズは、あんまりドラマチックに演出しすぎない作りで、再現ドラマみたいなセミドキュメンタリー。『愛・おぼえていますか』は、芝居づけも気持ちオーバーな感じにチャレンジした舞台劇。じゃあ次はマンガと思ったから『マクロス7』になって、『プラス』の方は洋画ということになるんです」
ちなみに、その後の『マクロスゼロ』(02年)は神話風、『マクロスF(フロンティア)』(08年)は学園もの、『マクロスΔ(デルタ)』(16年)はチームものとなる。このように作品ごとにスタイルを変えるのだが、どの『マクロ ス』シリーズも必ず、”歌”と”戦闘”と”三角関係”の要素が、三本柱としてある。河森自身にとって、『マクロス』らしさはどこにあると思っているのだろうか。
「作品を作っている自分にとってもいちばん楽しいのは、歌と戦闘とドラマの全部が一致していくところですね。カオスな感じっていうか、あの高揚感がすごく好きなので、そこはひとつの柱だと思います。集大成を作ったことがなかったので、『F』でそこにトライしたんですけど、あれで『マクロス』がリセット、若返りできたような。これでもう一段、次に続けられるようになれた気はします」

やはりあの歌と戦闘とドラマが渾然一体となる瞬間は、確かに『マクロス』ならではの映像。あそこに集約するからこそ、すべての要素があるとも解釈できる。
また、シリーズが長く続けば、ずっと続けてくれてるスタッフもいれば、新しいスタッフも加わり、新たな風を吹き込むことになるので、新たな『マクロス』の世界を見せることができる。『プラス』や『F』で音楽を担当した菅野よう子などは象徴的な例だ。加えて新しい技術もどんどん追加されており、かつてはアナログの手描きだったが、CGを活用し、デジタルアニメの時代になり、3Dが導入されたりと、常に新たなチャレンジができる。
「ある種、時代の変化をそのまんま受けながら育っている感じはありますから、それは『マクロス』シリーズのおもしろいところかもしれないです。もともと歌も含めた文化がひとつのテーマになっているので、カルチャーを表現しやすい作品ですから、変化を表現しやすい構造にはなってると思いますね」
河森たちが作り上げた唯一無二の基軸は守りつつ、時代に応じて変化を取り入れていく。それが『マクロス』が長年続いている要因なのだろう。最後に、ファンへのメッセージをうかがった。
「40年以上前から観続けてくださっている方も、近年の『F』や『Δ』から観てくださっている方も、『マクロス』シリーズを観ていただきありがとうございます。これからも新たな”デカルチャー”を求めて創り続けていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします」
※情報は取材当時のものです。
(出典/「昭和50年男 2023年7月号 Vol.023」)
取材・文 サデスパー堀野 撮影 坂本光三郎
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)