いよいよ、どちらのボディか決心しないといけないタイミングが来た。さて、どちらを選ぶべきなのか?

電源スイッチの位置はEOS R6の方がいい
実は、両者を借りた最初のタイミングでは、違いはあまりよく分かってなかった。
画素数約2010万画素→2420万画素は、どちらにしてもそれほど公がおは必要ないし、連写20コマ→40コマも、そんなに連写する必要はない。手ブレ補正最大8.0段もR6と同じ。高感度高画質とかは、どんなカメラでも言うし、AFのトラッキングで馬が追えると言っても、馬を撮る機会はほとんどない(笑)

ならば、10万円安いR6の方が良いのではないか? 10万円あればレンズの1本も買える。それどころか、操作性に関してはR6 Mark IIよりR6の方が良いように感じた。

EOS R6 Mark II(左奥)は電源スイッチが右ダイヤルのところに移動しているのだが、これは以前のように左にあった方がいい。というか、左肩にある動画、静止画切り替えスイッチが勝手に切り替わって動画モードになってしまっていることが多かった。あまり動画を撮らない私として、こんな触れやすいところに切り替えスイッチを配して欲しくない。
まぁ、慣れればいい話かもしれないが。
10万円追加出費の言い訳を考えてみよう
新機能をいろいろ試してみたが、当初、大筋は変わらないような気がした。1点AFの時に選べる点が、より細かくなったり、というような違いはあるが、そのために10万円出せるというものでもない。
しかし、なんとなくやっぱり旧型を買うというのは悔しい。そこで、新型を買うべき理由を書き出してみた。
順を追って説明していこう。
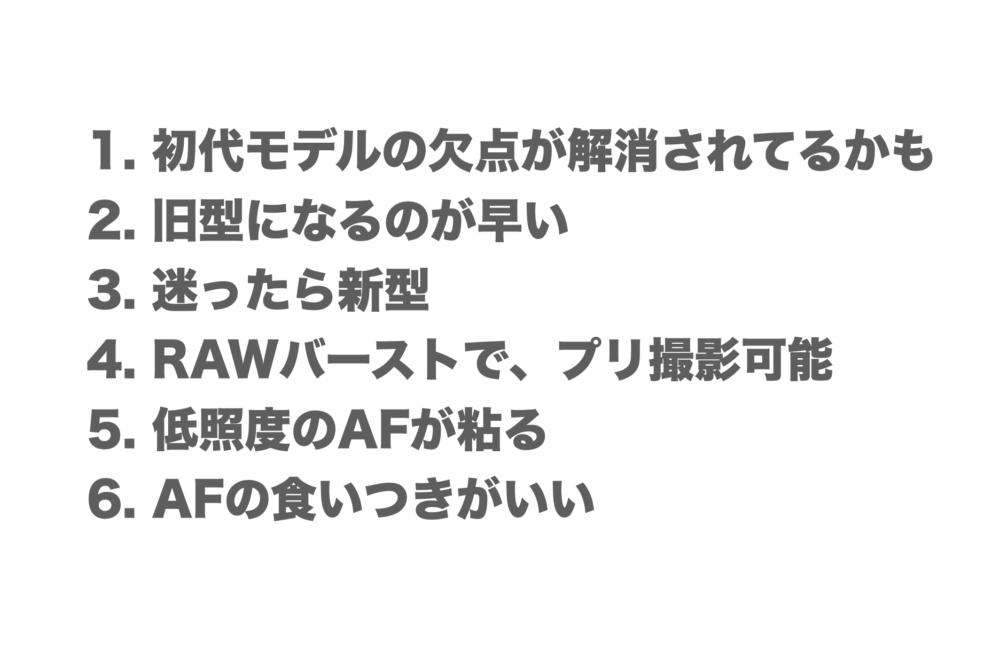
1.初代モデルの欠点が解消されてるかも
これはガジェットを買う時の基本のようなものだが、初代モデルには少なからぬマイナーな不具合があることがある。たとえば、初代モデルで折れやすかった部品に補強が入るとか、壊れやすかった部分が改良されるとか、そういうことは絶対にある。
絶対にあるが、カメラ屋さんで聞いてみると「今やR6を作る時に、何か経験値が足りないということはないから、あまり2型がいいというものではないです」とのこと。まぁ、僕の思い込みのようなものかもしれない。
2.旧型になるのが早い
これは、iPhoneや、クルマなどでもそうなのだが、3年落ちの製品を買って、3年経つと6年落ちになってしまう。何を当たり前のことを……と思うかもしれないが、部品の供給が途切れるもの早いし、サポートが終了するのも早い。筆者のように、なんでも長期間使い続ける人にとっては、『旧型になるのが早い』というのは大きな欠点だ。
3.迷ったら新型
もう、家訓のようなものですね。
『迷ったら新型』。ガジェット好きなら誰しも分かってることだと思うが、新型の方がいい。だって新型だもの。新型のモビルスーツに乗れば勝てるんです。
まぁ、ここまでは、なんとか新型を買うことを自分に納得させるための、言い訳のようなもの。本番はここから。
4.RAWバーストで、プリ撮影可能
RAWバーストという機能があって、シャッターを切る前の瞬間の画像をバッファし続けて、押した瞬間から0.5秒前までの画像を選択可能になる。
何のためにある機能かというと、言うならばカワセミを撮るための機能。いくら頑張っても一般人の反射神経では、カワセミが飛び立った瞬間にシャッターを押すことはできない(少なくとも私は)。この機能があれば、飛び立ってからシャッターを押しても、カワセミが枝から飛び立つ瞬間を記録することができる。

使うかどうかというと微妙な気もするが、新しいAFは鳥の目も追いかけてくれるそうだから、これがあれば私も飛翔するカワセミが撮れるかもしれない。EOS R6 Mark IIを購入した暁には、いつか撮影したい。
5.低照度のAFが粘る
AFにも光が必要だから、暗くなるとピントが合わなくなる。しかし、EOS R6 Mark IIのAFはかなり頑張って、ピントを合わせてくれる。

この写真はISO 4000、F2、1/160。けっこう暗い場所なのだし、髪の毛が目にかかっていたりするのだが、ちゃんと狙った左目にピントが来ている。

こちらはストロベリーパンケーキにピントを合わせているのだが、なんと感度2万5600で、F4.5、1/100。相当暗くても使える絵を撮ってくれる。もちろん手持ちだが、手ブレ補正のおかげでブレもない。
写真だけ見ると分からないと思うが、一昔前だったら、絶対に手持ちで撮れるような明るさではない。
6.AFの食いつきがいい
なんといっても最終的に、「これは、Mark IIを買うしかない」と思ったのはAFの食いつきの良さだ。
手前にも紅葉があったりするような複雑な場所でモデルにグルグル回ってもらって、そこを連写して、どのぐらいピントが来ているかを試してみた。
こちらがEOS R6。

こちらが、EOS R6 Mark II。

縮小画像なので分かりづらいと思うが、瞳にピントが来てる度合いは圧倒的にEOS R6 Mark IIの方が多い。
また、瞳が見えない確度だったとしても頭部、つまり髪の毛に合焦したりしている。EOS R6だと、ピントが抜けてしまうこともある。
これはどういうことかというと、取材時で人が錯綜しているような状態、たとえば、発表会の会場でティム・クックを見つけて、周りに人がいっぱいいるような状況で、手を伸ばしてワンハンドで撮ったりしてもちゃんとティム・クックの瞳に合焦した写真が撮れるということだ。
記事に使っている写真は当然、極力合焦した写真を使うから、読者の方はお気付きではないと思うが、しかるべきところにピントが来ておらず、使えない写真はけっこう多い。
また、F値の小さなレンズで、開けて撮って後ろをボカしたりした場合、ちょっとしたズレで合焦しているところが違ってしまうが、被写体検出トラッキング任せで、バッチリと瞳を追い続けるので、インタビュー写真などの時にとても便利そう。

この写真はRF 135mm F1.8で撮っているが、1cmズレたら、瞳にピントが来てる感じはしないだろう。そういう意味では、ピントの浅いポートレート写真を撮るには、必須の機能といえるだろう。
たとえば、こういう大勢の人がいる写真などは、あまりピントが合う場所を意識せずに撮ってしまうこともあるが、それでも自動的に一番主題になりそうな人に合焦してくれるのは助かる。誰にもピントが合ってない写真よりは、誰かにしっかりとピントが合っていた方がいいのだと感じた。

被写体がグッと乗り出した、こういう写真でも、しっかりピントが来る。この写真もF2なので、ともすればピントが合わなくなる写真だが、しっかりと瞳にピントが来てることは大切だ。

ただし、食べモノなどを撮る時は、かならずしも主題の部分にピントが来るわけではないので、そこは1点フォーカスで、ピントを合わせねばならない。
オートだと、手前のショウガにピントが来たりしてしまう。
魚や肉のいちばんシズル感のある所にピントが来て欲しいのに、付け合わせのパセリに合焦したりしてしまってはガッカリだ。実際には、料理の場合は思ったより手前に合焦したりすることが多かった。

ちょっと離れたところにいる人でも、ガッチリ人物にピントが来る。
クリスマス前に、店内で働いている人を、テラス席から撮った。こういう何気ないカットでも、自動的に、人物、頭部、瞳に合焦するように頑張ってくれるのは本当にすごい。

何気なく撮ったカットでも、ちゃんと人物にピントが来てることで使いモノになるかと思うと、『ピントが合う確率が上がる』というのは素晴らしい。
特に望遠レンズを使ったり、明るいレンズで開けたりとピントの浅い状態になると、ピントの食いつきが良く、しっかり追い続けてくれるEOS R6 Mark IIのAFの価値は大きい。
というわけで、EOS R6 Mark IIを買おうと思う。
(以上、高い方を買う自分に対する言い訳でした……(汗))
(村上タクタ)
【関連記事】
関連する記事
-
- 2026.02.19
大陸の真ん中で、「観光」が「沈没」になった。【H-D偏愛主義】
-
- 2026.02.12
【旅とハーレーと日々の風景】CVO ROAD GLIDE ST
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)














