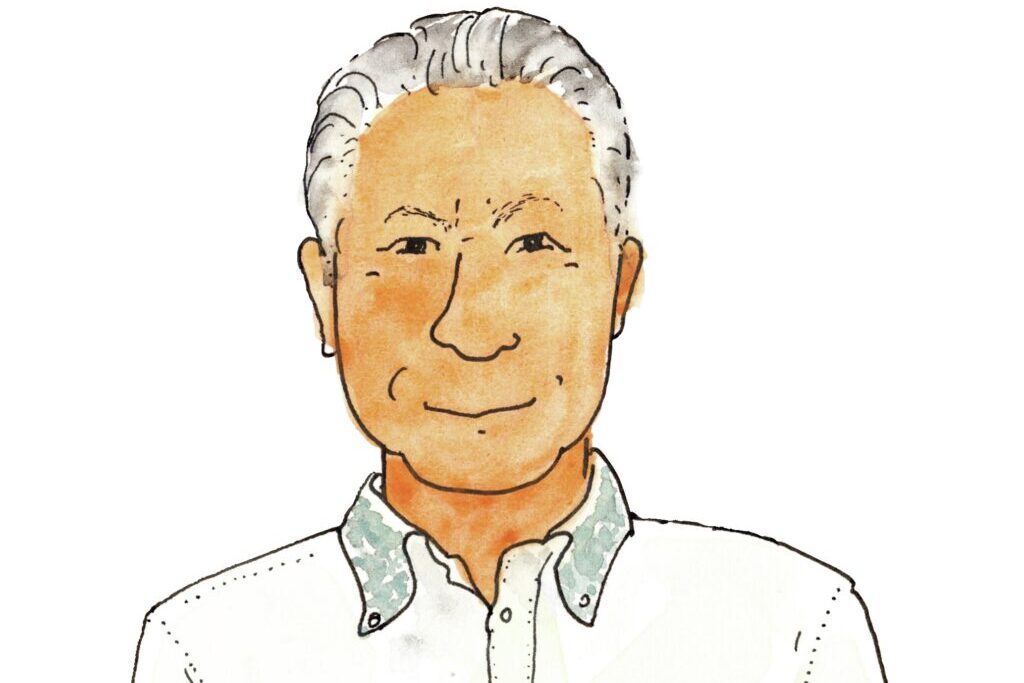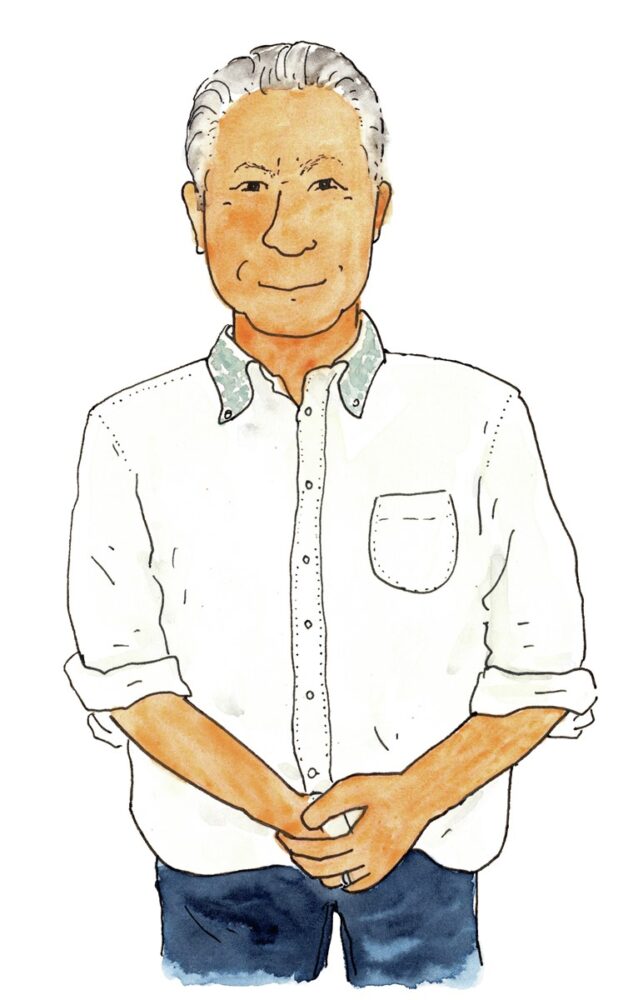
目覚めはやっぱり「VAN」だった
日本におけるアメカジムーブメントの礎を築き上げたリビングレジェンドたちの貴重な証言を、Ptアルフレッド代表・本江さんのナビゲーションでお届けする連載企画。今回ご登場いただくのは、こだわりのもとに型数を絞ったシャツやデニムなどベーシックかつ上質なデイリーウエアを展開する「ハンドルーム」代表・藤澤緑朗さん。ファッションへの目覚めはご多分に漏れず「VAN」がきっかけだったと当時を振り返る。
「小学校3年生時分、8歳上の従兄からもらった『VAN』のオックスフォードBDシャツ。台衿やカフスは擦り切れていたものの祖母に修理してもらいながら大切に着続けました。モノが少ない時代に“本物”に触れられた喜びは格別で、今でも鮮明に覚えていますね」。
四国は松山で生まれ育った藤澤少年にとってその着古されたBDシャツはただのお下がりではなく、ファッションを初めて意識した瞬間でもあった。
「ぼくの地元には『サツキハウス』や『ミスターショップサツキ』といったメンズショップがあり、『VAN』を中心にアメカジからクロージングまで幅広く展開していて、放課後は毎日のようにサツキハウスに通い、お年玉も小遣いも全部洋服か『メンズクラブ』に使ってしまう中学生にいつしかなっていました(笑)」。
「VAN」倒産の衝撃と東京での青春時代
ファッションを生業にすべく高校卒業後には今はなき代々木のメンズファッション専門学校へと進学。
「専門学校の入学式の日に、まさかの『VAN』倒産を来賓祝辞で知らされてショックで倒れそうになりましたよ(笑)」。
1978年、二十歳の誕生日と重なったその出来事は、若き藤澤さんにとって忘れ難い転機となったが、同校で培ったコネクションを通じて果敢にも業界の最前線に飛び込んでいく。
「授業が終われば、齋藤久夫さん(TUBE)や村松周作さん(COZO)の事務所に図々しくお邪魔したり、業界人御用達として知られていた原宿の喫茶レオンでは菊池武夫さんや松田光弘さんの隣に座って耳をダンボにしていました。あまり真面目な生徒じゃなかったけど(笑)、そういう時間が僕には大きかったと思います」。
夜は新宿ツバキハウスに通い詰め、昭和サブカルチャーの渦中を体感しながら先達の立ち回りを貪欲に吸収していった。
苦闘の日々が続いたキャリア初期
卒業後は80年代に隆盛を極めた国産アメトラブランド「エーボンハウス」に入社。
「当初は物流担当。その後は配送や検品、梱包まで何でもやりました。『そろそろ終電なので、お先に失礼します』が唯一の免罪符だったブラックな時代(笑)。夕飯も食べられず体を壊したほどです」。
2年足らずで退社するが、その後も複数の会社で企画や買付けを経験し、10年をかけて業界での足場を固めた。そして1990年、満を持して「エブリマン」を設立。しかし、時はバブル崩壊直前。
「新参者が持ち込んだサンプルでは商談すら応じてもらえませんでした。そんな折、元上司から『「ビームス」を辞めた重松さんたちが新しい業態を始めるから手伝え』と声がかかったのです」。
VAN好きが高じエーボンハウスにて商品部に配属

メンズファッション専門学校の同期たちと過ごした青春時代を筆頭に、藤澤さんの歴史を語る思い出の写真たちを誌面では紹介していただいた。82年、ニューヨークデザイナーコレクティブ会場では、かのモハメド・アリとともに、同年9月にはロンドンの直営店にてマーガレット・ハウエルさんと2ショットも。他の集合写真にも「シップス」メンズクリエイティブアドバイザー鈴木晴生さんの若かりし姿も見られる。


1980年代に製作されていた「エーボンハウス」のアイテム。新入社員のころに購入したというオフホワイトレタードカーディガンは、メリノウールを使ってマカオのニット工場で編まれた秀作。コットンパイルのネイビーブレザーは、夏場のちょっとした正装として活躍。シルクニットタイも英国のファクトリーに別注したもの。どれも相当なこだわりで作られたアイテム群である。


「エーボンハウス」のアウトドアライン「アーガイルクラブ」。1980年に作られた。「今見ても素晴らしい縫製と素材、仕上がりですね」と藤澤さん。
- 1
- 2
関連する記事
-
- 2026.01.21
雑誌「2nd」の看板スタイリスト・吉村祥吾の「撮影前夜、事務所にて」第5回
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)