金沢21世紀美術館での個展に至るまでにあったこと
金沢21世紀美術館で10月18日から開催されているSIDE COREの個展は、能登との出会いと震災後の経験が軸になっているという。2018年の珠洲滞在をきっかけに始まった縁は、2023年の「奥能登国際芸術祭」への参加、そして震災後の土地の人とのつながりを経てさらに深まっていった。
地震で隆起した海岸を記録した映像《new land》の制作や、金沢のアートスペースや美術館による企画「Everything is a Museum」への参加、さらにレジデンスプログラム「AIR KANAZAWA」では、SIDE COREからの呼びかけに集まった人々と一緒に能登を訪れるビジティングプログラムや瓦礫を用いた野焼きを行い、地域との交流を重ねてきた。
今回の展覧会「Living road, Living space|生きている道、生きるための場所」は、金沢と能登をつなぐ新たな関係を示す試みだ。ストリートカルチャーの思想を背景に、移動や出会いから生まれる予期せぬ出来事を展示に取り込み、美術館を旅の中継地点のような場へと開いていくという。
—— まず、金沢21世紀美術館での個展に至る経緯から聞かせてください。
高須咲恵(以下、高須) 最初のきっかけは2018年ですね。友人で今回の個展にゲストアーティストとしても参加している細野晃太朗さんが珠洲に3か月半くらい滞在していて、その時に遊びに行ったのが最初でした。で、2023年に「奥能登国際芸術祭」に参加したのがふたつめのきっかけです。その年の5月に地震があって開催が延期になり、9月から11月まで展示しました。その2カ月後にまた大きな地震があって、展示していた場所やお世話になった人たちも被害を受けたんです。
松下徹(以下、松下) その頃に金沢21世紀美術館の学芸員・髙木遊君と連絡を取っていて、彼の「Everything is a Museum」という企画に誘ってもらいました。震災後にアーティストランスペースやオルタナティブスペース同士が交流し、議論する企画で。そこでSIDE COREとして作品を出すことになったんです。
西広太志(以下、西広) 美術館も天井のガラスが落ちて閉館してしまって。展示が止まった作家たちの作品を一時的に別の場所に移したり、そういう動きの中で僕らも関わりました。
松下 その企画で髙木君から「奥能登芸術祭に出ていた経験を生かして作品を作ってほしい」と言われて、《new land》という映像を作りました。能登半島地震で最大5.5メートル隆起した海岸に行って、鳥笛で鳥を呼んで、持ってきた魚をあげようとする様子を撮影したんです。生態系の始まりみたいな瞬間を重ねた作品ですね。急ごしらえというより、あの場の状況を記録する意味が強かったと思います。そのあと髙木君が「レジデンスに参加して個展もやらないか」と提案してくれて。活動全体を紹介する以上に、奥能登との関わりを主軸にしたいという意図がありました。



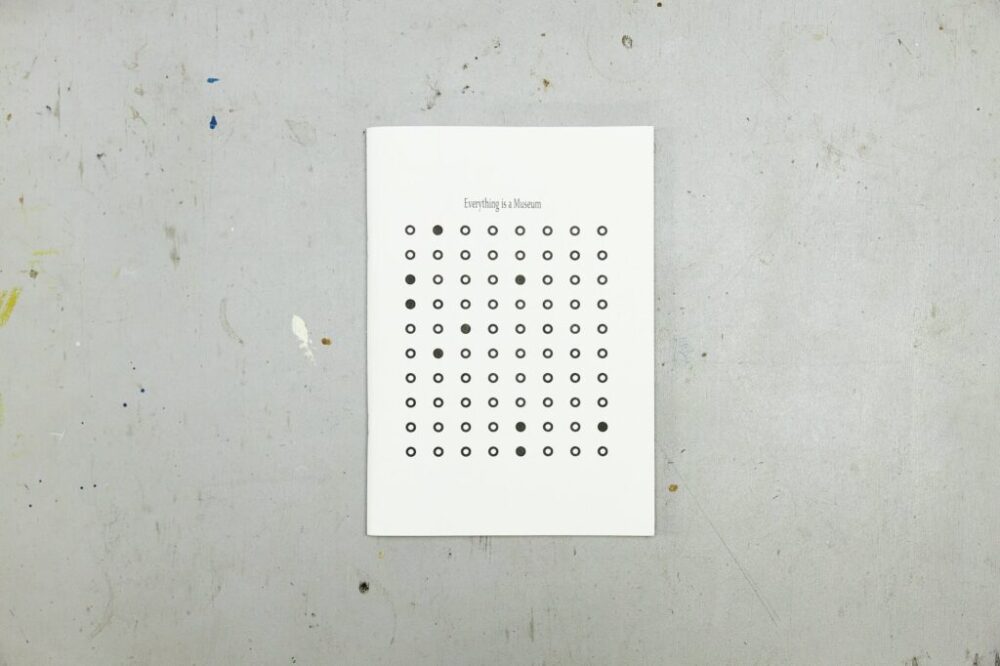
「僕らの珠洲の見方をシェアすることで、それぞれの人が行動を起こすきっかけになれば」
—— 2024年9月から約一年半、金沢21世紀美術館が主催する「AIR KANAZAWA」というレジデンスに参加されていたと伺いました。主にどのような活動をされたのでしょうか?
高須 レジデンスではビジティングプログラムをやりました。能登のことを気にしていた人たちとともに訪れ、自分たちが展示していたけど今は入れない場所を遠くから見たり、知り合いを紹介したり。そういう、自分たちなりの考え方について話したりとか、見てきたところへ一緒に訪れるっていうことをしたんです。それと同時に美術館で1日かけて野焼きもしました。ボランティアで泥出しをしたときに出た粘土質の土をもらってきて、倒壊家屋の瓦礫を燃料にして焼いたんです。9時間くらいかかるので、その間に能登のことを話し合う場にもなりました。
西広 瓦礫は許可を取って集めて、福井の会社で炭にして燃料にしました。だから能登のものを使って作品を作ったと言えますね。
松下 レジデンス中のリサーチの中で「旧ジャンボリー」って呼ばれる震災瓦礫の仮置き場を見ました。本来は全国からボーイスカウトが集まってキャンプする場所です。広大な土地一面が瓦礫で埋め尽くされていて、これは何かしなくちゃなと思ったんです。地震直後は「ボランティアは不要」と報道されていて、行きたくても行けない人が多かった。道も限られていて、インフラも復旧していなかったから。でも僕らは現地の様子を知っていたので、人を連れて行って紹介しようと思ったんです。僕らの珠洲の見方をシェアすることで、それぞれの人が行動を起こすきっかけになればと。
西広 震災から1年経って、地域の人も「来てほしい」「現状を伝えてほしい」、それから「楽しいことをしたい」という雰囲気に変わっていました。だから人を連れて行くことに意味があると思ったんです。
松下 野焼きの土も元々、僕らより先にボランティアに来ていた陶芸家の方が「この土は焼き物に使える」と言ってくれて、それをボランティアリーダーの方がとっておいてくれ、実際に活用しました。その炭を別のアーティストに渡して壁画制作に使ってもらうなど。人の行動がつながっていくのを実感しました。


「ストリートカルチャーは特定の都市に閉じたものじゃなくて、人の移動や文化的なつながりで育ってきた」
—— 今回の展覧会のテーマに「異なる場所をつなぐ表現」とありますが、それはどういった意図なのでしょう?
松下 ストリートカルチャーやカウンターカルチャーの基本的な思想として、ローカルな文化が結びつくことを重視しています。金沢から能登への繋がりをどう作るか。ただ半島を題材にすればいいわけじゃなく、自分たちなりの方法で関係を表す必要があると思いました。だから「Living road, Living space|生きている道、生きるための場所」という企画にしたんです。土地に根ざしたテーマに取り組むのはこれまでもやってきたことです。横浜では都市、東京では歴史やストリート。背景には東日本大震災があります。東京と他地域とのつながりを考えることは、SIDE COREの活動に一貫して流れています。ストリートカルチャーは特定の都市に閉じたものじゃなくて、人の移動や文化的なつながりで育ってきた。ウッドストックやサーフカルチャーもそう。移動とともに発展してきた文化をどう表現できるかを考えています。
西広 あと、ひとりじゃないからっていうのもあるかもしれないですね。誰かがあっちに行こうと言ってくれると、それに付いて予想外のところに行くみたいなこともあるのが大きいですね。
高須 あとは移動は好きです。私が一番移動したいって言ってるかも。どこか目的地があってそこに行きたいっていうことじゃなくて、つねに移動してる状況にしたいと思っています。
—— 今が準備の佳境だと思うのですが、今回の展示はどんな内容になりますか。
松下 館内の1/3くらいを使って、普段有料になっている展示室を開放して無料ゾーンを広げます。新作で大きなプロジェクトは、移動をテーマにしたロードムービー的な映像作品。過去作も合わせて展示します。それに加えてゲストアーティストも参加します。アメリカ人のアーティスト、スティーブン・ESPO・パワーズ、ストリートスケーターで映像監督の森田貴宏さんにはスケートパークを作ってもらいます。能登に行くきっかけを作ってくれた細野さんにはイベントを企画してもらい、予想できない人との出会いや、予想外の出来事を展示に反映していく予定です。
西広 準備段階からイベントをやって、2018年から細野さんが関わっていたカレー屋さんにも出てもらったり、知り合った人に出演してもらったり。地元の若い世代ともつながってきました。美術館の地下シアターを使った音楽イベントなんかも試みています。



「ただ能登を題材にすればいいわけじゃなく、自分たちなりの方法で関係を表す必要がある」
—— 最後に、展覧会づくりのプロセスで特に大事にしている点を教えてください。
高須 能登とのつながりですね。展示空間の完成度だけじゃなく、人を訪ねて、関係を紡ぎながら進めていくことを大切にしています。
西広 能登には月一回は通ってます。素材を集めたり祭りに参加したり。そういう継続的な関わりが作品にリアリティを与えると思っています。
松下 「移動そのもの」に価値を見ています。目的地に到達することより、その間にある体験や交流が重要なんです。金沢21世紀美術館は観光客も多いけど、旅の中継地点でもある。展覧会もその一部として機能すればと思っています。


(出典/「
Photo/Yoshika Amino Text/Risako Hayashi
関連する記事
-
- 2026.01.23
絵画の世界に迷い込む! 『プラド美術館所蔵品VR展』を見てきた
-
- 2025.12.10
50年代のボウリングシャツのような佇まいがたまらん!
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)









