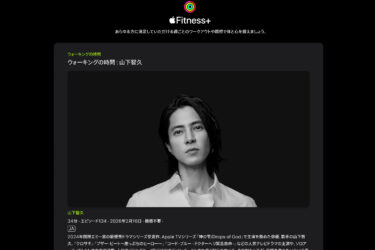日本でもこの12月から『スマホ新法(スマートフォンにおける競争確保に関する法律案)』が施行される予定であり、法律の運用次第では同じことになる危機に瀕している。ジョズウィアック氏は、「日本にはEUの轍を踏んで欲しくない」と語った。
※写真はiPhone発表会のKeynote動画から引用。インタビュー時のものではない。
EUでは、『ライブ翻訳』も『iPhoneミラーリング』も使えない
インタビューの話に移る前に、最新の情報を解説しておこう。
現地の法律に基づくと、多くのユーザーの個人情報が漏洩してしまう可能性があるため、アップルは多くの機能をEU圏内でローンチできていない。
たとえば、MacからiPhoneを操作する『iPhoneミラーリング』や、今話題のAirPodsを使った『ライブ翻訳』もEUでは提供できない。
たとえば、ライブ翻訳はAirPodsとiPhoneがシームレスかつ強力に連携することが必要不可欠で、両デバイスからの音声が統合され、iPhone上でApple Intelligenceを使って翻訳される。しかし、EUの規制に則ると、アップルは他の開発者にも複数のマイクを利用するAPIを許可しなければならなくなる。しかし、他企業がアップルの提供するユーザーのプライバシー、セキュリティ、誠実さに関する高い保護基準を満たすことは困難だし、そもそも喜んで情報を取得するかもしれない。
また、最近、アップルはEUに対して『iOSの通知機能』『近接ペアリング』『ファイル転送手段』『自動Wi-Fi接続』『自動オーディオ切り替え』などの規制除外を申請していたが、その全てが却下されたという。
EU圏のiPhoneでは、これからは個人情報が他企業に公開された状態になるか、これらの機能は今後使えなくなるかの二者択一だ(アップルは個人情報保護を優先して後者を選ぶと思う)。
日本のスマホ新法の実際の運用はこれから定まっていくが、もしEUと同様の方針が採られるようであれば、日本でもライブ翻訳、iPhoneミラーリング、近接ペアリング、AirDropなどが順次使えなくなっていく可能性がある。これはどう考えても避けたい事態だ。
人々の対話を促進するはずのライブ翻訳が、規制されて断絶を生むなんて、あまりにも悲しいことだ。特に多言語社会であるヨーロッパにおいてこそ、役立つはずの機能であるにも関わらず。
欧州委員会の無茶な要求
インタビューにの話に戻ろう。ジョズウィアック氏が語った話の核心は、EUで導入されたDMAの規制が、スマホ新法を含む他国の政策にも同様の影響を及ぼしかねないという危惧にある。彼は「ユーザーのプライバシーとセキュリティ保護を損なう」「イノベーションを妨げる」と、強い言葉で警鐘を鳴らす。
中でも彼が繰り返し口にしたのは、「相互運用性(interoperability)」という概念である。欧州委員会の言う「すべての製品と連携させろ」という指示は聞こえは良いが、それほど簡単な話ではない。

アップルはこれまで、数十万のAPIを開発者に公開しつつも、製品全体の体験が「魔法のように動く」よう設計してきた。カメラやマイク、連絡先、位置情報サービスなど、多くの要素を慎重に統合することで、一貫したユーザー体験を築いてきた。しかしDMAでは、こうした独自の体験すら他社製品に開放することが求められる。それは『魔法』を『最低限の機能の寄せ集め』にしてしまう危険を孕んでいる。
我々の個人情報を公開せよというEUの要求
たしかに『透明性』や『ユーザーの保護』といった理念は素晴らしい。だが、その理念を実現する手段によって、逆にユーザー体験や技術革新が犠牲になってしまっては本末転倒である。
たとえば、通知の内容、Wi-Fi接続履歴、位置情報、端末の利用履歴といった極めて機微な情報を開示させられるようなルールは、アップルにとっても、ユーザーにとっても大きな問題である。
だが相互運用性を理由に、これらの情報開示が義務づけられ、秘密保持義務すら課せられないケースが規制案に含まれているという。ジョズウィアック氏は、「これはユーザーにとって本質的に危険な要求」であり、「政府や企業が『簡単で良いことだ』と思い込んで規則を押し込んでしまうこと」の恐ろしさを指摘する。
EUからの要求には驚くべきものもあったという。
たとえば、過去に接続したすべてのWi-Fiネットワークの履歴を共有せよ、デバイスに届いた通知の内容を完全に提供せよ、という項目もあるという。
Wi-Fiネットワーク履歴を知れば、病院や裁判所、宿泊したホテル、不妊治療クリニックなど、ユーザーが訪れた場所が一目瞭然になる。
スマートフォンには非常に機微な情報が詰まっている。アップルは常にそれを最大限尊重し、責任を持って扱ってきた。これらはアップル自身ですらアクセスできないように設計してきた極めて機微な情報だ。アップルのサーバーには保存もされていない。すべてはデバイス内だけに存在する。しかしEUの規則では、利用目的に関係なく他社に提供せねばならない。そして利用条件すら課せないのだという。
これでは、これまでアップルが守ってきたプライバシーがすべてさらけ出されてしまう。
ジョズウィアック氏は、スマホ新法について「日本にはEUの轍を踏んで欲しくない」と語る。
日本はどうすればいいのか?
なぜEUはこんな奇妙な方向に進んでしまったのか。そしてなぜ、日本も同じ轍を踏みかねないのか。多くの方にとって不思議だと思う。
さて、ここからは筆者の私見だ。
おそらくは、欧州委員会の競争総局では、欧州企業の競争力を高めるために、なんであれシリコンバレー企業に制限を与えることが評価されるのだと思う。ある意味、日本の公正取引委員会にもそういう風土があるのだろう。
たしかに、’90年代以降のビッグテックの躍進は世界をあまりに席巻してしまっている。
音楽を聴いたりアプリを使ったりすればアップルに、買い物をすればAmazonに、広告を見ればGoogleに、検索すればまたGoogleに、AIを使えばOpenAIなどに——どんな行動でもビッグテックに対価が流れてしまう仕組みができてしまっている。
となると、もはやヨーロッパとしては、ルールを変えるしかない。オリンピックやF1でもよくある話だが、ヨーロッパにはさまざまな機関の本部があり、ゲームに負けそうなら、ルール自体を変更してしまうということがよくある。もはや場外乱闘をしないと、お金の流れは変えられない状態だ。
それは確かなのだが、日本が欧州の場外乱闘に追従しても利があるとは思えない。
アップルをはじめとするビッグテックは、基本的には資本主義のルールに則っており、その多くは正しく、リベラルで、倫理的である。しかし、正しいだけではどうにもならないことがある。むしろ、正しさは刃であることもある。資本主義の正しさを追求した結果、生活が苦しくなった人達が、正しいことを度外視する首長を選んでしまったのが今のアメリカだ。
日本はそのバランスを見誤ってはいけない。アップルの正しさだけに付き合うのも苦しいが、EUの場外乱闘的なルール変更に付き合うのも良くない。
ぜひ日本政府には、「和を以て貴しとなす」の精神で、技術革新とユーザーの安全の両立を目指した折衝を期待したい。我々が安全に、便利に、そしてプライベートな情報を守られながらアップルの新しい体験を享受できるように。
(村上タクタ)
関連する記事
-
- 2026.02.19
Apple Fitness+継続してる? 頑張ったら筋肉痛に!
-
- 2026.02.16
表参道でToday at Apple『研修医のあおい』さんのGoodnotes活用術
-
- 2026.01.31
心配されたスマホ新法の運用だが、我々アップルファンにとって最悪の事態は避けられたようだ
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)