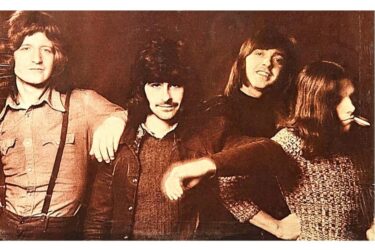斬新なリズムやビート面でアプローチをする時代

しかしながら、このアルバムはファンにとっては微妙な内容で、心から喝采を送りたいと思う傑作ではなかった。先行シングルの「プレス」こそ、ポールのポップ感とデジタルが融合したサウンドに新機軸を感じさせたものの、アルバムに収録された10曲の中に「プレス」で感じた高揚感を抱かせる曲はなく、逆にどうしてしまったの? と戸惑いさえ感じさせる曲のほうが多かった。
前年末に放送された『ベストヒットUSA』でのインタビューの中でポールは「いまレコーディング中のアルバムはとてもハードでヘビーなロックサウンドになる」と発言しており、その言葉通りの内容を期待していたが、実際はリズムやビートに重きを置いたという意味のもので、つまりそれは時代に即したサウンドにアプローチしたサウンドであるということを、アルバムを聞いたあとに理解した。
この時代の音楽シーンはパワー・ステーションに代表されるような迫力あるスネアが人気を博し、あるいはプリンスが試みていたようなシンセを用いての実験的なドラムセクションに注目が集まるなど、メロディよりもリズムで驚かせることが重要視されていた。いかにリズムやビート面で斬新なアプローチをするか、というのが時代のトレンドであった。
一時代を築いた大物のベテランであっても同時代性を意識するのはアーティストの性であり、ポール自身もソロ以降も常に時代のトレンドに寄り添って作品を作り続けてきたわけだから、『プレス・トゥ・プレイ』の制作意図も理解できる。だが、悲しいかな。センスと時代感にズレがあり、そのギャップが大きな溝になってしまっているような印象。何度も聴き返し、好きな曲もあるにはあったが、アルバム全体として今一つ好きにはなれなかった。
それは最初に10曲入りのLPレコードで聞いてしまったからかもしれない。あとから13曲入りのCDを聞けばまだ全体像をつかむことができたが、当時わたしはまだレコード派だったので、レコードしか聞くことが出来ず、10曲ではポールのやりたかったことを十分に理解することは難しかった。
ずいぶんあとになってから、そもそもこのアルバムは10CCのエリック・スチュワートとのコラボで進められていたということを知る。『タッグ・オブ・ウォー』『パイプス』『ブロードストリート』に参加して自分のフォロワーのようなエリックとメロディアスな曲を作っていたのが、途中でヒュー・パジャムが入ってきて事態が変わってしまったのだとか。そういう事情であればこうなってしまったのが理解できる。
映像面は充実していた『プレス・トゥ・プレイ』
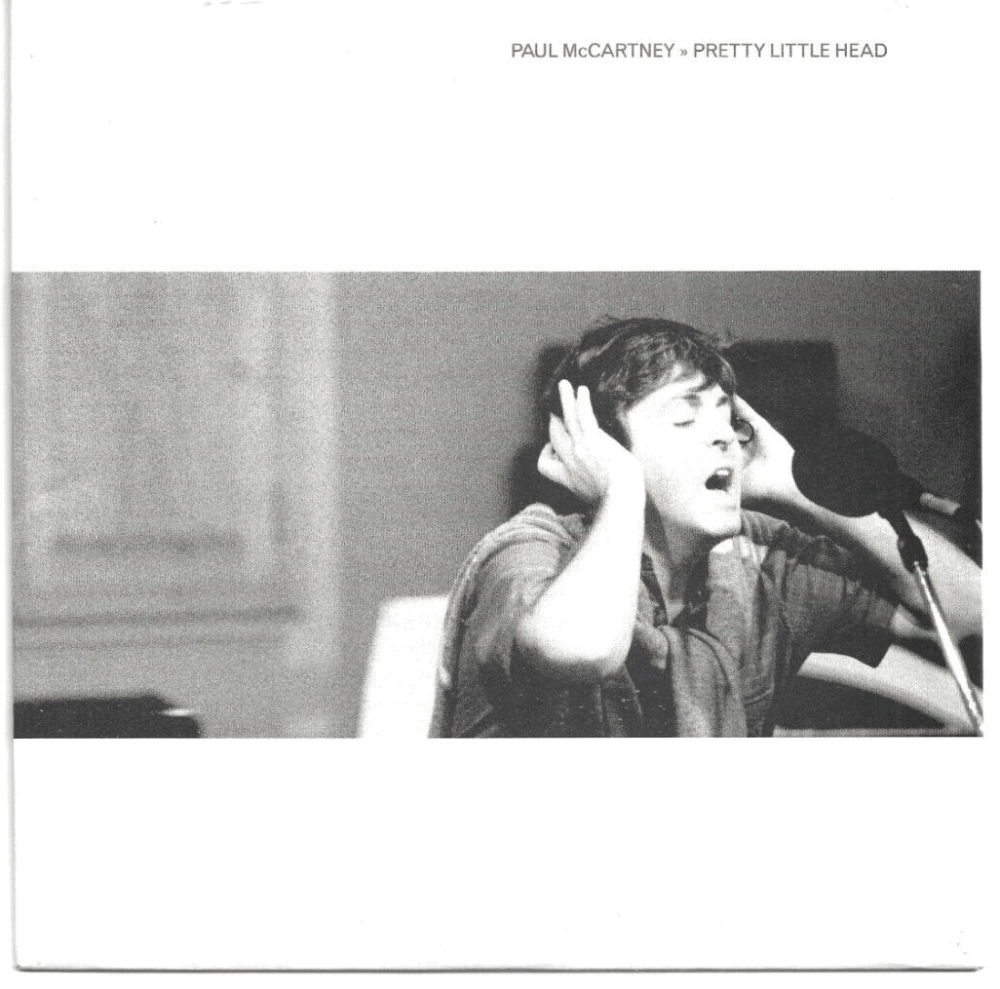
それでも『プレス・トゥ・プレイ』には特筆すべきことがあった。それはビデオクリップである。このアルバムシングルカットされた曲のビデオはいずれも秀逸で、見どころは十分。MTV出身といわれたほかのアーティストの作品と比べてもクオリティも申し分なかった。ビデオクリップを最初に作ったのはビートルズと言われるから、まさに面目躍如というべき、力の入れようだった。
最初の「プレス」は、ポールがロンドンの地下鉄に乗って、周囲の反応を撮影するというゲリラロケの様子が楽しい。2本目の「プリティ・リトル・ヘッド」はポールの登場シーンは少ないが、実験性の高い曲を独創的な映像演出で表現するクリエイティブが素晴らしい。冒頭の「シーズ・リーヴィング・ホーム」が流れるのも気が利いている。そして3本目の「オンリー・ラヴ・リメインズ」は曲自体は目新しい部分は全くない、ポールなら目をつぶってでも書けそうなラブソングの演奏シーンをワンカメで撮影するというもの。『ポッパーズMTV』でピーター・バラカンが絶賛していたことを覚えている。また、日本とアメリカでのみシングル発売された「ストラングル・ホールド」は、「セイ・セイ・セイ」のクリップをベースにしたような演出だが、全体にバンドを率いての演奏シーンがフィーチャーされており、ただライブシーンが見られるというだけでうれしいクリップであった。
アナログとデジタル、音楽と映像。そのバランスのとり方に気を取られて、全体が散漫になってしまったという部分もあるのかもしれない。
『ロッキング・オン』に載った写真の衝撃

最後に触れておきたいのは、雑誌『ロッキング・オン』である。同時期に発売された、表紙は確かプリンスの号の巻頭にポールのインタビューが掲載されたのだがここに使われた写真に衝撃を受けた。
この頃、同誌にビートルズ関連の記事が載るのは松村さんの原稿だけで、ディスクレビューはあってもインタビューが載ることは珍しかった。『タッグ・オブ・ウォー』は松村さんが現地取材していたので記事はあったものの、『パイプス』『ブロードストリート』についての記事はなく、それゆえこの号はポールのインタビューが掲載されているとのことで喜び勇んでページを開いたものであった。しかし、そこに使われたポールの、短髪七三分けで顔中しわだらけの写真に落胆した。それまではどの写真を見ても若くてチャーミングに見えていたのに、この写真は急に老けたおじいさんのようで、たとえるならまるで欽ちゃん。
白黒だったというのもあったのかもしれないが、自分の好きなポールはもはやこれまでかと、まで思った。はたしてなぜそんな写真を使ったのか。編集者の悪意を感じるほどであった。『プレス・トゥ・プレイ』を聴く度に、この記事のことを思い出す。
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)