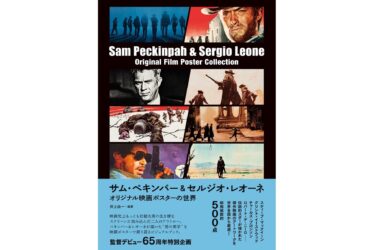木目を出したい部分をガスバーナーで燃やしてから削るという技法で、一般的に「ウッドバーニング」と呼ばれることもあります。ウッドバーニングのワークショップなどを開いている大学の友人から教わって以来実践しているんですが、なかなかコントロールが難しいんです。燃えすぎると潰れてしまったりするんですが、私はむしろそれが好きですね。美術ではよく「偶然性」という言葉も使われますが、偶然というよりも、木がこうしたかったんだろうなって、自然と一緒に作っている感覚で。作品を作るってこういうことだよなって。その感覚を大事にしています。
──ブルーシートや透明のビニールシートに刷られた作品もありますが、素材の選び方に意図はありますか?
ありますね。「見えないことにされている存在」を可視化したいと思って。ブルーシートって、日本ではたとえばホームレスの方が生活のために使っていたりして、社会が見ないふりをしてしまっているものだったりする。でもヨーロッパに行ったとき、ホームレスの方も堂々と世界遺産の前に座っていて、一緒に生きてるぞみたいな感じがした。それからスマホ社会で置き去りにされる高齢者とか、存在しているのに透明化されることへの違和感がずっとあって。だからこそ、対象を透明なビニールに刷ることで、「透明化できないよ」と示したかったんです。
──TARO賞に出品された《春の気立つを以って也》(2025)も、ご祖母を題材に透明なシートに刷った作品でしたね。
祖父が亡くなって、祖母がはじめてひとりの部屋を持つようになって。最初は寂しがるかと思ったんですが、むしろ元気になっていったんです。私もずっとおばちゃんとして見ていたけど、「祖母」や「妻」という役割から解放され、友達と長電話したり、ひとりの女性として時間を過ごしはじめた祖母の姿がとても印象的で。その姿を作品に残したいと思いました。

──高さが5メートル近くあるという巨大な作品でした。制作が個人の範囲を超えてプロジェクト化していってるのも面白いですね。
彫っているときは孤独だし、ひとりなんですが、刷りの作業は友達に手伝ってもらっています。家での制作中も、電話しながら作業したり、友人と話すことで考えがクリアになることも多いです。その友達がいないと作れないくらいの感覚です。作品は人との関係の中でできていく感じがありますね。
──今回の個展はどんなテーマで始まったんですか?
家という場所をテーマにしました。祖母の肌の皺と、長年住んだ家の壁や床の傷が重なるように感じる瞬間があって、人と家が一緒に時間を刻んでいくイメージで構成しました。私の展示場所はホワイトキューブではないなってずっと思っていたなかで、会場の「オープンレター」を知り、ここに住んでいる山内さんにも意見を伺いながら設営して。ギャラリーでありながら暮らしの場でもある空間を探していたので、理想的でした。
──会場全体を使った大きな作品がカーテンのように揺れて、作品のなかに入り込むような感覚です。
最初はもっと小さいつもりだったんですが、考えているうちにどんどん大きくなって、6メートルの作品になってます。祖母が寝てる姿なんですが、胎児みたいな体勢になっています。これが人間なんだっていうのを見せたくて。今までとちょっと変えて、より抽象的なものになっています。
関連する記事
-
- 2026.01.23
絵画の世界に迷い込む! 『プラド美術館所蔵品VR展』を見てきた
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)