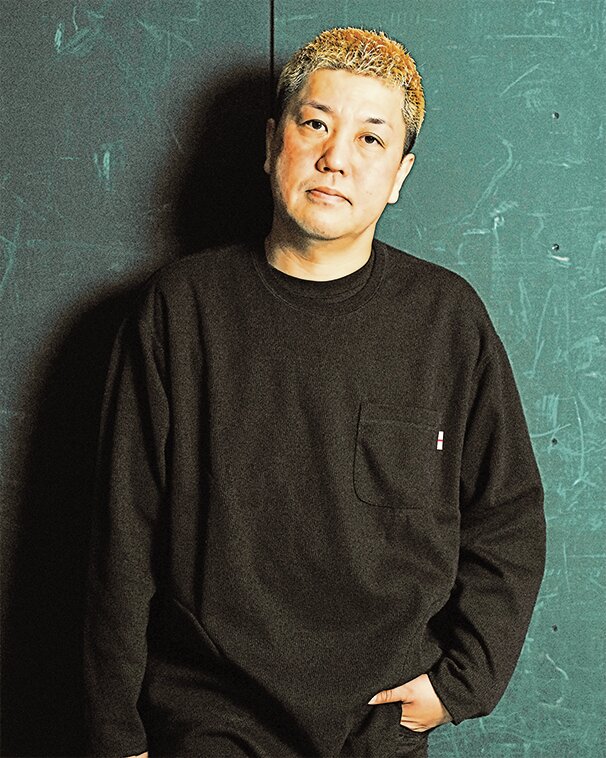
1.コンバース「キャンバス オールスター ハイ」(1917年)|ほぼすべての人類の脳内に刷り込まれてる靴って他になくない?

原型が誕生したのは1917年。元プロ選手にして同社の営業マンとなったチャック・テイラー氏の尽力によって、20年代からバスケ界に普及して以降、60年代前半まで、なんと40年近くに渡ってプロユースのバッシュとして輝きを放った。その功績によってアンクルパッチに同氏の名が刻まれていることは著名な話だろう……みたいな堅苦しい“語れる歴史”なんて、この靴のほんの一面にすぎない。
「キャンバス生地のアッパーにラバーソール用いた、いわゆるヴァルカナイズ製法で仕立てた靴は、100年以上の歴史を持つ、クラシックの極致。今作はその源流とも呼べる傑作ですが、凄いのは誰もこれを“昔の靴”なんて思っていないこと。むしろバリバリの現役。要は完成されてるんですよね。軽くて通気性もいいし、ソールも加水分解しづらい。見た目もクセがなくて、性別も年齢も国境も服の嗜好も関係なく履ける。
例えば昔のモッズの人たちなんかは、トゥの切り替えがあるから正統なストレートチップの代わりだ! なんて、スーツのハズしとして使ってたくらい。ここまで多様な文化に長く添い遂げているスニーカーはそうない。”米国製じゃないと”とか、“○○年代はトゥが細くて”なんてのは、この靴の本質じゃないんですよ」
1足目からこんなこと言うと身も蓋もないけど、要はロジカルに理屈立てなくても、すでに僕らの脳内にインプリント済みってことが、歴史に残る何よりの理由ってこと。以上。
2.オニツカ タイガー コルテッツ(1967年)|日本初世界の先駆。

「このモデルがなければ今のナイキは存在しなかった。そう言い切れるれくらいスニーカー界にとっては重要な意味をもつモデルだと思います」
ナイキの創設者フィル・ナイトが日本のオニツカ本社を訪れたのは1962年。当初はまだ設立前だった“ブルーリボン・スポーツ”という架空の社名を用いて、代理店契約を結ぶことに。その後かつての陸上の恩師ビル・バウワーマンとともに、本当にブルーリボン・スポーツを設立すると、輸入されてきたモデルを販売するかたわら、オニツカサイドへ改良点のフィードバックも重ねていった。
そして1967年、彼らのアイデアを具現化し、晴れてオニツカが“タイガー コルテッツ”を発売。当時としては画期的だった分厚いクッションとキャッチーなデザインが奏功して、見事大ヒット!……したものの、両者の関係は徐々に冷え込んでいく。
「両者が決別した71年にナイキが創設されると、72年にスウッシュをまとった“タイガー コルテッツ”を、“ナイキ コルテッツ”として発売。市場には2つのコルテッツが存在し、商標を巡る訴訟に発展しました。結果はナイキの勝訴。商品名変更を余儀なくされたオニツカは、モデル名を“タイガー コルセア”に変え、今に至ります。
まさにナイキ誕生の契機になった名機。これがなければあの名画のあのシーンもなかったはず。何より日本が世界にインパクトを与えた草分け的モデルとして、リスペクトせざるを得ません」
3.アディダス スタンスミス(1971年)|テニスのレギュレーションをクリアすべく生まれた究極のエレガンス。

テニスに厳格な服装のレギュラーションが存在していることは有名だ。かくいう今作も、今でこそファッションの定番と目され、ギネスブックに“世界で最も売れたスニーカー”なんて認定されているけれど、元を正せばリアルガチなテニスシューズとして開発された。
「ただこの地位を築き上げるまでの経緯にこそ、ドラマを感じるんです」と、国井さんが惚れ込む理由を、レッツ・オサライ。
実はこの名機は元々フランス人テニスプレイヤー、ロバート・ハイレのために開発され、65年に彼の名を冠して(英語読みで“ハイレット”として)発売された。が、ハイレがほどなく引退したため、アディダスは71年にアメリカ人選手スタン・スミスと契約。ハイレを着用させることになったのだが、スミスが勝利を重ねるうちに、ハイレとスミスの名前が併記されるようになり、70年代末になるとスミスの名だけが残されることになったそうな。
「ハイレにとってみれば相当切ない話し(苦笑)。ただどちらの名前にしろ、この靴が凄いのはテニスのレギュレーションをクリアするために、白を基調としながらもしっかりデザイン哲学が息づいていることです。お馴染みの3ストライプがパンチングで表現されてるのも、華美にならないための配慮。その副産物としてミニマルかつエレガントな顔つきになり、時代も用途も超越する普遍性も獲得することになった。間違いなくコートシューズの頂点だと思います」
4.プーマ クライド(1973年)|スポーツシューズからブラックカルチャーの象徴に。

始まりは68年のメキシコ五輪。プーマの“クラック”というモデルを、200メートル走で金メダルを獲得した米国人選手トミー・スミスが表彰台の脇に脱ぎ置き、黒の革手袋をはめた右拳を掲げ、人種差別への抗議を表明。“ブラックパワー・サリュート”と呼ばれるこのパフォーマンスが世界に与えた衝撃は、とてつもなく大きかったそうな。
「これに触発されたからかどうかは定かではありませんが、NBAの名プレイヤー、ウォルト・フレイジャーはプーマと契約した際、この伝説的モデルをベースにした改良版を着用。73年にフレイジャーの愛称を名に冠した、バスケ界初のシグネチャーモデル、“クライド”が誕生することになったんです」。
ただまだストーリーは完結しない。彼の契約終了後も、プーマは今作をインターナショナル品番で呼称し、生産し続けたのだ。
「巷では単に“プーマのスウェードのスニーカー”と呼ばれることになった今作は、後にそのまま現在知られる“プーマ スウェード”を正式名称として、継続生産されることになったんです」
するとこの一連の流れに続く形で、80年代に入るとヒップホップシーンなどとリンク。いつしかブラックカルチャーを象徴するスニーカーの代表格として認知されることになった。
「NBAでも屈指の洒落者として知られたクライドの影響力は絶大。派生したスウェードとともに、スタイルを超越するマスターピースとして愛され続けることになったんです」
5.ヴァンズ スリップオン(1977年)|履きやすいのに脱げにくいディス・イズ・イノベーション。

一説によるとボタンは紀元前ウン千年前から存在してたらしい。けど誰がいつ作ったものなのか、今だにハッキリしたことはわかっていない。でもどうだろう。ボタンは一枚の「布」を身体にまとう「服」へと昇華させる、アナログにして究極のイノベーションではないだろうか。スリッポンもまさしくそれと同じ理由で、国井さんから歴史に残る10足に推された。
「極端に言ってしまえば僕らが学校で履いてた上履きのご本尊みたいなものじゃないですか。誰も気にも留めていないけど、サイドにゴムを備えることで、ヒモを結ばなくても『履きやすくて脱げにくい』を実現している。これ以上の機能美はないですよね。ローテクに区分されてますけど、革新性という点において後世にこれほどインパクトを与えた靴は、そう多くないと思います」
ヴァンズといえばスケートカルチャーに深く根付いたスニーカーとしてもお馴染みだ。しかし1982年に傑作青春映画『初体験/リッジモント・ハイ』が公開されると、様相が一変。ショーン・ペン粉する主人公ジェフがチェッカーボード柄のスリッポンを履いたことで、一大センセーションを巻き起こし、限られたコミュニティの靴から、青春を謳歌するすべての若者の靴として、世界中にファンを増殖させていった。
ひょっとしたら今日本でこうしてヴァンズを履けるのも、スリッポンのおかげかもしれない。そう思うと、なるほど歴代10傑に入らない理由はない。
6.ニューバランス M990(1982年)|“グレー”の伝道師。

ニューバランスが持てるノウハウを総動員、4年もの歳月をかけ完成させたM990。“1000点満点中の990点”という謳い文句からも、その入魂ぶりは明白だ。ただ今作の最大の功績は意外なところにある。色だ。
「今でこそグレーのスニーカーは珍しくありません。ただ当時としては極めて斬新。ビビッドなランニングシューズが多い中、自社の屋台骨に据える作品にグレーを採用する先見性には感嘆します」
実は同社がグレーを用いるようになった経緯は諸説ある。筆者は以前関係者から、ジム・デービス会長が70年代半ばにアウトドア製品の展示会で見た、シルバーやグレーのスキーウェアに衝撃を受けて採用した、とする説を聞いた。しかし、国井さんが米国本社で聞いた経緯は異なる。
「ハイエンドな1000番台や、オフロード用の500番台を展開しているけれど、これからは舗装された道をランニングするのが主流になる。900番台はそのオンロード用シューズの主軸。だから街の景観やアスファルトに馴染むグレーを採用したんだ、と。つまり当時の最新技術を注ぎ込むだけでなく、前衛的な色使いでも市場に一石を投じることになったんです」
狙いが奏功してか、今作は100ドルという高値(当時の一般的なスニーカー価格の3〜4倍!)で販売されたにも関わらず大ヒット。グレーってありなんだ! を広く印象づけることとなった。グレーを当たり前にしたグレートな伝道師に、拍手。
7.ナイキ エア ジョーダン1(1984年)|“別ライン”という手法を生み出した神との邂逅。

あまりにも有名。だからこそ少しでもスニーカーにアンテナを張っている人にとってみたら、今更この靴について鮮度のあるウンチクを収集するのは、不可能に近いだろう。でも散々擦られているのは、それだけ旨味がある証拠。発売時は派手すぎてNBAからドレスコード違反とみなされ、罰金1000ドルの裁定がくだったものの、ナイキはこれを支払い続けてまでジョーダンに着用させ続けた……なんて逸話は、やっぱり何度聞いても不思議とグッときてしまう。
「もちろん逸話に事欠かない名作ではあるんですが、個人的に今作の凄さは、そのブランディングにあると思っています。バスケ界としては73年にプーマがウォルト・フレイジャーと契約し、すでに初のシグネチャーシューズを発表済みでした。しかし今作はその取り組みよりも一段上。選手の名前入りのシューズをレギュラー製品とは一線を画した、ある意味“別ライン”としてシリーズ化するというのは、初の試みだったはずです」
どうだろう。今やアスリートやアーティストなどの名を冠し、別ラインで発売するという手法は、ごくありふれたものになっている(現にエア ジョーダンシリーズに至っては、97年に“ジョーダン ブランド”として、ナイキ傘下のもと独立まで果たしている)。あまりのインパクトで各メーカーの売り方の選択肢まで広げてしまった。その観点は、この名靴にとって久方ぶりに鮮度を感じる魅力ではないだろうか。
8.ナイキ エア マックス1(1987年)|機能を視認化してデザインに昇華。

「ハッキリ言ってエアバッグそのものより、それを“視認化させる”というアイデアの方が断然凄いと思います」
そう国井さんが称賛する通り、この靴が歴史に名を刻むこととなった理由は、“機能の視認化”もとい“機能のデザイン化”にある。ナイキはすでに78年の時点で、エアバッグを採用した“エア テイルウインド”を発表していた。しかしこの靴はミッドソールの内部にエアバッグを内蔵していたため、エアの逃げ場がないという問題が。
そこでエアの容量を最大化させつつ、着地時に変形したエアバッグをサイドに逃すため、通称“ビジブルエア”を発案したのが、天才デザイナー、ティンカー・ハットフィールドだった。
「彼が着想を得たのは、パリにある総合文化施設“ポンピドゥー・センター”。配管を剥き出しにした、“機能をデザインに活かす”という手法を参考にしたようです。この作品以降エアマックスはシリーズ化され、さらに進化していきますが、エア部分に関していうと、基本的には見せる範囲をいかに広げるかという作業。日本ではエアマックスというと95の方が有名ですが、歴史という観点から見ると最初にビジブルへと舵を切った今作も見過ごすわけにはいきません」
ちなみに本作はビジブルエア以外のデザイン性においても抜きん出ていた。当時はシリアスなランニングシューズでこれほどビビッドな配色はなかったからだ。ひとりの天才のセンスが凝縮された、まさしく傑作だろう。
9.アディダス エナジー ブースト(2013年)|スニーカーの在り方そのものをひっくり返した革新作。

「今作の登場によって、各社が靴の作り方そのものを変えることになった。それほどこの靴がもたらしたインパクトは大きい。今後も語り継がれるべき名品だと思います」
国井さんをしてここまで感嘆させる理由は、今作に初搭載されることになった「ブースト フォーム」にある。そもそもスニーカーのミッドソールが担保する機能は、ザックリ言うと「反発」と「衝撃吸収」の2種類に大別される。反発力が強いと、当然脚に加わる衝撃は大きくなるが、反対に脚に優しいと、今度は反発する力が弱まってしまう。
「この矛盾を解決するため、各社は60年代後半以降、主にEVAという加工しやすい素材をミッドソールに採用してきました。これに何かを混ぜたり埋め込んだりして、相反するふたつの要素を両立させようと試みたんです」
ところがアディダスは、ドイツを拠点とする化学会社ビーエーエスエフ社との共同開発によって、TPUというまったく新しい素材の採用に至った。しかもそれを一度発泡させてから形にするという、これまたまったく新しい成型方法まで取り入れた。
「そうして見事このふたつの要素を兼ね備えた革新的ミッドソール素材『ブースト フォーム』が完成。これ以降各社は“ミッドソールの素材自体を開発する”という方向に舵を切らざるをえなくなったんです。昨今話題の厚底シューズも、この革命の延長線上にあることを考えれば、近年稀に見る先進的な靴と言えるでしょう」
10.キーン ユニーク(2014年)|スニーカーとサンダルの境界線も、フィールドの垣根も飛び越えた傑作。

アウトドアギアの進化は目覚ましい。それは例えばシュラフやレインジャケットなんかの話だけじゃなくって、シューズも同じ。どれもスペックが充実していて、国井さんは「強さも軽さも行き着いちゃってる感じがしてた」のだそう。
「ところが今作を見た時、アウトドアブランドが作る靴に初めてイノベーションを感じたんですよね。基本的に従来のスポーツサンダルの目的は、解放やリラックスにあったはず。ところが[ユニーク]はフィッティングにまでテコ入れしつつ、着用可能な用途まで拡大している。それも2本のコードとソールユニットを組み合わせるという、極めて原始的なパーツ構成だけで。既成概念を取っ払って開発された、まさにユニークなフットウェアだと思います」
既存のどの靴のカテゴリーにも入らない今作は、自らを「オープンエアスニーカー」と呼称している。厳密にはスニーカーとサンダルの中間くらいの立ち位置。だが活躍するフィールドは、そのどちらよりも圧倒的に広い。
「これまでも競技場からアスファルトへと垣根を越えた靴はあるし、スポサンをファッションとして取り入れるスタイルも定番化しています。でも[ユニーク]ほど多様なフィールドでシームレスに活躍する靴は他にありません」
格別に珍しい材料を使わずに、進取の精神とコロンブスの卵的発想だけで、新たなスニーカー像を築き上げたユニーク。これほど体を表している名もまた、他にないだろう。
※情報は取材当時のものです。現在取り扱っていない場合があります。
(出典/「2nd 2023年6月号 Vol.195」)
Photo/Yoshika Amino, Yuta Okuyama, AFLO Text/Masato Kurosawa
関連する記事
-
- 2026.01.22
ハーレー社を救った立役者!! ソフテイル誕生秘話。
-
- 2026.01.15
「アディダス」のタグの変遷とアイコニックな3本ラインの変化
![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)









